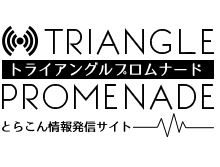『Zero The White Christmas』#00/#01*相馬貴之編
#00overture / #01/December.23
――overture
白い粉雪が舞っていた。
あたりは一面の銀世界。
少年は二人の少女と出会った。
街並みに溶け込んでしまうかのような真っ白なコート。
艶やかに輝く金色の髪。
まるで精巧に作られた人形のように整った顔。
全てが淡い色彩を持つ世界で、深く吸い込まれそうな蒼い瞳。
はじめまして。一歩前に出てペコリと頭を下げる右の少女。
こんにちは。その背に隠れるようにして一言呟く左の少女。
同じ顔、同じ声。
しかし全く別の人間であるとすぐさまわかった。
少年は手を差し伸べた。
こちらこそよろしく。
それが思い出せる一つ目の記憶。
クリスマスイブ。
欲しいものを手紙に書いてサンタクロースに願おう。
幼い少女達は、サンタクロースに何を願ったのか。
少女達の求めたものは小さな靴下には入らないものだった。
右の少女は願った。
どうか左の少女が笑顔に包まれて幸せに暮らせますように。
左の少女も願った。
どうか右の少女がいつまでの自分の隣にいてくれますように。
はたして願いは叶ったのだろうか。
ニコニコと笑う二人の笑顔を見て少年は思った。
きっとこの願いは、サンタクロースが叶えるまでもないものだと。
それが思い出せる二つ目の記憶。
原初の赤。
少女の口元から流れ落ちたそれは、青白い唇から白い肌を伝い雪へと落ちた。
まるで絵画の世界のような美しい一瞬。
しかし少年の瞳には、その光景はひどく恐ろしいものとして映った。
人も生物の中の一つにすぎないと改めて感じた。
死はすぐ隣にあるのだと。
こんなにも簡単に人を蝕むのだ。
それが恐ろしくてたまらなかった。
少女は雪の上に膝を折り倒れた。
まるで絵の具のチューブからひねり出したかのような赤。
目にも鮮やかな喀血が白い雪を染めていった。
それが思い出せる三つ目の記憶。
声が聞こえた。
助けて。
お願い、助けて。
倒れこむ右の少女。
その傍で涙を浮かべる左の少女。
助けてほしいと差し伸べられた震える手。
だが、少年は握り返せなかった。
一歩も動けなかった。
一言も言葉が出てこなかった。
何も。何一つ出来なかった。
ただ、こう思った。
そしてそう思ってしまった自分を呪った。
――ああ、サンタクロースは願いを叶えてはいなかったんだ。
そこで記憶は途絶えた。
――12/23*21:13
「寒い。寒すぎる」
内海に隣接する地方都市、神山市。
その中心街である嵩鳥駅の目の前のコンビ二から出た少年は、冷たく吹きつける海風に身震いしながらコートのポケットに手をつっこんだ。
時刻はすでに二十一時を回り、気温もグッと下がっている。手がかじかみ、ケータイを出すのも一苦労だ。こんな事なら手袋を持参しておけばよかったと、少年は舌打ちをした。
ポケットの中で振動するケータイで着信には気が付いていたものの、レジでの清算中ではどうしようもなかった。勿論その場でケータイを取り出す事も可能ではあったが、一般的なマナーを尊重する性格のこの少年は敢えてそうしなかった。
折り返し電話をかけなおすために、先ほどの着信履歴をチェックする。
「なんだ由美かよ」
表示された名前は相馬由美。少年の母親であった。
どうせ大した用ではないだろうと、少年――相馬貴之は再びケータイをポケットにしまいこんだ。
ふっと小さく息を吐き出すと、クリスマス直前のなんとも言えないお祭りの前のような空気を吸い込む。
二学期の終業式が終るやいなや、クラスの男子生徒に連行された大カラオケ大会が終わったのはつい先ほど。コンビニで買い物を済ませた少年は、肩を軽く回しながら曇った夜空の下帰路につこうとしていた。
クリスマスイブを明日に控え、街は普段の数十倍も活気付いている。駅からとめどなく現れる人達にも普段よりも笑顔が多く感じられる。それを見ているだけで少年は少しだけ幸せな気分になれた。
せっかくのクリスマス、楽しまなくては損である。
たとえ高校生活はじめてのイブに何の予定が入っていないとしてもだ。
だから、せめてこうして、街の発する幸せな空気に当てられておくのも悪くないと思っていた。
「クリスマスかぁ」
吐き出す白い息ごしに、道行く人々をぼんやりと眺める。
相馬貴之という少年は、どことなく女性的な雰囲気を持つ中世的な顔立ちをしている。自然で柔らかな表情から彼の人当たりの良さが滲み出ていた。女性ばかりの家庭環境で育ったせいもあるのだろう、彼はこの年齢の男子としては異性に対して少々大人びた性格だ。今、ひとりきりのクリスマスになんの嫉妬心や抵抗感がなく、このように穏やか表情を見せているのが何よりの証拠である。
「さて、帰りますかね」
貴之はモスグリーンのハーフコートのボタンをかけなおしはじめた。
彼の外見は一般的な高校生男子の平均身長。これといって目立った特徴もない。強いていうなら少々痩せ気味というくらいで、人混みにまぎれ込んだら探し出すのは難しいだろう。しかし服装はというとそうでもない。進学校である港北大付属一乃谷高校の制服は、黒のスラックスはともかく赤の詰襟というモダンさが売りである。つまり派手だ。これといってやましいことなどしていなくとも、こんな夜遅くに派手な制服で繁華街を闊歩するのは中々に勇気のいることなのだ。
しっかりと首元までボタンをかけ終えると、先ほどのコンビニで買ったビニール袋から缶コーヒーを取り出す。
「やば、早く飲んじゃわないと」
すでに温かさを失い始めているそれは、家に辿り着く頃にはアイスコーヒーに生まれ変っているだろう。慌てた貴之は、パチリと音を立ててプルタブを開いた。
――12/23*21:29
「あれ? 貴之くんじゃない」
「あ、孝子さん。こんばんは」
「ハイ、こんばんは」
隣に住む雨宮孝子と顔を合わせたのは、自宅に着く直前であった。
年季の入った軽自動車のドアを軽い音を立て閉める。どうやら彼女もまた今帰宅したばかりのようだ。
「お疲れ……ですね」
街灯のあかりのせいではない。青白い肌をしていた孝子の顔には、かなり疲労のあとが見られる。
「ちょっと、しんどいかなあと思うけど。まあ、こんなもんよ」
もともと身体が丈夫ではない孝子が、こんな時間まで仕事をしているのは明らかにオーバーワークだ。
「そんな不安そうな顔しなくても大丈夫。今日は午後からの出勤だったし」
精一杯の笑顔をみせる孝子であったが、来年はいよいよ四十代だ。そろそろ気合だけでなんとかなるという歳ではない事を、その表情から察することができる。
貴之はさらに孝子へと労いの言葉をかけるつもりで口を開こうとしたが、彼女の空元気に敬意を表し、そっと口をつぐんだ。
「あ、貴之くん。シエルの調子はどう?」
自宅の二階、カーテンからもれる光を孝子は見上げた。
この人の頑張りを無駄にしてはいけない。そんな気持ちであの部屋で一人の少女が戦っている。
「頑張ってますよ。ぎりぎりかもしれませんが、僕はいけると思います」
「そう……」
作り笑いではない。もっとナチュラルな笑みを浮かべる孝子。その表情を見ると自分のボキャブラリーの中に、彼女を安心させるような言葉はどうせ見つからないだろうと貴之は思った。
「と、あんまり話しこんじゃうと、それこそ風邪ひいちゃうわね」
「ええ、今日はまた一段と冷え込みますしね。孝子さんもコタツでも入ってのんびりしててください、後で差し入れもっていきますから」
貴之はコンビニ袋を持ち上げてニカッと笑った。
「あら、ありがとう。じゃお言葉に甘えて、ココアでも飲んで待ってるわ」
軽く手をふりながら玄関の扉を開けた孝子に、貴之も同じように軽く手をあげる。
彼女が家の中に消えるのを見送ると、貴之は一度大きく身震いをする。
「あ、これ本当に寒いやつだ。風邪引いてもおかしくないやつだ」
空を見上げると、曇り空からは雪でも降るかのような勢いだ。
「違う、これ降るやつだ」
貴之は小走りで自分の家へと向かう。
玄関の前、もう一度隣の雨宮家の二階へと視線を向ける。
「うーん、さっきはそういったものの心配ではあるんだよなぁ」
その部屋にいるであろう少女を想いながら、ドアノブを回した。
――12/23*21:40
「おがえぢ~……」
リビングのソファーに上に荷物と上着を放り投げ、台所で手を洗っていた貴之の耳に恨みがましい声が聞こえた。
「……何やってんの?」
鼻水をすすりながらやってきたボサボサ頭の母親、相馬由美の様子を見て貴之は怪訝な表情を見せた。
「何って、見てわからないか、アンタは……」
着る毛布を羽織るのはいいが、その状態で家中歩き回るのはどうだろう。貴之は毛布の裾を眺め、あれでは即洗濯機コースだと顔をしかめた。
「風邪……っすか」
「ゴホッゴホッ! 風邪よ」
「いつからだよ」
「夕方に起きたら、もうこうなってた」
「なんか不機嫌だなぁ」
「アンタに薬買ってきてもらおうと思って電話したのに、無視するからでしょ、ごほっ! けほっ!」
「あ、ああ…、それは申し訳ないことを」
くだらない用事だと思い、折り返し電話を入れなかったのが不味かった。と一応は反省してみるが、普段が普段なので無視される由美にも問題はあるのだが。
「ごほっ、ごほっ!」
さすがに病人に追い討ちをかけるほど貴之は無情ではない。
「あー、わかったわかった。今からシエルのところ行くから、孝子さんに頼んで風邪薬もらってきてやるよ」
「そ、その手があった、げほっ! 頼むわ! ごほっ!」
「まぁ、そういうわけだから一時間もしないで戻ってくるから、とりあえず寝てろ」
「わかったわ。病人をほっといて、ごほっ、一時間も雑談してくるという事実は、後から問詰めるから、げほっがは!」
「……どの口が言うのか」
再びズルズルと毛布を引きずりながら寝室へと帰っていく由美を見送りながら、置き薬のストックぐらいは確認しておけよ、などと貴之は思うのだった。
「ふぎゃ!」
毛布を挟んだままドアを閉めようとして転んだのだろう。廊下の向こうから悲鳴が聞こえたが、貴之はそれを無視してコンビニ袋からケーキを取り出す。
「コンビニのケーキでも、一応ケーキはケーキだかんな」
三つあるケーキの一つを冷蔵庫に入れる。由美のぶんである。
「まったく……母親らしいこともたまにはしろよな」
お隣の雨宮孝子と同年代とは思えないほど相馬由美という女性は自由奔放な性格をしている。売れっ子のウェブデザイナーなどという肩書きがなければ、ダメな大人筆頭であろう。いやそんな長所を持ってしてもダメな大人だが。
そもそも母親のくせに自分の事を名前で呼ばせている時点で通常の家庭とは大きくズレているのは間違いない。単身赴任中の父は、そんな型にハマらない由美を気に入ったのだそうだ。本人は至って真面目人間で、その対極にあるパートナーを選んだわけだが、残念ながら女を見る目はなかったとしか言いようがないと貴之は思った。
「そもそも、なんだよ由美って。姉や妹でもそんな風に呼ばないだろう、普通は」
子供の頃からそう呼ばされていたせいか、今更「母さん」などと呼ぶのは不可能だ。自分のズレも含めて、腹立たしい事が満載である。文句を言ってもバチは当たるまい。
「……あった」
ブツブツと文句を垂れながら、台所の隅に置かれたダンボール箱を物色していた貴之はお目当てのものを見つけた。
「しゃーないな」
赤いリンゴを一つ取り出すと、包丁を片手にテーブルに乱暴に腰を下ろす。
由美の体調から察するに、夕食……もとい朝食などは取っていないに違いない。
手馴れた手つきでリンゴの皮を剥きながら、貴之は大きく溜息をついた。
――12/23*22:05
「おっす、頑張ってるかー」
襖を開けると温かい空気が廊下へと流れた。これはまずいと部屋に急いで入ると再び襖をしめる。
学習机に向かう少女は返事をする代わりに軽く左手をあげて挨拶をした。
「ああ、言葉が出ないくらい頑張ってるか」
小柄な身体の上に半纏を着込み、椅子の上であぐらを組み座る。机の隣にはストーブ、そして上に乗せられたヤカンから立ち上る蒸気。
まるで昭和な風景の中、そこに座る少女だけが異彩を放っていた。
少しウェーブのかかった長い髪を、黒いボンボンゴムで二つにわけたツインテール。中学生としてはありきたりな髪型も、その髪の色を見れば大抵の人は驚きの声を上げるだろう。
目にも鮮やかな黄金色。
「そんな頑張ってるシエルに、差し入れもってきた」
貴之は部屋の中央にある小さな丸いテーブルに置くと、少女の机の隣、ストーブの前に腰を下ろした。
「……差し入れとな?」
シエルと呼ばれた少女はシャーペンを動かす手を止めると、隣に座り込んだ貴之へと顔を向けた。
その瞳は透き通ったサファイアブルー。
「ほれ、そこの机の上にケーキ」
「お、おお!?」
シエルはその言葉を聞くや否や椅子から飛び降りるようにテーブルにつくと、コンビニ袋を手に取った。
「おお、モンブラン!」
「あ、コンビニのだけど。栗好きだったよな?」
ご機嫌な表情で、ケーキを取り出す
「そうそう、大好物! よく覚えてたな、タカユキ!」
「うん、あんまりケーキは食ってる覚えがないんだけど確かそうだったかなぁと」
「よし、カフェオレ持ってくる!」
勉強疲れの陰鬱とした表情はどこへやら。シエルは軽い足取りで台所へと駆けていった。
現金なやつめ。貴之はそんな事を考えながら、開けっ放しの襖をそっと閉めた。
雨宮孝子の娘、雨宮シエル織姫。
あまりにもかけ離れた容姿を持つ二人だが、れっきとした血のつながった親子である。フランス人の父親の血を強く継いだシエルは、見た目だけならまるで日本人とは思えない。だが英会話はからっきし。中身も日本人そのものだ。
おまけにそれほど成績も優秀な方ではない。クリスマスを返上してまで受験勉強をしているのもそのせいだ。
貴之は、彼女が座っていた椅子に腰掛けると、机の上に置かれたノートに目を通す。汚い字で書かれたそれは、確かに一年前自分が通った道であり、懐かしさを感じた。
「本当によくまぁ、ここまで頑張ったもんだ」
参考書をペラペラとめくると、付箋がビッシリと貼り付けられている。そのメモ書きなどを見ながら、貴之は微笑んだ。
さっき孝子に、シエルは大丈夫だと見得を切った事はどうやら正しかったようだ。この調子なら本当に受かるかもしれない。
幼馴染であり、妹でもあるハーフの少女とは、すでに十年の付き合いになる。
母子家庭である雨宮家では孝子が仕事で家をあける事が多く、ひとりぼっちのシエルは隣人である相馬家に預けられることが多かった。
そんな事を十年も続けてきたのだ。貴之とシエルは、もはや兄妹のような関係である。それどころか家事全般にだらしない由美にかわり、今やシエルが相馬家のそれのほとんどを仕切っているといってもよい状況なのだ。相馬家にとって彼女はなくてはならない存在と言えよう。
「うわ、閉まってんじゃん! タカユキあけろー!」
「おっと……、悪い今あける!」
貴之は参考書を机におくと急いで襖をあける。そこには小さなお盆の二つのマグカップ。
「あ、僕のぶんも作ってくれたのか」
「当たり前でしょ」
ケーキの隣にカップを並べたテーブルの前に、シエルはちょこんと座る。
「あー、もう、頭がスポンジ状態だったんだよねー」
「なんだそれ」
貴之も再びストーブの前に座り込んだ。
「ちょっと寒がりすぎ」
ケーキの蓋を開けながら、貴之を蔑んだ目で見るシエル。
「いや、うちには石油ストーブないかならさ……いいよなぁ、火のあったかさって」
背中からストーブの温かさを満喫しながら、貴之はマグカップを手に持つ。
「あ、待って」
「?」
シエルは慌てて、自分のマグカップを持つとそれを貴之のそれへと向けた。
「一日早いけど」
「ああ、なるほど」
互いにマグカップをぶつけると、コンッと低い音を奏でた。
「メリークリスマス!」
「メリークリスマス」
――12/23*23:45
風邪を引いても頭痛も吐き気もなく、ただひたすらに咳や悪寒だけの症状が出る場合がある。頭はスッキリしているので、大人しく寝ていることが暇で暇でしょうがないという経験をした人は少なからず世の中にはいるはずだ。
リビングのソファーの上、毛布のミイラになり果てた由美もまさにその一人であった。
「なんでゲームやってんだよ! 布団で寝ろ、布団で!」
「暇だからしょうがないでゲホゲホッ! そもそも、あんた帰って来るの遅いのよ! 一時間!? 一時間って言った、ゴホゴホッ!! 言ったよね!?」
ゲーム機のパッドを高らかに空中に上げそれを振り回し抗議をする由美に、貴之はこめかみを押さえて唸った。
「そう言われてもなぁ……一時間ぐらいはあくまでぐらいであって、一時間ぴったりなわけじゃないし」
「口の、げほっ! 減らない、ガキめ! ごほっ! 親の顔を見たいわ!!」
「なんでそんな綺麗なブーメラン投げてくるんだよ」
「りんごおいしかったわよ!」」
癇癪をおこしたかのように騒ぎ立てる由美を相手に、一日の疲れがどっと出たかのように貴之は肩を落とした。
「シエルの勉強をちょっとみてたんだよ」
「ごほごほっ、ああ、シエルちゃん、早く帰って来て……」
由美は頭まで毛布に包まるとテレビ画面から視線を外さずに、その向こう側にシエルの顔を思い浮かべながら唸った。シエルの様子を気にするよりも、自分の生活を心配する由美に、貴之も開いた口が塞がらない。
「……シエルに頼りっきりすぎんだよ、由美は。ほらこれ、孝子さんから」
ぬるま湯の入った湯飲みと風邪薬をテーブルにおくと、貴之は制服のポケットに手を突っ込んだ。
「ああ、本当に雨宮家様様ね! ごほっ!」
咳き込みながらテーブルに手を伸ばす由美の目の前、貴之は一枚のメモ帳をつきつけた。
「だから、これでも読んでちょっとはヘコめ」
「……んー?」
目を細め、そのメモを注視すると、そこには孝子の綺麗な文字が書かれていた。
「シエルに風邪をうつさないようにしてね……孝子」
メモを読み上げ沈黙する由美に貴之は内心ざまぁみろと思ったのだが、どうやら彼はまだ母の事を侮っていたらしい。
「孝子ったら何言ってんのかしら。私が風邪を、ごほっ、うつすなら、こうやって世話を焼く貴之が最初なのにね」
「……あ、はい」
貴之の完全なる敗北であった。
りんごを食べ終わって空になった器を手に持つと、再びテレビ画面の視線を戻した由美をあとに、ヨタヨタと台所へと引き返す。
「……ああ、最悪のクリスマスになりそうだ」
水をはった桶に器を沈めると、貴之はしばらくそれを見つめていた。
――12/24*00:45
気持ちよく夢の世界に誘われる寸前、枕元に置いたスマートフォンの着信音が貴之の意識を現実へと引き戻す。
誰からの着信かも調べぬまま受信キーを押した貴之の耳に聞きなれた少年の声が届く。
『メリークリスマスだな!』
「……ん? ああ、そうな。うん、そうな」
半分寝ているところに、このテンションはかなりキツイと思いながらも、貴之はモゾモゾと身体を起こした。薄い毛布をかけただけで、エアコンもつけっぱなしであった事に気付くと、急いでリモコンを探す。
「ああ、んでさ、夜遅く悪いんだけどさ、明日暇か?」
「本当に遅いよな。寝てたわ」
「ああ、そうだろうなぁと思った」
ベッドの淵に転がっていたリモコンを見つけると、おやすみモードへと切り替える。
「思ってたらなら朝電話しろよ」
「俺、朝遅いからなぁ……」
この時間にこんなに元気よく電話をかけてくるのだ。どうせ就寝まであと三時間はあるに違いない。
「つまり明日の午後からの予定ってわけだな」
「そうそう、多分朝までゲームやってると思うから、起きるの昼過ぎだわ」
「和泉……、もうちょっと有意義な冬休みの一日目を迎える気はないのか」
親友であり、幼馴染でもある結城和泉。そのあまりに自堕落な予定に、貴之は先ほどの由美との会話の時同様、頭を抱えた。
「いやな? ほら、だからせめて昼からみんなでカラオケどうかなって話で。丘村がさっき連絡よこしてきやがったもんだからさ」
「はぁ!? カラオケ!?」
つい数時間前までカラオケボックスで精根尽きるまで熱唱していた同級生と同じ名が出てきたことで、貴之は思考を停止した。
「今年はシエルの受験で、いつもみたいに四人で遊ぶとかできないだろう? だからどうかなぁと思ってよ」
「ああ、円も家族と明日から旅行だって言ってたな」
話をしながら部屋を消灯すると、貴之はモソモソと布団に潜りなおす。
「たまには野郎ばっかで騒ごうぜ」
「……まぁ、それは別にいいんだが、遅いんだよ連絡が」
「よし、んじゃ駅前のゲーセンわかるよな。あそこで三時ぐらいってことで」
「聞けよ! 僕の話も聞けよ!」
「んじゃまた明日な!」
一方的に通話を切られた貴之は憤慨しながら再び起き上がり、通話記録が画面に出されたスマートフォンを呆然と見つめる。
「……頼むよ、本当にもう」
完全に眠気が飛んでしまった貴之は、ベッドから降りるとカーテンを開ける。窓から隣の雨宮家を覗くと、シエルの部屋はまだ明かりが灯されていた。
「頑張れよ」
貴之は、幼馴染であり妹のような少女に小さなエールを送った。
もしもサンタクロースが彼女にプレゼントを届けてくれるなら、彼女がこれからも幸せな生活を送れるような未来を与えて欲しいと願わずにいられなかった。
その願いは、いつか誰かが願ったこと。
貴之はその願いを受け取っただけだ。
だが、願いはどうやって自分に託されたのだろうか。
それは長い年月をかけ、失ってしまった貴之の約束だった。
――interlude.A
「サンタクロースはいるよ!」
雪の降り積もった真っ白な世界。
少女は泣きじゃくる少年の手を優しく握り返した。
「これからもあの子を……」
ごめんなさい。
ごめんなさい。
ごめんなさい。
サンタクロースなんて居なかったんだ。
少年はサンタクロースを信じない。
だから少年は――
―― Next #02