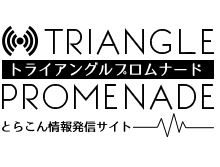『Zero The White Christmas』#02*相馬貴之編
#02/December.24 Part.1
――12/24/*06:41
ゆっくりと目を開く。
静かな、とても静かな朝だった。
枕元に置かれた目覚まし時計がカチカチと時を刻む。普段ならけたたましく鳴り響くのが仕事のそれも、今日からは二週間ほど休業である。
布団から出た貴之の肌に、冷たい空気が容赦なく突き刺さった。身震いをしながら慌ててジャージの上にパーカーを羽織ると、チャックを首元までしっかりあげる。
おぼつかない足取りで部屋から出ると、廊下は部屋の比ではない程冷え切っていた。
「寒いっ!」
呟きと呼ぶには少し大きな声を出すと、貴之は小走りで階段を降りリビングへと向かう。
ソファーには母親の姿はなかった。さすがに布団で寝てくれたようだった。少しだけほっとしながら、コーヒーを入れるために小さなヤカンに水をいれ火にかけた。
薄暗い中ガスコンロの青い炎を確認すると、再びリビングに戻りカーテンを勢いよく開いた。
「ああ、積もったのか」
白い粉雪が舞っていた。
昨晩、雪が降りそうだと言っていたのはドンピシャだったらしい。見慣れた町並みは一晩で銀世界へと姿を変えていた。
しばらくその光景に見蕩れていたが、お湯が沸騰したことを告げるヤカンの大きな音が貴之を現実へと引き戻す。急いで台所に戻ろうとするが、何故か足がもたつく。
「……なんか、フラフラするな」
コンロのスイッチを切ると、貴之は自らの額に手をあてる。
「あれ、これ……ちょっと熱っぽいのか?」
千鳥足である理由はこれかもしれない。
「まぁ、もっかい寝れば大丈夫だろう」
コーヒーを淹れ終わった貴之は自室へと戻ろうとしたが、リビングからみえる雪景色に再び足を止めた。
「九年か」
あの時も雪が降っていた。
雪が降る季節に貴之は少女達に出会った。
そして雪の降る日に少女と別れた。
先ほどの夢を思い出し、貴之は唇を軽く噛んだ。
もはや断片になってしまった古い記憶。それでも後悔の念だけははっきりと残っている。そこには今の貴之をカタチ作るものが確かにあった。
しばらく物思いにふけっていた貴之だったが、その記憶を思い出そうとする前にそっとその場を立ち去った。
――12/24/*15:11
「あー……」
ゲームセンターの片隅、ベンチに腰掛ける貴之は呻き声と共に項垂れる。
確かに寝起きの貴之は体調が悪かった。が、孝子から貰った風邪薬を飲み二度寝をしたおかげか、自宅を出る前にはすっかり元気になっていた。そう、なっていたはずだった。しかしそれはあまりに楽観的な考えであったようだ。集合場所に到着したころには貴之の身体はすっかり冷え切って、体調は今朝の比ではないほど悪化していた。
「まいったなぁ。さっきまではなんともなかったのに……」
お気に入りの缶コーヒーを自販機で買ったものの、微妙な吐き気で飲むことも叶わない。
こんな事なら炭酸飲料にしておけば、少しは胃もスッキリしたかもしれないなと考えながら、壁にかかった古臭いアナログ時計を見る。
「遅いな。ここだと見つけにくいのかな……」
駅前のゲームセンターはアミューズメントパークと呼んだ方が適切なほどに規模が大きい。貴之はその一番奥まった場所にある休憩所にいた。ひょっとすると和泉達は店の入り口辺りで合流済みなのかもしれない。
「動くのが辛い」
立ちあがる気力が湧かない貴之はコートのポケットに手をつっこんだ。電話で連絡をとり、誰かしらここまで迎えに来て貰おうという算段だ。
「あれ……」
普段スマートフォンを入れているコートの右ポケット。そこには何も入っていなかった。慌てて他のポケットも探してみるのだが、見つかったのは財布のみ。
「うぁ……まいったな」
どうやら自宅に忘れてきてしまったようだ。
普段の貴之なら外出時の持ち物チェックは忘れることなどありえない。他人の面倒まで見るほどの徹底振りだ。それがこうも間の抜けた行動をとってしまったのは、やはり出かける前から体調が悪かったのである。大丈夫などと思っていた事自体、すでに大丈夫ではなかったということだ。
「……仕方ない、歩いて探すか」
幸い立てないほど酷い体調なわけではない。
本来スマートフォンが収まるポケットに、冷めかけの缶コーヒーを仕舞うと貴之は立ち上がった。
多少フラフラするが、ここに到着した時ほどではない。これならばカラオケボックスの中でしばらく休んでいれば回復するだろう。いつもなら最悪の事態を想定して動く慎重な貴之が、そんなポジティブな考えで行動している時点で、やはりいつもの彼ではないのだが、それこそ本人にはわかりようもないことだった。
なんとかなるさ。貴之はマフラーに顔を埋めると重い足取りで歩き出した。
それにしても、なんとも冴えないクリスマスイブである。これならば受験勉強をしているシエルのほうがよほど有意義なイブだろう。
「クリスマス返上で勉強か。……懐かしいな」
去年のクリスマス会と称した勉強会。
貴之、和泉、円の受験生トリオはファミレスの片隅で必死に勉強をしていた。
唯一受験生ではないシエルも退屈そうにその輪に加わっていたが、そんなシエルに、和泉が随分と嫌味を言っていた覚えがある。
来年はお前が苦労する番だとかなんとか。
その頃のシエルは進学校である一乃谷高校を目指す気などさらさらなかった。それどころか高校に進学することさえ無関心であったのだ。
母子家庭である雨宮家。その大黒柱ともいうべき孝子はあまり身体が強くない。現在の仕事は若い頃のツテを頼りにしているようだが、あまり人に収入の話はしたくない様子だ。
極端な貧乏……というほどではないが、とても裕福とは言い難い家庭事情。
母を助けたいという気持ちを、シエルが子供の頃から持ち続けているのは不思議ではない。
一刻も早く仕事に就きたい、早く大人になりたい。シエルは中学生時代ずっとそんな事を言っていた。
だが、幼馴染である貴之達の高校生活は、シエルにとってもやはり羨ましいものだろうことは想像に難くない。
高校に進学しないということになれば、長年つるんできた貴之達四人との輪から外れてしまうことになってしまうかもしれない。
できるならば、そんな娘を何とか進学させてやりたい。幼馴染たちと一緒の子供時代をもう少し味あわせてあげたい。そう思うのが親心というものだろう。もちろん孝子も心からそう思っていた。
しかしシエルに高校受験をするように言ったところで、彼女がそう簡単に首を縦に振るとは思えない。
そこで孝子は一計を案じた。
「もし、シエルが勉強を頑張ってくれるなら、それがお母さんにとっては一番の贈りものなんだけどな。お母さんはあなたが一乃谷高校に通ってくれたらいいなと思っているの」
一刻も早く母を助けたいというシエルの気持ちを知っていながら、孝子は高校に進学しろと言う。ましてや私立校である一乃谷に通うことになれば、今まで以上に孝子に負担がかかるのは火を見るよりも明らかだ。さらに成績があまりよろしくなかったシエルにとって、孝子の提示した条件はとてつもなくハードルの高いものだ。
だがそれでも孝子はシエルに貴之たちと同じ一乃谷高校に通って欲しいと言う。これが何を意味するかはシエルにもよく理解することができた。
母の想いに応えるためにはどうするべきなのか。答えははっきりしていた。
この茨の道を乗り越えて高校生活を送ることこそが、最高の親孝行なのだ。
シエルは覚悟を決めた。
そして今に至る。
実際、ここ半年でシエルは驚くべき成長を遂げていた。
何年間も妹のように付き合ってきた隣に住む少女。
その少女とこれからまた二年間共に学園生活が送れるかもしれないことに、貴之もまた少しばかり心を躍らせていた。
「がんばれよ」
シエルに向けた昨晩と同じエールを、貴之は小声で呟いた。
――12/24*15:45
「誰もいねーじゃねぇか!!!」
ゲームセンターをさまようこと三十分。一向に誰も姿を見せない現状に、いよいよ貴之の怒りも爆発寸前である。
今度は、入り口近くにある誰も遊んでいない大型のゲーム機の椅子に腰掛ける。
電話やメールさえ出来れば。今更ながらスマートフォンを忘れてきた事は貴之にとっては痛恨の極みであった。
「くそ……もう帰っちまうか」
三十分もあれば、自宅まで戻れていたことにまた頭を抱える。
普段の自分とはあまりにもかけ離れた間抜けっぷりに、貴之の苛立ちは頂点に達しようとしていた。
「落ち着け、落ち着け」
自分をたしなめる為に、大きく深呼吸をする。
ここまで探して和泉達に出会えないというのは明らかにおかしい。
今日集まるメンバーがどれほどの数かは分からないが、同級生全員が一斉に遅刻するとは考え難い。
「ようするに集合時間が間違っている……が一番適切な答えだよな」
少し考えればすぐに解決する事だった。
その発想を得ないまま無駄に歩き続け、体力を消耗してしまった事に再び項垂れる。
「和泉ぃ……」
友人に対する呪いの言葉を発するが、スマートフォンを忘れてしまった事でこの泥沼の状況に陥っているのは自業自得とも言える。
「ああ、本当にもう、さっさと帰っておけば……」
ゲームセンターの喧騒が貴之の疲労を一気に加速させた。
「~~♪」
いい加減考えることそのものが面倒になりつつあった時、隣のゲーム機にクレジットを投入される音が響いた。
貴之の座る大型筐体はいわゆるリズムゲームだ。音楽に合わせて画面に表示されるアイコンをボタンで操作して、擬似的に楽器を弾いているような感覚にしてくれるというもので、もう十年以上ものロングヒットになっているものである。
だが、長く続きすぎたシリーズの宿命か、最前線でプレイするゲーマー達に設定された難易度は、初心者などお断りの空気をかもし出していた。よって入り口近くに設置されているにも関わらず、プレイする客が少ないため、こうして貴之はプレイすることもなく座り続けていられるのだが。
隣の筐体は、貴之が座る筐体よりも遥かに難易度の高いリズムゲーム。それをプレイしようというのだから、きっと歴戦の勇者に違いない。
貴之は項垂れたまま、隣に現れたスゴ腕プレイヤーの演奏に耳を済ませることにした。そんなささやかなイベントでさえ、荒みきっていた貴之には一服の清涼剤であると言えたのだ。
「……え!?」
ガシャンッと、ゲーム画面がクローズする音が聞こえた。
「え!? え!? これで終わりなんですか!?」
あっという間にゲームオーバーになった隣の客は女性のようだった。どうやらどんなゲームかさえ理解しないまま、コインを投下してしまったらしい。
「えーと、えーと……。え、本当に終ってる! これで百円取られちゃったの!?」
必死でボタンを叩きゲーム機に訴えかける女性の声に、貴之は驚き顔をあげた。
はたしてそこに佇んでいたのは、彼がよく知った顔であった。
「シエル……? 何やってんだこんなところで」
が、そこで貴之は絶句する。
街並みに溶け込んでしまうかのような真っ白なコート。
艶やかに輝く金色の髪。
まるで精巧に作られた人形のように整った顔。
全てが淡い色彩を持つ世界で、深く吸い込まれそうな蒼い瞳。
記憶が切り取られ、この場で再現されたかのような。
紛うことなきあの時の少女の一人が、時を経てそこに立っていた。
「え? ……ええええっ!?」
彼女は貴之の顔を見ると、大きな目をさらに大きく見開く。
「な、なんでタカユキさんが、ここに!?」
「は?」
いきなり、さん付けで呼ばれたことに貴之は間の抜けた声を出す。
「いやいや、何言ってんだよ! 受験勉強どうしたんだ!?」
「は、はい!?」
「はいじゃないだろ。何ちゃっかりイブにゲーセンきてんだよ!」
半分放心状態の彼女は、何かを言おうと口をパクパクとするのだが、言葉がでてこないらしい。
「くそ、丁度いい。僕も今から家に帰るところだ。さっさと帰って勉強するぞ」
貴之は立ち上がると彼女の手を取る。
ボンッというまるで漫画のような効果音を発したかのように彼女が硬直する。
「あ、あわわ、え? え? あ、あの……なぜ?」
「何故って……」
シエルの様子がおかしいような気もするし、そうでないような気もする。今の貴之の体調でははっきりと判断がつかない。
それでも何か、何か違和感があるのは間違いがない。
「……シエルだよな?」
いつものツインテールではない。
前髪をヘアピンで留めただけで、腰まである長い髪はそのまま下ろされている。
「え、えと……は、はい。シエルです……よ?」
ぎこちない笑顔。だが嬉しそうな笑顔。それでいて泣きそうな笑顔。
その表情に貴之はひどく懐かしさ感じていた。
――12/24*16:30
「ああ、なんで僕はこんなところに居るんだ……」
「少し休んだ方がいいからと先ほど結論も出たでしょう?」
「いいや、僕は承諾してないぞ。帰るって言った」
「何を言ってるんですか、そんな熱で!」
ゲームセンターで周囲の客が少し引くほどの口論をした貴之と彼女。
結果的に最後の力を使い果たした貴之が、その場でへたってしまったということだ。
執拗に彼女に叱られながら、近場のカラオケボックスに入ったのはつい先ほど。当初の予定とは随分違ってしまったものの、落ち着ける場所に辿り着いた事は確かである。
「ああ、和泉達には明日連絡入れておかないとなぁ……でも元々はあいつのせいだよなぁ……」
貴之はカラオケボックス内のソファーにぐったり倒れこむ。L字ソファーの斜め前に座った彼女は、コートと同じく真っ白なハンドバックの中を探っている。
その様子を薄目で見守りながら、貴之は不思議な感覚に囚われていた。
確かにそこに居るのはシエル本人。にもかかわらず貴之は無性に懐かしさを感じてしまう。
熱で朦朧としているせいなのだろうか。
今日に限ってあんな夢を見てしまったせいなのだろうか。
下ろされた長い金色の髪が貴之の中の記憶を呼び覚ます。
「なぁ、シエル」
「は、はい? なんですか?」
今日のシエルは何故敬語なのだろう。
ここに居るはずのない少女。その姿を真似るシエル。
街を覆った雪の中、まるで別世界へと誘われたような感覚。
貴之は寝転がったままその顔を彼女へと向ける。
ひょっとするとこれはシエルの仕掛けたサプライズなのだろうか。いったいどんな意図があるのか。
色々と思考を巡らせてみるが、貴之にはまったく見当もつかない。
となれば、この幻想を打ち破る為に何らかの方法でシエルをこちらの世界へと引き戻し、その企みを暴くだけだ。
「……えと、どうしたんですか?」
彼女は訝しげな表情で貴之を見ていた。
自分から話しかけたもののかなりの長考をしていたらしい。普段ならものの数秒でまとまる思考でさえ、今の貴之のパフォーマンスではままならぬ状態であった。
「あ、うん……そう、だな。首がその、痛いので枕が欲しいかなぁって」
とっさに思いついた事を口にしてみる。
「枕ですか……。このコートとかどうでしょう」
白いコートを脱ぎ始める彼女に、貴之はほくそ笑む。ここで何かシエルを怒らせるような事を言えば、この夢の世界からは抜け出せるはずだと確信していたのだ。
「いや、膝枕がいいなぁ」
「ふえ……っ!?」
彼女はコートを丸めたまま硬直する。
主導権を握られっぱなしのシエルに対して、貴之は殴られる事を覚悟しながらも一矢報いた気持ちになっていた。
「なーんって……な、ってちょっとオイ!」
貴之の頭を持ち上げると、彼の上半身のあった場所に彼女は乱暴に腰を下ろす。
「……い、いつもやってますもの、ね!?」
普段のシエルはまず着ることのない紺色のフレアスカートは、ジーンズなどとは違い彼女の柔らかな感触をダイレクトに貴之の後頭部へと伝えた。
「え、あの、シ、シエルさん?」
――いつも僕が膝枕をされているだって?
なんだそれ、一体どこの世界線ですか?
ひょっとしてこれがクリスマスプレゼントとか、そんな感じ?
幼馴染で妹のように育ってきたシエルが膝枕をしてくれているだと?
あれ、これってなんか滅茶苦茶幸せじゃないか?
いやいや、そうではないだろう!
そうでない!
違う、断じて否だ!
貴之は恐る恐る彼女の顔を覗きこむ。
「……こんな事させてるなんて」
「え、させてって、いや、してもらった記憶などございませんが」
頬を膨らませていた彼女は、貴之の言葉で再び真っ赤になった。
「え!? ……わ、わかってます。きょ、今日だけですからね!」
目を合わせているのが恥ずかしくなったのか、彼女は貴之の視線を隠すようにその額にそっと手を乗せた。
暖房の効いた部屋で、ひんやりとした手のひらの感触が心地いい。
「コホン! と、とりあえず、先ほど私が渡した解熱剤が効いてくるまでにちょっと時間があります。大人しく寝ていてください」
「あ、ああ」
何故シエルが解熱剤を持ち歩いていたのかはよくわからなかったが、貴之にとってはありがたいことだった。このまましばらく休めば家に帰るまで持ちそうである。
「タクシー、拾えばよかったんだけどな」
「……勿体無いじゃないですか」
そういう所でケチるところがいかにもシエルの発想だなと貴之は微笑む。
「な、なんで笑うんですか」
「いや、別に……。それじゃちょっと静かににしてるから。……なんだその、疲れたらすぐに止めてもいいんだからな、ひ、膝枕」
「あ、はい。気にしないで下さい。というか、そこで恥ずかしがらないで下さいよ」
手のひらで視線を遮られているので彼女の表情は見えないのだが、きっと自分と同様にばつの悪い顔をしているのだろう。
その顔が見られない事が残念だと思いながらも、貴之の意識は次第に遠のいていった。
――interlude.B
少女は少年の前から姿を消した。
残されたもう一人の少女は貴之の背中へとしがみついた。
サンタクロースは願いを叶えてくれなかったのだ。
だが、まだ終っていない。
これ以上彼女達の世界を壊してはいけない。
消えた少女の願いはもはや叶えられることはない。
だからせめて――
少年は背中の少女を引き剥がした。
「君は一人じゃない。だからそんな怖がらないで」
背中に隠して守るのではない。
彼女の背中を押してあげようと思った。
幸せな世界を見せてあげようと思った。
サンタクロースはいない。
願いなんか叶わない。
少女は自分の力で幸せを見つけなければならない。
少年は残された少女の背中を守ろうと思った。
彼女がずっと前を見て歩けるようにと。
それが思い出した四つ目の記憶。
―― Next #03