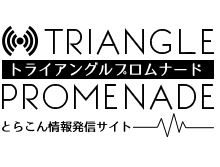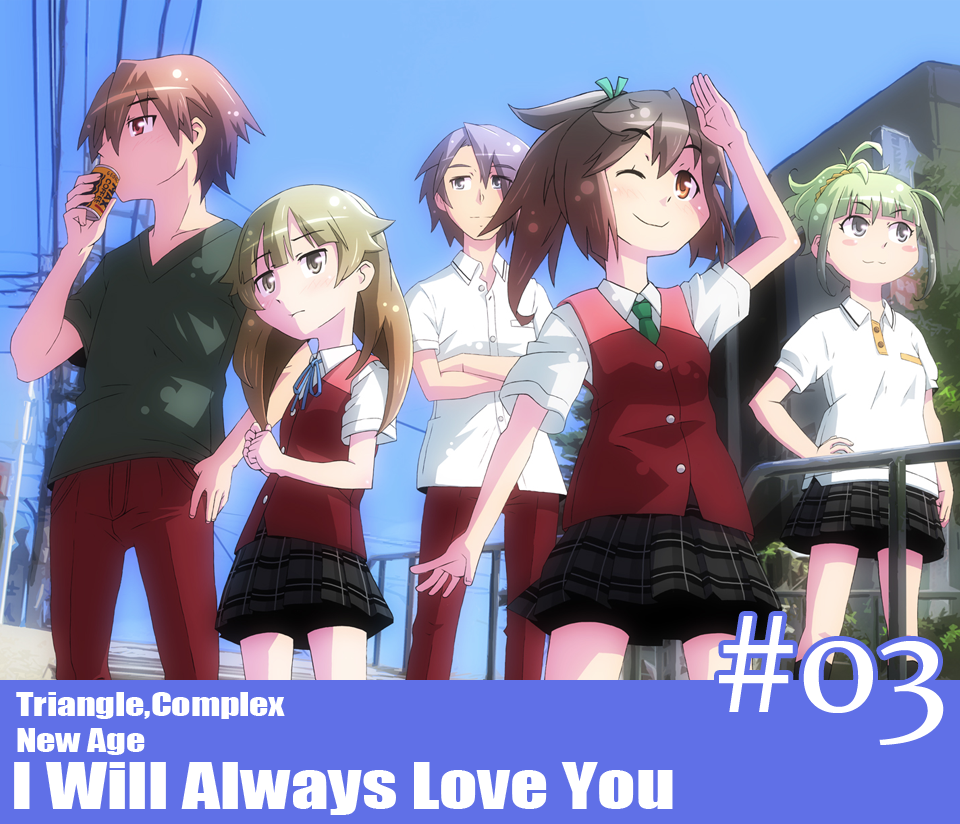『I WILL ALWAYS LOVE YOU.』 #03 *三咲凪編
#03/葉風 :hakaze
柚が待ち合わせ場所に着いた頃には、夕焼け空から落ちた鮮やかなオレンジの光がベンチに座る凪の顔を照らしていた。
「ごめんね、急に呼び出しちゃって」
「いえいえいえいえ! いつでも呼び出しちゃってください!」
暇を持て余し駅前商店街に足を運んでいた柚だったが、凪が嵩鳥駅公園を待ち合わせ場所に指定したことで、結果的に彼女の行動は功を奏することとなった。
「うわぁ、私服の三咲先輩ってそういう服装なんですね~! すごく似合ってます!」
「うん? ああ、そっかプライベートで会うのって初めてだよね」
凪は一度学校から帰った後、こうしてここまで歩いてきたのだろう。
その姿は一乃谷の制服ではなく蒼色のワンピースであった。ロイヤルブルーというのだろうか。深く落ち着いた気品ある色は中世のお姫様のよう。そして足元の赤いリボンのついた茶色の革靴は、そんなファンタジーな世界を連想させた。
柚には、凪の佇まいが一般的な女性とは何か違うものとして感じられる。
視覚だけではなく、彼女の存在そのものが魂に直接響くと言えばいいのだろうか。きっとその服装さえも、彼女の心を具現化したものにちがいない。
しかし、凪はドラマの中の存在でもなければ、小説のような夢物語の登場人物でもない。凪の足はしっかりと地を踏みしめている。こうして手を伸ばせば確かに触れる事ができる現実であると感じられる。
これは柚にとって、とてもうれしいことだった。
「ありがとうね、柚ちゃん」
凪は立ち上がると柚へと深々と頭を下げる。
「ちょ、ちょっとなんで頭を下げるんです!? 」
先ほどの電話で、凪は用件については何も触れなかった。ただ会えないかと言っただけである。にも関わらずテスト期間の真っ只中、わざわざこうして足を運んでくれた後輩に凪は喜びを隠せなかったのだろう。
彼女の喜びの表現、それは素直に相手を敬うこと。だから先輩だとか後輩だとか関係ない。今は、柚に対して礼を尽くすことが、彼女にとって何にも変えられない絶対事項であり、彼女自身の心を満たす行為もであった。
わかっている。これが三咲凪という人なのだ、と柚にはわかっている。
しかしそれがたとえ感謝の気持ちからくるものだとしても、年上で、しかも憧れの存在の人から頭を下げられるのはなんとも居心地が悪いのも確かであった。
「あ、ごめんね、つい」
時折柚は、凪本人も彼女自身をあまり制御できていないのかもしれないと感じることがある。今こうして柚に頭を下げたことも、凪は後で悔やむのかもしれない。こんなにもスゴイ人なのに、どうしてこうまでこの人は繊細でお人好しなのだろうか。いや、だからこそこの人はスゴイのかもしれない。
色んな考えが柚の脳内で繰り広げられ、そしていつもの答えへとたどり着く。
そんなところまで含めて、自分は三咲凪という人物に惹かれているのだと。
珠希の言うとおり、自分には同性愛の傾向があるのかもしれない。が、そんなことは取るに足らないもので、魂をゆさぶる存在を認める感覚こそ大事にするべきなのだと思い直す柚であった。
「とりあえず座ろっか」
凪は再びベンチへ腰を下ろすと、柚に隣に座るよう促した。
哀愁を帯びた笑顔に柚の心音は大きく跳ね上がる。
その表情。全てが尊敬してやまない三咲凪という女性の中でも、最も愛すべきはその表情なのだと柚は思う。
まるで、世界は楽しいことで満ち満ちているんだよ、と柚へと手を差し伸べているような笑顔。世界への興味をなくしていた柚の尖った心は、凪のその表情で救われる。
「は、はい! 木住野柚、お隣に座らせて頂きます!」
ベンチに並んで座った二人は、しばらくは会話することもなく空を眺めていた。
別に話を始めるタイミングを逃したわけではない。
ただ二人で空を眺める時間が心地よかったからだ。
日の暮れた公園に人影は少なく、余計なノイズが入ることはほとんどない。遠くで聞こえる電車の通過する音でさえ、森の中で耳にする小鳥のさえずりのように感じられる。
この時、凪がこの時間をとても大事にしているという感覚が何故か柚にも伝わって来た。
そして、おそらく日が沈むまで彼女は何も話し出さないだろうと思った。
気が付くと、永遠であったかのような時間はあっという間にその役目を終え、すでに夕日はビルの隙間へと隠れてしまっていた。
空は太陽の残照が雲を赤くしながらも、蒼く深い闇がそれを飲み込んで行く最中だった。
昼と夜の境界を空は描く。それはとても美しい光景だった。
「この空の色……ね、私大嫌いなの」
「え!?」
予想外の展開。
凪の言葉に柚は驚きの声をあげた。穏やかだったこの空気がその言葉に繋がるとは思えなかったのだから仕方がない。
動揺する柚とは対照的に、凪は夜空に光り出した星の輝きに目を細める。
「そ、そうなんですか?」
下手な愛想笑いを浮かべそう聞きなおした柚に、凪は無言でうなずいた。
こんなにも優しい顔をしてどうしてそんな事を口にできるのだろう。
嫌いなものを穏やかに嫌いなのだと何故言えるのだろう。
柚には理解できない。
嫌いなものは嫌いだ。
そんなものが視界に入ったら不機嫌になるのが人間ではないのだろうか?
今まで凪の事を肯定的に受け止めてきた柚だったが、さすがに理解の及ばないものにはどう対処していいのかわからない。
「でも、先輩楽しそうに、見てるんですけど……気のせいです?」
「ふふ」
狼狽しておっかなびっくり話す柚に凪は笑った。
「びっくりした?」
「え!? あ、はい、……え?」
凪にしては珍しい悪戯っぽい顔つき。
「あ、あれ?」
クスクスと笑う凪に、柚はようやくからかわれたのだと理解した。
「も、もう! 三咲先輩!」
頬を膨らます柚に、凪はごめんごめんと謝る。
「まさか、そんなに驚くとは思ってなくて」
「だ、だって三咲先輩が冗談ってあんまり言わないし」
柚はからかわれるのが苦手だ。当然からかうのも得意ではない。
いつだって真面目に物事に向かい合う彼女にとって、からかうという行為は、そこに隠されたものが善だとしても中々に容認はできない。
先ほどの咲奈の顔つきがチラつき、柚は少しばかり不機嫌になる。
が、何故だろうか。不思議なものでイラつきは咲奈へと向けられているだけで、目の前の凪へとは向く事はなかったのだ。彼女もまた咲奈と同じように、自分のことをからかった人だというのに。
だがしかし、ごめんねと優しく微笑む凪の顔を見て柚はすぐさま直感した。
――ああ、今のは嘘ではないんだ。
その後の二人の会話は本当に他愛のないものだった。
最近の部活の調子はどうだという二人の共通の話題から、テスト勉強の捗り具合、そして好きな食べ物は何か等々。
しかし、柚が凪とこんな風に話を交わしたのは今日が初めてだった。こうして隣に座って自分の話を聞き、笑ったり、考え込んだり、困ったりする凪など想像したことすらなかった。
この距離感はなんとも心地よい。学校外で自分に連絡をくれたことだってそうだ。多くの後輩の中から、自分を選んでくれたことも柚にとっては最高に名誉な事であった。
街灯の明かりが、二人の座るベンチを照らす。まるで舞台の一幕のように。
そんな幸せな時間だからこそ、柚は笑顔の下でザワつく心を抑えられなかった。
三咲先輩は何故あんなことを言ったのだろうか?
先ほどの凪は夕焼けを飲み込んでいく空の深く蒼い色が大嫌いだと言った。
にも関わらず今日の凪はそれと同じ色のワンピースを身に纏っている。わざわざ嫌いな色を自分に合わせるのは何故だろうか。
一乃谷高校の制服が赤いジャケットであることもそうなのだが、柚にとって凪のイメージカラーは赤以外考えられない。なにより凪のイメージはプリンセスローズそのものなのだ。
凪の私服姿を見られた事は確かに嬉しいが、蒼い色の服を着ていた彼女は柚のイメージからは若干ズレていた。だからこそ柚は不思議に思う。
柚は蒼い服を身に纏った凪こそが、本当の三咲凪だと感じてしまったのだ。
先ほどの彼女の発言と、その自分自身の直感が柚の心のザワつきの正体。それは段々と嫌な予感へと成長していった。
「ふぅ……」
会話が途切れると、凪は大きく深呼吸をして再び夜空を見上げた。
柚はそんな彼女の横顔をしっかり見つめ、身構えた。
来る、そう感じ取ったのだ。
「あのね柚ちゃん。今日呼んだのはね、ちょっと相談があったからなの」
「はい」
力強く返事をする。
柚は嫌な予感を振り払おうとしなかった。
例え凪の身に何が起きていたとしても、自分が彼女のために頑張ればそれでいいのだ。彼女の不幸を一緒に背負うことはない。彼女の不幸を取り除くことが自分の使命のはずだ。
柚の直感はそう告げていた。
それがどんな相談なのかはどうでもよかった。
ただ憧れの先輩に頼られたということが、柚にとってはとてつもなく喜ばしいことだった。
だから、どんな相談にも――
「私ね、プリンセスローズを柚ちゃんにやってもらいたいの」
どんな相談にも……?
「…………?」
どんな相談にも??
柚の頭の中がクエスチョンマークで埋め尽くされていく。
彼女に起こり得る不幸???
「…………………はい?」
間抜けにも柚の声は引っくり返ってしまっていた。
「柚ちゃんは私の知る限り、一番プリンセスローズを好きでいてくれる子だから」
「……え? え? どういう、え? ちょ、ちょっと待ってください……」
どんな相談でも構わない、というには語弊があった。
どうやら、他人に対する覚悟と、自分に対する覚悟とはまるで質が違うらしい。柚はそう実感した。
勿論実感はしたものの、それを理解するまでは到達していない。よって柚は聞きなおす事で精一杯。まともな言葉が口からこぼれることはない。
「私はプリンセスローズに向いてないから……」
深淵を覗かせているかのような蒼い夜空。
その空に輝く淡い光を凪は見つめていた。
星。
プリンセスローズは凪にとって星そのものだ。
だから――
「柚ちゃん。学祭の舞台、あなたに主役を演じてほしいの」
「あ…………」
――頭がクラクラとする。ああ、これが眩暈というやつなのか。
まるで他人事のように歪んでいく視界を、柚は冷静に分析をし始めた。
自分はいつだって冷静沈着、世界を客観視する存在だ。だからこんな状況でも自分は大丈夫なのだ。
そう考えながらも、柚は目の前の世界がどうしようもなく壊れて行くことに歯止めがかけられない。
ふと、柚は彼女の瞳を真っ直ぐ見据える凪の視線に気付いた。
これは夢であってほしいと、安直な逃げ道を探す自分を見下ろすかのような視線。
三咲凪という女性を深く想っていれば、その瞳の見据えるものが舞台でローズを演じる柚の姿なのだと否が応にもわかってしまう。
わかってしまったのだ。
そして、これは現実なんだと、柚の心は認めてしまった。
認めてしまったのだ。
柚の瞳にはみるみる涙が滲んで行く。
「ど……どうして! どうしてそんな事言うんですか!?」
悲痛な叫びは自身の口から。
喉から、身体から、心から。
柚は自分らしからぬ自分に驚きを隠せない。
「柚ちゃん……」
凪がこんなことを言うのにはきっと深い意味があるはずだ。
彼女の瞳の奥にたたえられている悲しみがそれを物語っている。
凪がなんの考えもなくプリンセスローズを放棄するわけがない。
だからちゃんと最後まで彼女の話を聞くべきだ。
そう思いながらもとうとう柚の瞳からは大粒の涙が零れ落ちた。
柚は止まらない。
「三咲先輩以外に……」
その言葉は止まるわけがない。
「プリンセスローズができるわけないじゃないですか!!!」
憧れ、追いかけ続けたいと思う人は――
一番大切なものに背を向けようとしているのだから。
その後、柚はどうやって家に帰ったのか覚えていない。
気がつくと誰もいない居間のソファーで彼女は眠っていたようだ。
寝ぼけた顔で時計を見ると、針はもうすぐ二十三時を差そうとしている。
「……寝ちゃってたのか」
こんな時間に一人娘が居間の電気もつけっぱなしで寝ていたというのに、母親は一体何をやっているのだと勝手なことを考えたが――
「あ、あちゃー」
目の前のテーブルにラップをかけて置かれた夕食を見れば大体の察しはついた。これは明日母親に怒られることを覚悟するべきだろうと、柚はため息をつきながら目をこする。すると目元がパリパリと音を立てた。おそらく塩分がこびりついてるのだろう。
「……久しぶりに泣いちゃったな」
ポソリと呟く。
だらりと足を投げ出しソファーに座りなおすと、柚はゆっくりと目を閉じる。
前に泣いたのはいつだっただろう。
記憶の糸を手繰り寄せると、小学生の頃サッカーで負けた男子の事を思い出した。
――そうか、私は悔しいと泣くんだ。
何を当たり前の事をと思いながらも、その事実からは逃れられない。
その同級生の男子は確かにサッカーが上手かった。
だが、彼の上手さに嫉妬したわけではない。ましてや男女の身体的な能力差なども柚は感じなかった。
ただ、本当にその男子の上手さに感服したのだ。
尊敬といってもいい。
コイツはすごいヤツだと天才である自分が認めたのだ。
きっといつか彼はプロになるだろう。ひょっとするとオリンピック選手になるかもしれない。幼い頃とはいえ、そんな人間と戦えたのだ。後悔も何もない。むしろ戦いあった自分を誇らしい。そう柚には思えた。
だがその男子はケガでサッカーの選手生命を断たれた。
本当に些細な事故。階段を踏み外し彼はたったの五段を転げ落ちた。それで頭の打ち所がちょっと悪かっただけ。たったそれだけのことで彼の選手生命は終わったのだ。
日本を代表する選手になるかもしれなかった彼は、その存在を歴史に刻むものでもなく、あっという間にただの人になってしまった。
それが悔しかった。
だから柚は泣いたのだ。
きっと今日流した涙も同じモノなのだろうと柚は思った。
人間とはいうのは、大人になれば誰であれ社会のパーツであると聞いたことがある。
そこには代わりがあるのだと。誰かは誰かの代わりになれるのだと。
なんと物悲しい世界だろう。だが効率のいい世界でもある。
柚の本質はどちらかといえばリアリストなのだから。
だが。
それでも。
代わりのない人間はいるはずなんだ。
その人が、その人でしかできない役割があるはずなんだ。
私はそういう人間がいることを証明したいんだ。
目を見開き身体を起こす。
ポケットから転げ落ちたであろう足元に転がっているスマートフォンを拾うと、それを強く握り締める。その瞳にはすでにいつも彼女と同じように、強い意志が宿っていた。
柚は自分自身の事をよく知っている。リアリストであることの反動が自分の本質なのだと。
「私はこう見えて、恐ろしくロマンチストなんだぞ」
―― Next #04