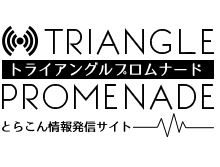『I Will Always Love You.』 #01 *三咲凪編
#01/雨風 :amekaze
――#01
六月中旬。
いくら梅雨どきとはいえ、こうも律儀に雨も降り続くと、迷惑をこうむる人間もさぞ多いだろう。
降り続ける雨でぬかるんだ土を踏みしめ、野球部員が懸命にボールを追いかけている。農家の方には申し訳ないが、彼らにとってはこの雨は恵みの雨でもなんでもない。ただただ憎らしい存在である。
「……にしたって」
こんな天候の中必死に練習をしたところで、一乃谷高校のような進学校では甲子園出場など夢のまた夢。せいぜい地区予選の一回戦を白星で飾ることができるかどうか。ひょっとすると二回戦突破ぐらいは狙っているのかもしれないが、所詮はその程度。
「小さな目標の為に、難儀なこって」
冷めた目で野球部の練習を眺めながら、一人の少女がグラウンド脇の小道を歩く。まるで足元に注意をはらうことなく水溜りを器用に避ける少女――木住野柚は、文化部が集まるクラブ棟へと向かっていた。
運動部の天敵である雨も文化部には関係がない。
――傘をさすのは面倒な事にかわりないんだけどね。しかもこの傘じゃ……。
柚は片手に持った安っぽいビニール傘をパラシュートのようにして、少し大きな水溜りをジャンプした。水しぶきを立てる事なく着地するその姿は、まるで今までどんな壁にもぶつかったことがない柚のスマートな生き様を現しているかのようで、劇中の華麗なワンシーンのようだった。
「……なんかつまんないなぁ」
修正箇所をチェックした脚本を文芸部に届けてこいという演劇部部長の花房了輔の指示で、校舎から少し離れた場所にあるクラブ棟へと向かう柚は、雨空と同じく晴れない顔である。
演劇部期待の新人。それが今の木住野柚の肩書きだ。
入部して二ヶ月。
持ち前の飲み込みの早さ、どんなことにも対応できる応用力、そして物怖じしない性格を最大の武器にして、柚は演劇部内でも一目置かれる存在へとなっていた。
にも関わらず、そんな自分がこうして使いっぱしりになっている。これは一体どういうことなのか、と思うのは至極当然といえよう。
「ちぇっ」
クリアファイルに入った分厚い脚本を小脇に抱えて、柚は口を尖らせる。
「木住野またきたんだ?」
「ん?」
クラブ棟まであと少しとなったところで、柚は聞き覚えのある声に振り返る。
予想通りの声の主だった。柚を見て小走りでもしてきたのだろうか。ズボンの裾を濡らしているところを見ると水溜りに思い切り足を突っ込んだのだろう。
「足、びしょびしょだよ、仲地」
柚の言葉に男子生徒、仲地瑛太はハハハッと笑った。
毎度の事といえ、瑛太のマイペースに柚は毒気を抜かれる。彼のこんなところを柚は気に入っているが、果たしてドジっ子属性の高校生男子とはいうのは、世間的な評価としてはどうなのだろうかと内心考えてしまう。
「で、今日もいつもの用?」
瑛太の問いに、柚はクリアファイルをパタパタと振る行動で答えた。
「ああ、やっぱりまたリテイクか。部長厳しいね」
「本当にね」
その度にこうやって文芸部にまで足を運ぶことになっている柚としても、乾いた笑いしか出て来ない。
そうこうしている間にクラブ棟へと辿り着いた二人は、鈍く黒光りする傘立てへ水滴を振り落としたそれぞれの傘を突きさした。
「……これ盗まれたりしないよね?」
「木住野はそういうところ気にするよね。案外ちっちゃいって言うか……」
「うるさいなー」
雨は朝から降り続けているのだ。こんなに日に傘を持たずに学校に登校する生徒もさすがにいるまい。と思いながらも柚がついこんな事を言ってしまったのは、先日コンビ二で傘を盗まれたばかりだったからだ。
お気に入りの黄緑色の傘は当然ながら手元には戻ってくることはなかった。
「ここでまた誰かが盗んでくれでもしたら、意地でも犯人を見つけ出して八つ当たりしてやるのに」
柚はそんな事を考えながら二階へと続く階段を乱暴な足取りで登り始めた。
木住野柚は現状に不満を抱いている。
柚は新人の為に組まれた練習プログラムをすでに終了してしまっていた。
楽しいと思った事に対してはとことんのめり込む性格の柚にとって、練習という行為には苦痛という言葉は存在しない。そんな自分の欲求を忠実に実行してきた今の柚は、練習量も並ではなかった。これでは他の一年生と大きく差がつくのも致し方ない。
他の一年生は今頃まだまだ発声練習をしているのだろう。その指導に手一杯の二年生。もちろん花房部長の率いる三年生も、文化祭の準備や進路の事などで柚を見る暇などはなかったわけで。
そんな中、ただ一人だけ自分の練習時間を削ってでも熱心に指導をしてくれた三年生の先輩がいた。
が、その先輩も最近は不調であるせいか、柚の練習を見るところまで手が回らなくなくなっている。その人との練習が大好きであった柚としては、唯一の楽しみを取り上げられた格好だ。
もちろん自主練は行っているが、期待の新人とはいえ今の柚の立場では演劇部の中でできることは限られている。あげくの果てに、柚に回ってきたのはおつかい係のお役目だった。
こんな状況に不貞腐れるなという方が無理な注文である。
「こんなのってありえないですよね! ね!! ね!!?」
「ふーん。つまり木住野は優等生すぎたがゆえに、ここに来てる。で、それが面倒くさいなーと」
赤線の引いてある修正箇所がチェックされた脚本。そのコピー用紙をプルプルと震わせる文芸部副部長の皮肉たっぷりの言い回しに、柚はあわてて首を振った。
「い、いや、そういうつもりでいったわけでは……!」
「いいや、明らかに不満たっぷりの愚痴だったよ、木住野」
隣に座る瑛太はどうやらフォローする気が一切ないようだ。
「そこは、もうちょっと、こう……ぶひょ」
柚の言葉を遮るかのように、文芸部副部長の守山珠希(もりやまたまき)は彼女の片頬を引っ張った。
「なーにが、もうちょっとこうよ!」
「いたひ! いたひ! にゃにひゅんですかー!?」
柚よりも一回り小さな珠希は、その小柄な身体に見合わない握力で柚の頬をつねり続ける。
「はにゃひてください!!」
「こちとらイライラしてんだ、ちょっとぐらい八つ当たりさせなさい!」
柚の頬をパッと離すと、珠希は軽い鼻息とともに机の上に乗り出していた小さな身体をひっこめた。無理やり頭頂部でまとめられ、まるでパイナップルのようになっているセミロングの髪がふさふさと揺れる。
「ほーら、木住野が無神経に愚痴を言い続けるもんだから」
つねられた頬を撫で続ける柚に、瑛太は笑いかける。
「後輩くんも、こうなることがわかってるならさっさとソイツを止めなさい」
「はは、たまにはお灸をすえるのもいいかなぁと思いまして」
ひどいと呟きながら、柚は細長い会議机にオデコをぶつけて突っ伏す。
「そもそも、木住野はここにこれ届けに来るだけじゃない。私はこれ直すのにどんだけ時間かかると思ってるん?」
「ううっ……」
珠希が柚に当たるのも無理はない。このリテイクですでに五回目。最近、珠希の肌が荒れてきているのは、間違いなく度重なる脚本の修正による寝不足のせいだ。
「まぁまぁ、もう十分おしおきになったみたいですし、その辺で」
唸り続ける柚の頭を軽く叩きながら瑛太は席を立つ。
「こういう時は甘いものを飲むのが一番ですって。コーヒーでいいですか?」
「……そうな。砂糖六個で」
日増しに砂糖をいれる数が多くなっていくことに一抹の不安を覚えながら、瑛太は電気ケトルを持つ。
「あれ? もう水なかった」
「ああ、そういや昨日使ったもので最後だったな」
電気ケトルは便利であるが、水をなみなみと入れてあったとしても、コーヒーを飲める回数はせいぜい一桁台であるのが弱点だ。それでも水道も近くにない上に火を使う事が出来ないクラブ棟で、温かい飲み物を飲めるのはありがたいのだが。
「ちょっと外、行ってきますね。ついでになんかつまめるお菓子でも買ってきます」
「あいあい、よろしくね、後輩くん」
部室のドアを開け外に出た瑛太は、この雨を浄化すれば飲めるんじゃないかと小声で呟くが、たかが水汲みに何時間かけるつもりだという珠希の呆れた声に笑いながらドアを閉めた。
コツコツと階段を下りていく瑛太の足音が消えるのを確認すると柚は顔をあげる。しかめっつらで脚本を読み直す珠希に、柚は前々から思っていた疑問を投げかけた。
「……あのぉ、ちょっと聞きたいことが」
「ん?」
「先輩はいつまで、仲地の事を後輩くんって呼ぶんですか?」
「え、そこなの? こう脚本の何がダメなんですかとか、そういう事じゃないの?」
コピー用紙とにらめっこをしていた珠希が、予想外の柚の質問に少しだけ戸惑って答えた。
「いや、だって私達が中学一年生からの付き合いだから……三年?」
「まだ三年だよ」
といっても、たったの十五、六年しか生きていない柚達にとっての三年は人生の五分の一である。決して短い時間ではない。
「もう三年ですよ」
だから柚は反論をする。
もう三年も経っているにもかかわらず、一向に深まらない瑛太と珠希の関係に、柚としては少しぐらい口出しをしたくなるというものだ。
「それはあれか、私が後輩くんを三年間も後輩としか見てないのはどうなの、って話か」
「まぁ、ありていに言えば、そんな感じ……です。だって先輩、好きでしょ、仲地の事」
申し訳程度に敬語を付け足す柚に珠希は苦笑する。
「そりゃ好きは好きだけどさ、あくまで後輩としてだよ。後輩くんは私にとって後輩以上でも以下でもない。それより先に踏み込む気なんかさらさらないんだ。だから、後輩くんって名前でいいんだよ」
「えー、でもでも、仲地のヤツ三年間も守山先輩の後を追いかけてるんですよ? 嬉しくないんですか?」
「木住野にはそう見えるのか」
うんうんと頷く柚に珠希は苦笑した。
中学時代の珠希は、わずか五人の部員ほぼ全員が幽霊部員という、文化部最果ての図書部に在席していた。
彼女の将来の夢は小説家になること。珠希は本気であった。
図書部には自分以外部活に顔を出す部員が全くいないのも、彼女にとって都合が良かった。何せ放課後の三時間は広い図書室を独り占めできていたのだから。たまに教師から言いつけられる本の整理さえしっかりしていれば、図書室はまさに彼女の城だった。休み時間に他の生徒がたむろしている図書室を見ると、「ようこそ私の城へ!」などとくだらないことを考えていたものだ。
そこで彼女はだれに邪魔されることもなく、お気に入りの本を読みあさり、そして自らの小説を執筆していた。
仲地瑛太がそこへ現れたのは珠希が二年生になった時。
どうせこの新入生も、他の部員同様とりあえず籍を置くだけだろう。そう珠希は考えていた。
――何にしても私の邪魔さえしなければどうでもいい。
その頃には拙いながらも数本の短編を書ききるだけの力をつけはじめていた珠希。ネットで短編小説を発表して一定のファンもつきはじめ、そろそろ長編を書いて新人賞に応募でもしてみようかと考えていた彼女にとって、新入生の存在など毛の先ほどの興味もなかった。
だが。
「こんにちは、先輩」
「お、おう、こんにちは後輩くん」
瑛太との挨拶は毎日のように放課後の図書館で交わされた。
積極的に人付き合いをすることなく、必要最低限の人間関係で生活するのは珠希のライフスタイルであった。だから自分の趣味に熱中することが全てだった珠希にとって、こうやって同じ人物と毎日のように時間を共有するなど久しぶりな事であると言えた。
「後輩くん」
瑛太に少し負い目があった珠希は、いつのまにか瑛太をそう呼ぶようになっていた。何せ、珠希は自分のやりたいことをする為に本の整理という面倒な職務を放棄し、それを後輩に押し付けているのだ。だから名前を呼び捨てにするなど後ろめたくてできなかった。しかしこれまで人付き合いを疎かにしてきた珠希には、後輩とはいえ異性の名を君付けで呼ぶのはいささか抵抗があった。
だから、中間をとって「後輩くん」と呼ぶようになったのだ。
「先輩」
一方瑛太は珠希をそう呼ぶが、そう呼ばれるのにふさわしい事など珠希は一度たりともしたことがない。むしろ嫌われる要素しか思いつかない。
が、瑛太は毎日のように図書館に顔を出しつづけた。そして珠希に話しかけるでもなく、戸締りをする時間になるまで窓際の指定席で持参した文庫本を読みふけっていた。
そんな後輩くんが、珠希の小説の生の読者一号となるまでには時間はかからなかった。
本の虫といってもいいほど、物語と名の付くものならどんなジャンルであろうが読破していった瑛太の感想は、常に珠希のインスピレーションを刺激した。その後発表したネット小説はより多くの読者を得たのだから、彼の感想なくして珠希の成長はなかったのかもしれない。
こうして二人は、現在も一乃谷高校の文芸部の先輩と後輩という関係として続いている。
「後輩くんと私は互いの才能に惚れてるんだよ。なんでも恋愛関係にもっていくのはよくないな」
「うー、でも男と女だと、そこから恋愛関係に発展してもおかしくないのにー」
不満そうに足をバタバタとする柚。そんな様子をみて仕方がないと珠希は口を開いた。
「あれだ、木住野にも、今お熱な人がいるよね?」
「私が?」
「そそ」
柚は腕を組み少しばかり真面目に考えてみたが、該当する人物は一人もいなかった。
「私にはいないけど?」
「いやいや、いるっしょ、演劇部に」
いやまったく心当たりがありませんといった柚の鈍さに、珠希はやれやれと溜息をついた。
「三咲凪先輩」
珠希のその言葉に、柚は目をパチクリとさせた。
「なに、その意表をつかれた顔は」
「いや、だって……お熱っていったら男の子の話じゃん。そんなのわかるわけないじゃん」
「私は、異性だなんて一言も言ってないだろう」
「……確かに」
柚はついつい二人の関係を恋愛ありきで考えてしまう。
三年間も男女間で友情を維持することができるのだろうか。しかも珠希と瑛太は二人きりでいる時間も多かったわけで、疑ってしまうというよりも、どうして恋愛感情が生まれないのか不思議でならなかった。
だが、柚はどうやら信頼という関係をすっかり失念していたようだ。珠希と瑛太。二人の関係性を自分に当てはめ、三咲凪という女性を柚は想う。するとなるほど。納得する話だという結論に至った。
「つまりさ、私と後輩くんはそういう関係なんだって」
「……なんとなく意味としてはわかります」
わかってくれればそれでいいと頷いた珠希だったが、彼女の不満そうな顔を見て、この問題がまるで解決してない事を察した。
「……納得してないじゃん」
「あ、わかりましたか?」
「わざと? ねぇ、わざとだよね?」
「だ、だって、それって先輩の気持ちじゃん。それはわかったけどさ……」
柚の言いたい事は。追いかけてきた瑛太の気持ち。
そこが珠希の説明に含まれていなかったのだから、柚としては納得が行かない。
「後輩くんの気持ちか」
珠希は柚の言葉を補足する。それを聞いて再びコクリと頷く柚。
「それこそ意味ない話だわ。後輩くんは、アレでいて意外と策士だから、そういうところ気付かせないのはさすがだと思うけど」
「はい?」
なんだかよくわからない珠希の言葉に、訝しげな顔をする柚。
「木住野は恋愛を語りたいわりに、恋愛に対する嗅覚が酷く欠けてるよね」
「えーっ!? なにそれー!!」
そう柚が大きな声をあげたとき、部室のドアがカチャリと開いた。
「外まで声きこえてるぞー、木住野ー」
コンビニ袋と電気ケトルを持った瑛太が帰ってきた。先ほどよりもさらにズボンの裾が濡れているのが彼のどんくささを証明している。
「あ、お帰り。あとでお金は払うわ」
「そうしてください、さすがにこんだけ買いこむと僕の財布が泣いてしまいます」
珠希と会話を交わしながら、瑛太は電気ケトルを台座に差し込むと電源スイッチをいれる。そのまま手際よくマグカップを本棚から出し始めた。
「な、仲地、コンビニ行って来たんだよね?」
それを眺めながら、柚を唖然としていた。
「んー? そうだよー、ほらお菓子もいっぱい買ってきたしね」
「いやいやいやいや! そうじゃなくてケトル持ったまま行ったの!?」
わりとよくやるよ、と瑛太は笑いながらインスタントコーヒーの粉をマグカップへと入れていく。
「後輩くんはいつもそうだよ。一回で済ますことができる用なら全部やっちゃおうみたいな。そもそも体裁とか気にしないやつだしな」
瑛太の行動を見つめながら、やっぱり変なヤツだと柚は改めて思った。
「ところで何の話をしてたんですか? 大きな声まで出しちゃって」
コンビニ袋の中身を物色していた珠希はいやらしい笑みを浮かべる。
「それそれ、後輩くんは策士すぎて逆に遠回りしちゃってるよなぁって話だよ」
「ははは、なんですかそれ」
過程を話さず、いきなり結論だけを言い切る珠希に瑛太は笑う。
「……なによー、私にはさっぱりよ」
「そうそう、後輩くんと私にだけわかればいいことなのよ」
無論、この段階では瑛太も何もわかってはいない。だが、わからなくてもそれなりに流す事ができる瑛太と、わからないことは気持ちが悪いと思ってしまう柚。なんとも両極端な二人に、やはり珠希はにやけてしまう。
それが余計に気に食わないのか、柚は憮然として「いただきます!」とお菓子の山の中からスナック菓子の箱を引き抜いた。
「ん、美味しい。やっぱインスタントといえども、缶コーヒーとは味が全然違うわね」
「ですね。甘さも調整できるし」
砂糖一個のコーヒーを飲む瑛太。
砂糖六個のコーヒーを飲む珠希。
柚が去った部室には再び静寂が訪れていた。
栞を外し、読みかけの文庫本に再び目を落とす瑛太。
脚本の赤線が引かれたセリフの修正をする珠希。
これが二人のいつもの関係である。
「さっきの話、わかった?」
そんないつもの空気の中、珠希はコピー用紙から目を離すことなく瑛太に質問を投げかけた。
「大体は」
「さすがだね、後輩くんは」
一年ぶりに、再び始まった瑛太と珠希の時間。
まるで長く離れていた恋人同士の時間が戻ったように見えないこともない。
しかし現実は――
「後輩くんは、また木住野の帰りを待つ生活か。もうちょっと正面から行った方がいいじゃないの?」
優しい珠希の声に、瑛太の笑みがこぼれる。
「いいんですよ、僕は。このぐらいの距離が一番好きなんです」
柚が鈍感であることはもちろん問題なのだが、珠希の目の前のこの男にも随分と問題がある。
「そんなんだから、木住野は私と後輩くんの関係を疑っちゃうんだよ」
「ははは、後から全部自分の勘違いだって分かった時に、慌てる木住野の姿とか見たいんですよね」
なんとも気の長い話だなと珠希は呆れた。
「そもそも、先輩と僕がそういう関係になることはないですよ。いや先輩と居るのは楽しいんですけど」
「私も後輩くんは頼りにはしてるけど、そういう風に見れないなぁ」
そして二人は、ニヤリと不敵な笑みを浮かべた。
「だって先輩、僕のタイプじゃないですもん」
「私はおまえみたいなやつ、まるでタイプじゃないんだな」
珠希は三年間、いや正確には二年と三ヶ月、こうやって瑛太の恋の行方を見守ってきた。彼女にとっての興味は、彼がどうやって決着をつけるのか。ただその一点につきる。
「私はね、後輩くん。あんたがどうやって木住野に告白するか。それが楽しみでしょうがないんだよ」
「がんばりたいんですけどね。木住野次第といった感じでしょうか」
頼りない返事をする後輩に、珠希は笑いがこみ上げてきた。
木住野柚は、三年間という長い時間を過ごしてきた異性同士なら、恋愛関係になってもおかしくないと、一般的な女子の思考はできる。にもかかわらず、自分自身も瑛太と一緒に長い時間を過ごしてきた異性であるということが、すっかり頭から抜け落ちている。
そんな鈍感な少女を相手に、この絡め手オンリーで挑む無謀な後輩。こんなに面白い素材は他にはないだろう。
「いつか後輩くんたちの事は小説の題材にしたいなって思ってんの。だからもうちょっと一波乱あると面白いんだけどなぁって常に考えてるよ」
「勘弁してくださいよ。……あ、でもその場合はフィクションだってちゃんと書いてくださいね?」
心配するところそこなんだと、柚と同じくいちいちズレたところを問題視する愛すべきお馬鹿な後輩達に珠希は苦笑した。
「オッケー、オッケー。ちゃんと有名になったら、あとがきに書いてやるって」
「有名になるって目標はいいですけど、まずはその脚本を仕上げましょう」
「……そうな」
いきなり現実へと引き戻された珠希が、面倒くさそうに再びコピー用紙に目を落とす。
今晩は睡眠をとることができるだろうかと、珠希は大きな溜息をついた。
「いやぁ、失敗失敗。ついサボっちゃったよ」
柚は演劇部のホームである第二音楽室へと帰りの道をのんびりと歩いていた。
五回に渡る使いっぱしりを命じた花房部長には多少恨みがある。そのせいで、柚の足取りはあえてゆっくりなのだ。だがさすがに、新人がこうも油を売っていては叱られるのは必至であろう。
と、ふいにケータイがポケットの中で震えた。
「おっと?」
スマートフォンを取り出してその画面を見る。
そこには「三咲凪」と表示されていた。
三咲凪。
演劇部の副部長にして、柚がこれまでの人生で唯一憧れを抱いた人物。
あの日、柚が親友の上林咲奈に連れられて行った演劇部の春公演。
プロの力がどれほどのものか見極めてやろうなどと意気込んでいた柚だったが、公演が終わるころにはそんなことはどうでもよくなっていた。
柚は主演女優の凪の演技に涙を流した。
たかが学生の演劇で、だ。
プロでもなんでもない、一介の女子高生の演技に、だ。
完全に負けたと思った。しかし、悔しさなど全くなかった。
ただ、あの人のような演技をしてみたいと思った。
あの人の隣に立ちたいと思った。
「も、もしもし、三咲先輩?」
急いで電話にでると「あっ」と可愛らしい声が聞こえた。
『ごめんね、あんまりにも帰りがおそいから、どうしたのかなぁって』
受話器の向こう、柚の憧れの先輩、三咲凪は心配そうな声でそういった。
「すいません、文芸部の守山先輩とつい話し込んじゃって……」
『ううん、最近柚ちゃんの練習を全然見てあげれなかったから、怒ってそのまま帰っちゃったのかなって」
「え!?」
凪の意外な答えに柚は思わず大きな声をあげる。
『ひうっ』
「あ、ああ、すいません、いきなり大きな声を出しちゃって」
凪が耳を押さえる姿が頭に浮かび、柚は慌てて謝った。
「ちがうんです、私が勝手に拗ねてただけで、三咲先輩がお忙しいのは知ってますし……。むしろ怒られるのは私かなぁって……。あ、そもそも、まだ学校にいますから!」
『ああ、そうなんだ。良かった~、大丈夫だよ、私は怒ってないから。あ、花房くんはちょっと怒ってたけど』
クスクスと笑う凪の声に、柚はほっと胸を撫で下ろした。
「あ、あはは……、部長が怒ってるのは大体が察しがついてたんですけどね」
『あ、それでね、あと二十分ぐらいしかないけど、私もちょっと手が空いたの。この前合わせてみたいって言ってたところ覚える?』
「え!? 今からですか!?」
『うん。みんなそろそろ帰り始めちゃってるけど。柚ちゃんさえよければどうかなって』
「やりますやります! すぐ帰ります! ちょっとだけ待っててください!」
『あ、慌てて転ばないでねー』
凪の言葉に大丈夫ですと元気よく答えた柚は、スマホの通話を切ると水溜りを気にすることなく全力で駆け出した。
―― Next #02