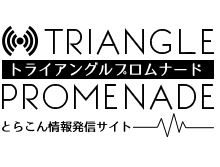『Tea for Two』 #07 *天ヶ瀬あかね編
#07「あたしも月島さんと友達になりたい!」

――#07
「うお、うめぇえ! なんだこれ!?」
「美味しい! 美味しいよ天ヶ瀬先輩!」
「こ、これは美味い……」
あかねと円が作った夕食が供された相馬家のダイニングは賞賛の声に包まれていた。
テーブルの横に立つあかねは、神妙な面立ちで口を一文字に結びつつも、笑顔を抑えきれずにいる。
チリソースのハンバーグとガーリック胡椒風味の野菜炒め。確かに味の濃い料理の組み合わせだが、これまでのあかねの味付けと一線を画していることは、それを口にした面々の評価が如実に物語っていた。
「えーと、みんな食べながら、なんとなく聞いてくれたら嬉しいかな?」
美味しそうに料理を頬張る皆に、あかねの隣に立つ円が説明を始める。
「ん、どうじょ、むぐっ、どうじょ」
口の中いっぱいにハンバーグを詰め込む庄治に、貴之が汚いと不満げな声をあげる。だがそんな光景も、今のあかねにとってはむしろご褒美といえよう。
「天ヶ瀬さんの舌でも、元々美味しいと思える食べ物……あ、ごめんね、今のは酷い言い方だったね……」
あかねはブンブンと首を横に振った。
「そんなことない! 月島さんの言うとおりだと思う! あたしが自分の舌の事を一番わかってるつもりだし!」
料理の説明が始まるはずが、二人ともしょんぼりした表情になり黙り込んでしまう。
「ん、円ちゃん、説明説明」
シエルが口を挟んで脱線しかけた話題を見事に軌道修正する。
「あ、うん……」
円は頼りない返事をして少し考えると、閃いたといった顔付きでポンと両の掌を叩いた。
「そうだ! 天ヶ瀬さんから説明してもらうのはどうかな?」
「ふ、ふえっ!?」
円の無茶振りに、あかねは思わず奇声をあげる。
庄治が口の中のものを頬張ったまま、またもやあかねをからかおうとしたのだが、テーブルの下、貴之は庄治の脛を軽く蹴飛ばしてそれを阻止した。
「僕からもお願いするよ、あかね」
あかねは照れくさそうに頷く。
「さぁ、早く早く。みんな美味しいって言ってくれてるよ! どーんと自慢しちゃって!」
円はあかねの背中に手を添えると、そう言って目を輝かせた。その曇りのない瞳にあかねは先ほど救われた事を思い出す。あかねは心底今日ここに来て良かったと思った。
「……ありがとう、月島さん」
あかねは円にしか聞こえない程度の声でお礼を言った。ニコリと頷く円に微笑み返すと、晴れやかな表情で料理の説明を始めた。
「えと、それじゃ説明するね。改めてする程の事でもないと思うんだけど。あ、最初に言っておくけど、あたしもこの料理はさっき食べました! すごく……ものすっごく美味しかったです!」
月島円は、あかねにとって久しく禁忌にも似た存在だった。
学祭中、貴之に告白されたあかねは幸せの絶頂期を迎えていた。
それまでのあかねにとって、現実の世界は虚構に過ぎなかった。優等生の仮面を被り、男勝りで勝気な自分を演じる事は、本当の自分を見せなければ傷つく事もないというあかね流の処世術であった。彼女のリアル、彼女の願いは、自らが描き出す物語の中にのみ存在したのだ。
そんなあかねに、現実の世界にも彼女の求める物語は存在する、彼女を救い出す王子様は確かにいるのだと貴之は教えてくれた。彼はその役を買って出てくれたのだ。
だが幸せを手に入れ、現実の世界が彼女のリアルになることの代償として、そこは痛みで溢れていることをあかねは知ってしまう。
親友である三咲凪から貴之を奪ってしまった事は、凪や貴之の想いとは関係なく今なお彼女を苦しめている。そしてそれを円に対して繰り返してしまうことへの恐怖、いや、すでに奪ってしまっている事実が、あかねの心に暗い影を落としていた。
あかねも歳相応の女の子の必須スキルである恋愛嗅覚というものは持ち合わせている。いつも貴之の側に寄り添うようにしていた円が、彼に恋をしている事もすぐさま察する事ができた。もしかすると、すでに付き合っているのではないかと考えもした。
円にとってみれば、自分は急に現れた泥棒猫そのものだ、とあかねは思う。どう見てもあかねに非があることは明らかだ。大切な人を奪われる苦しみは、想像するだけで胸が痛む。
そして今日、あかねは円と話すことでその彼女の痛みに直に触れてしまった。
その痛みを受けた時の苦しみをあかねを知っている。あの暗い部屋に引きこもった一ヵ月を思いだし、その苦しみを円に与えているのが誰あろう、自分自身であることがとても辛かった。
——でも、それでも今、貴之の彼女は幼馴染である月島さんではないんだ。自分なんだ。天ヶ瀬あかねなんだ。
せめて、円が貴之と付き合っていなかったという事実が欲しかった。
それならば、少しだけ自分の罪は軽くなるのではないか。少しは許されていいのではないか。
そう考えたあかねは自分を嘲笑った。なんと浅ましい考えだったのだろう。
「あ、美味しい……」
円に言われたとおりのレシピで作ったチリソースの味見をしたあかねは、その美味しさに舌を巻いた。
「でしょ?」
円はそう返事をしたものの、少し涙目になっている。
「これ、そうとう辛いけど、月島さんは大丈夫? 辛すぎない?」
ちょっと辛いかなと困ったように微笑む円を見て、やはり自分の舌に合わせてはまともな味付けにはならないのかと、あかねは溜息をつく。
「あ、違う違う! 私にはちょっと辛いけどこれは美味しいよ! 私が元々辛いものが苦手ってことなので、この場合はあまり私を信用したらダメだよ」
「……ん? てことはこれ、月島さんから見て不味いわけじゃないの?」
「うん、味はバッチリだよ! 辛いのが苦手なのは私の個人的な弱点です」
その言葉を聞いてテンションが上がってきたあかねは、ソワソワし始める。まさに踊りだしたい気分というヤツである。
「じゃあじゃあ、これって月島さんからしても、美味しいって事でいいのかな!?」
あかねの念押しに円は笑顔で頷くと「これが多分正解です」と自信満々に言い切った。
円の選んだあかねの濃い味付け料理の当面の解決策、それは至極簡単であり真っ当なものだった。
まず、誰もが味付けが濃い料理だと認知しているものを選ぶ。もともと濃い味付けの料理なのだから、少しばかり味付けが濃すぎてもそれほど気にはならないだろう。
そして、香辛料をふんだんに使って調理する。あかねの味覚を持ってしても、香辛料の刺激があれば調味料をそう大量に使わなくても満足がいくはずだ。
この策は見事に的中することとなる。
「せっかくだからハンバーグをこのチリソースで煮込んじゃおう」
円はそう言うと、フライパンに焼き上げたハンバーグを二つそっと置く。ジュワッといい音と共に赤いソースの海に沈んでいくハンバーグを見て、あかねはパチパチと手を叩いた。
「すごいすごい! 月島さん、すごい!」
円にしては珍しく、ふふんっと得意気な表情を見せる。
「……そっかぁ、あたしが美味しいと思えるものを月島さんが美味しいって言ってくれることって、こんなに嬉しい事なんだ」
円は、自分が美味しいと思える料理が作れると、他の人にも幸せをお裾分けできるんだよ、と言った。その言葉の意味も今のあかねには理解できる。自分の好きなものを相手も好きだといってくれることは、自分を犠牲にしてでも相手を喜ばせようとした時とは、根本的に違う喜びなのだ。
「これをタカくんが食べて、美味しいって言ってくれれば、天ヶ瀬さんもっと嬉しくなれるよ?」
ハンバーグをひっくり返しながら円が優しく微笑む。
あかねはキュッと胸を締め付けられた。きっと、こうやってこの人は貴之の喜ぶ姿に幸せを感じてきたのだろう、と。円はこれからもずっと貴之の隣にいたいと願っているにちがいない。それでもあかねを思いやり、こんな言葉をかけてくれる。
そんな彼女から貴之を奪ってしまったことがあかねは辛かった。とにかく詫びなくてはと思った。
「あ、あの……」
「ん?」
しかし、少しだけ開いたあかねの口元から、その後の言葉が続く事はなかった。あかねは急激に唇が乾いていくような錯覚を味わいながら、このまま時間が止まってしまうのではないかと感じた。
「……あのね、なんとなくだけど、私ね、今天ヶ瀬さんの考えてる事わかるよ」
円はフライパンから目を離さない。あかねはそんな円の少しだけ寂しそうな横顔に、今度は心臓を鷲掴みされたかのような痛みを感じた。
「でも、それ以上言わないで。今日は……うん、今日はそういうのやめにしよ?」
円はコンロの火を止めると、フライパンの中のハンバーグを小皿へと盛りだした。
「やっぱりガスコンロはいいなぁ〜。私の家は電気だから火力なくて炒飯とか美味くできないんだ」
言葉もなく立ち尽くすあかねの隣で、円がハンバーグにチリソースをかけていく。
「……はい、試作一号完成っと」
ハンバーグを盛った小皿を両手で持ち、それを見つめる円。
あかねも、円と同じようにその小皿を見ていた。
「あ、あのね、天ヶ瀬さん」
円は顔をあげずに、震えた声であかねの名を呼んだ。
「……ああ、ダメだなぁ私。料理の事なら結構色々と話せるんだけど、面と向かって人と話す事には全然慣れてなくって」
「……」
あかねには円が考えていることがわからなかった。
円はあかねの事がわかるといったのに、自分にはわからない。被害者だけが加害者の痛みを理解している。これではあべこべだ。それがあかねにはとても歯がゆかった。
そっと小皿を差し出す円。申し訳ない気持ちであかねはそれを受け取るが、円は手を離そうとしない。二人で小皿を持ち合う形になったまま動きが止まる。
一瞬間をおいて、円は勢いよく顔をあげた。
「あ、あのね!!」
「は、はい!?」
円の大きな声に、あかねも思わず大きく返事をしてしまう。
そのままの姿勢で妙な雰囲気のまま見詰め合い、固まる二人。
「……ぷっ」
「ふ、ふふっ」
やがてどちらともなく笑い声がもれ、張り詰めていた空気は穏やかなものに変わった。
あかねは、ようやく手を離した円からハンバーグを盛りつけた小皿を受け取ると「こんな事してたら冷めちゃうよね」と顔を赤らめた。
「きっとそれ、すごく美味しいと思う」
「うん!」
二人はお互いの顔を見合わせ、もう一度微笑みあった。
「……あのね」
円は、その透き通った瞳をあかねに向ける。
「だから、その……今日はね、天ヶ瀬さんと友達になれたらいいなってここに来たんだ」
その言葉は暗く閉ざされたあかねの心の扉を開く魔法の言葉だった。
少し錆付いた音を立てながら開く扉の隙間から、明るい光が差し込んでくるのをあかねは確かに感じていた。
「料理を通して、……天ヶ瀬さんと仲良くなれたらいいなって。美味しい料理を作って、天ヶ瀬さんが笑顔になれたらいいなって」
あかねは、自分の瞳が潤んでしまっているのではないかと心配になった。
今日、あかねは、目の前の少女に涙を流させることになってしまうかもしれない、と思っていた。それなのに、その少女の言葉があかねに幸せの涙を流させようとしているのだ。あかねにとって、こんなに嬉しい事などありはしなかった。
「……あ、あたしも! あたしも月島さんと友達になりたい!」
涙をこぼしたくない。そんな必死な想いがあかねに勇気をくれた。普段から想像もできない程にうわずった声のあかねは、まるで幼子のように無邪気な笑顔になっていた。
あかねはこんなにも素晴らしい出会いを、こんなにも素敵な時間を与えてくれた神様に感謝した。
そして、この現実の世界の物語は自分自身が勇気をもって踏み出していけば、しっかりと応えてくれるものだとも実感したのだ。
ハンバーグはとても美味しかった。チリソースはかなり辛かったが、でもそれ以上に幸せのスパイスがピリリと効いていた。
昼間の暖かさと打って変わり、その夜は急激に冷え込んだ。
吐き出される息が雪の結晶のようにキラキラと光り輝き、すぐさま幻のように消えてゆく。
「わざわざみんなで送ってくれてありがとね」
円の自宅は住宅地のど真ん中ということもあり、自然と声も小さくなっていた。
「まぁ、いくら近いとはいえもう九時も回ってたしな」
貴之は持っていた手さげカバンから、ビニール袋を取り出すとそれを円へと手渡す。あかねにはその中身を予想できたのか、クスリと笑う円に近づいた。
「つーきしまさーん、それってーなぁーに?」
「ふふ、天ヶ瀬さんの思った通りだよ。あんなに余らせても仕方ないしね」
円が開いてみせた袋の中を、あかねはヒョイっと覗き込む。案の上そこには大量のもやしが詰められた大きなタッパ−が二つも入っていた。
「う、悪かったわ」
貴之の後ろからシエルが言葉を漏らす。バツが悪そうな顔を見られまいと、首をマフラーの中にうずめながら、シエルはプイと後ろを向いてしまった。
「しかし、寒いなぁ…。月島さんも薄着なんだし、早く家入って温まった方がいいぜ」
ブルブルと震える庄治に、円はありがとうとお礼を言うと、再びあかねに向き直る。
「天ヶ瀬さん、あとでメールするね」
円はごく自然に微笑む。今度は勇気を振り絞る必要はなかった。そんな円の気持ちは、その軽やかな声であかねにも届いた。
「うん、あたしもするよ! 絶対にする!」
あかねの元気溢れる声を聞き、安心したかのように「またね」と小さく手を振って円は玄関の扉を開いた。
嵩鳥町はいわゆる田舎町で、普段から星がよく見える。今日は寒さで空気が透き通っているのか、一段と輝いて見えた。そんな満天の星空の下を、貴之達四人は連れ立って歩く
「うわ、なんかすげー青春してる感じがするオレ達!」
庄治がはしゃぎながら、恥ずかしげもなくそんな事を口にする。
「かっこいいようで恥ずかしいセリフですね」
「でも寒いのイヤ! シエルちゃん、マフラー一緒に巻かない?」
「最後で台無しなところがキモオタ的ー。丘村先輩キャラ立ってますよね」
わずか数時間のうちに、シエルの中で庄治のポジションは決まってしまったようだ。
住宅街を抜け、国道沿いを歩く。賑やかに騒ぎ立てる庄治とシエルの後姿を見ながら、貴之とあかねは少し離れて着いて行く。
円を送り届け、今度は庄治を駅へと見送りにいく番だ。
その後、あかねを自宅まで送り届けるプランなのだが、このルートは意外に距離がある。自転車があればいいのだが、あいにくシエルは自転車を持っていない。四人での行動となるとこうやって歩くしか手はないのだ。
「ああ、でも自転車の二人乗りかぁ。彼女を後ろに乗せて走るってのは結構夢だ」
貴之が考えた事をそのまま口に出す。星を見上げながらご機嫌な口ぶりの貴之を観て、あかねの頬も緩む。
「こんな夜中に二人乗りなんかしてたら、おまわりさんに怒られるわよー」
「ま、怒られたら怒られたで」
「ふふっ、それはそれで面白いかもね」
冗談とも本気ともつかない答えだったが、あかねもそのぐらいの共犯者になるのは楽しそうだと笑う。
前を歩く庄治がシエルに軽く蹴りを入れられている。そんな光景を眺めながら、貴之は少しだけ声のトーンを落としてあかねにたずねた。
「……円、どうだった?」
「うん、びっくりした」
「?」
「びっくりするぐらいいい子だった」
「そっか」
「うん、今日ここに来れて本当に良かった!」
そう答えるあかねの笑顔はあまりに清々しく、吐き出される白い息は、彼女の端正な横顔を神秘的に演出していた。
「……よ、良かったな」
不覚にも見とれてしまった貴之は、慌ててあかねから視線を外す。
あかねとの付き合いは確かに色々と問題を抱えている。シエルと庄治にも問い詰められた事だが、目下のところ最大の危険は、貴之自身が暴走してしまわないかという事だ。シエル達の前では格好をつけたものの、健全な十七歳の少年の理性がその欲望を押さえつけるのは中々に難しい。
「どうしたの?」
急に黙ってしまった貴之にの顔を、キョトンとして覗き込むあかね。
「なんでもない」とぶっきらぼうに言うと、真っ赤になった顔に気付かれないよう、貴之は別の話題を探すのに必死になっていた。
数日前と同じく、馬鹿な事をほざき続ける庄治を駅に送り届け、トリプルキックで改札口に放り込んだ貴之達三人は、あまりの寒さに駅前のコンビニで暖を取っていた。
さすがは土曜夜の駅前。この程度の寒さでは休日の開放感に歓喜する人々の行動をじゃまする事はできないようで、平日以上の賑わいを見せていた。
今、貴之達が寄り道しているコンビニ店内も、学校帰りに彼らが利用する時の倍以上の客で溢れ、一足早くクリスマスのような雰囲気をかもし出している。
「うう、本当に今日は冷えるな~……カイロでも買っておくか?」
熱々の缶コーヒーを、両手の中で握り締めながら貴之がシエルにそう提案する。
「うん、それもいいんだけど……」
何故か生活雑貨のコーナーにやってきたシエルが歯ブラシを物色し始めた。
「まぁ、この辺が妥当か」
「何が?」
「歯ブラシ」
そういいながらシエルは赤い歯ブラシをフックから外す。
「なんだ、新しい歯ブラシに変えるのか……赤色?」
赤い歯ブラシを見ながら貴之は少し不思議に思った。
シエルの好みは黒である。彼女の選ぶカラーは無機質で黒い光沢を放つモノが多く、ありていに言えば渋い趣味をしているのだ。そのシエルが赤という女性らしい色を選択することは貴之の記憶にはあまりない。
「女の子といえば赤だしね」
シエルは手にした歯ブラシのパッケージを軽く振るとニヤリと笑う。
「ふーん」
彼女の心境の変化など貴之が知る由もない。
そんなこともあるんだろうとなんとなく納得した貴之に、シエルは缶コーヒーをよこせと手を出した。
「なんだ? 奢ってくれるのか?」
「馬鹿言うな、ちゃんとあとで返せよな。ついでだから一緒に買ってくるってだけだ」
「そりゃそうか」
倹約家のシエルにしては珍しい事を言うと思った貴之だったが、シエルはやはりいつものシエルなのだった。奢りではないといういつも通りの日常に、何故か安心した貴之は缶コーヒーをシエルに手渡した。
「うん、レジ混んでるから、タカユキは天ヶ瀬先輩とちょっと待ってて」
「お待たせ~。いやいや、あっちも結構並んでたからね」
丁度トイレから帰ってきたあかねがそう言いながら貴之の後ろから顔を出した。
「あ、お帰り」
「うん、ただいま」
ニコニコと笑いかけるあかねに、貴之はまたもやドキリとしてしまう。
そんな彼の表情を見逃さなかったシエルは「ふふん」と意地の悪い笑い声と共に、レジ周辺の人混みへと消えていった。
「……あんの野郎」
シエルに心の内を読み取られた事は屈辱だったが、そんなことより上気した自分の顔をなんとかしなければと焦る気持ちのほうが貴之には大きかった。今日に限っては、普段のようなポーカーフェイスはまるで機能しておらず、何とか気持ちをコントロールしなければと必死になっていた。
「じ、じゃあ、とりあえず僕らは店の外で待つか」
「ん、そだね。混んでるし、身体も大分温まったしね」
あかねのその言葉に「温まりすぎたけどな」と小さく呟いた貴之は、その言葉の通りに火照った顔と気持ちを冷やすべく店外へと向けて歩きはじめた。
店前でシエルを待つたった数分の間に、急激に身体が冷えだしたあかねは、ブルっと大きく身体を震わせた。
「さ、寒い」
「寒いな、確かに」
昼間が暖かだったせいで、あかねは上着を持ってきていない。薄手のカーディガンだけでこの寒さに耐えるのはさすがに無理があったようだ。
「こういう時にダッフルとかだったら、一緒に入る? とかやるのかなぁ」
「昭和のドラマじゃないそれ」
大体こんな人混みの中でそんな真似をしたら恥ずかしくて血液が沸騰してしまう。
貴之もあかねも同じ事を想像したのか、『ないなー』と見事なハモりをみせた。
「なにがないって?」
いつの間にか店内から出てきていたシエルが声をかける。
「ん、激情に任せると、黒歴史をどんどん作るんだろうなぁと」
貴之の言葉にうんうんと頷くあかね。
まるで達観したかのような二人の表情に、貴之とあかねが似たもの同士である事をシエルは改めて感じた。この二人は、つい最近自分達がどれほど恥ずかしい過去を作ったのかを完全に棚に上げている。これを笑うなと言うのは、シエルには無理な話である。
「くっ、ぷ。んっ、うん、そ、そんじゃ帰ろか」
口を押さえ笑いを堪える。この後どうやって苛めてやろうかと、湧き上がる悪戯心が顔に出ないようにと必死に堪える。
「って、おいどこに行くんだ」
二人に背を向けて歩き出すシエルに貴之が声をかける。
「あ、雨宮さん、あたしの家はあっちだよ!?」
あかねも慌てて、シエルの歩き出した方向と真逆の方角へと指を向けた。
「あー……」
シエルは、どうやって二人を言いくるめようかと、頭を掻きながら考えつつ振り返る。
「私寒いからさ、もう家に帰りたいのよね」
「は?」
「うん。だからタカユキ、家まで送っていってよ」
事態が飲み込めない貴之に、シエルは仕方ないなといった表情で続ける。
「だからさ、天ヶ瀬先輩の家までこっから行くよりもタカユキん家に戻った方が近いじゃん? 要するに、三人で戻ろうってこと」
それともこんな美少女一人に夜道を歩かせるつもりか? とシエルは貴之をにらみつける。
「いや、何を滅茶苦茶なこと言って……」
「最後まで言わないとわからないか?」
シエルは再び意地悪く笑うと、貴之を無視してあかねに顔を向ける。
まるで状況を把握できないあかねは、口を半開きにして無言で立ちすくんでいた。
予想通りの展開にシエルは満足すると、コンビニのビニール袋から赤い歯ブラシを取り出す。
「天ヶ瀬先輩、今日ウチに泊まっていってよ。ほら、歯ブラシも買っちゃったしさ」
先ほどと同じように歯ブラシのパッケージを左右に軽く振り、ニヤニヤと笑うシエル。
本日二度目のあかねの驚きの声に、道行く人々も何事かと足を止めたのだった。
―― Next #08