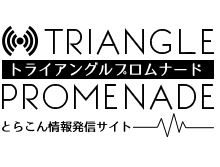『Tea for Two』 #04 *天ヶ瀬あかね編
#04「……何にもしなかったもんね、私」

――#04
その土曜日の午後は、十二月初頭にしては暖かかった。
「と、というわけで、私が……えと、今回のお料理会を仕切る事になりました、月島円です」
円は上ずった声で精一杯の自己紹介をすると、よろしくお願いしますとペコリと頭を下げた。緊張と気恥ずかしさで頬が紅潮しているのを自分でも感じながら、どうしてこんな事になっているのか今更ながらに戸惑っていた。ガンバレ! とシエルの激励が飛ぶが、その声は円の耳には届いていないようだ。
「さ、さて、本日はお日柄もよく、絶好の料理日和となりまして……」
自分で言いながらも「そんな日和はありません……」と円は軽く頭を振る。
円が緊張を隠せない理由。それは貴之の隣に座るポニーテールの少女の存在。居心地が悪そうにソファーに腰掛けているその少女は、円が見慣れていた相馬家のリビングを全くの別空間へと変貌させていた。
――月島円は、相馬貴之の幼馴染だ。
茶色がかったクルっとしたクセ毛。まんまるな大きな目に、鳶色の瞳。これまた丸く幼い顔のライン。丸いづくしの可愛らしい少女だ。
それにも増して、彼女の性格はとても丸い。争い事を好まない優しい彼女は、一乃谷高校でも一部の男子生徒から「いつも隣で笑いかけていて欲しいほっとする女子」として人気を集めている。外見上は決して美人というタイプではない円ではあるが、性格美人である事が彼女の評価をグッと上げている。
しかし、それは内向的な円にとってあまり喜ばしいことではなかった。円にとって他人に優しくすることは自信のなさの現れでもある。争いを好まないのも、負けると分かっている勝負をしたくないからだ。そんな逃げ腰の彼女には、性格美人などという評価はただのプレッシャーにしかならない。
そして今の状況も、円自身の弱腰が招いた結果である。目の前に座るポニーテールの少女をチラチラと見て、どうしてこんな事になってるんだろう? 一体何を話せばいいんだろう? と肩越しで跳ね返るクセ毛を両手で整えながら考える。自分の世界に入り込こんでしまうと知らず知らずに出るその癖が、今の彼女の困惑ぶりを如実に物語っていた。
「……え、えーと、それじゃ詳しい話はシエルちゃんがしてくれるので」
円は慣れない役を押し付けられたことが不服なようで、頬を膨らませてみせた。
「はい、マイク受け取りました! 今日は我が不肖の兄もどき、相馬タカユキ主催のお料理会にようこそおいで下さいました!」
円に代わり立ち上がったシエルは高らかに宣言をする。
「おい! もどきってなんだ、もどきって! あと僕は主催じゃない!」
「うるさい相馬! シエルちゃんの美声が聞こえないだろうが!!!」
騒がしい野郎二人を尻目に、シエルは改めて相馬家のリビングを見渡す。
何とか場の雰囲気についていこうと必死な感じの月島円。
女子会ってこんな感じ!? と、テンションが異様に高い丘村庄治。
なんだかやけくそ気味である、今回のイベント主催者の相馬貴之。
そして、貴之に隣に座るポニーテールの少女。
「いやぁ、みなさんノリが良くて本当に助かるわ」
司会の合間を縫うように貴之を一瞥し、シエルはニヤリと笑う。その表情は小悪魔そのものだ。覚悟はいいか? と言わんばかりのシエルの顔を見て、貴之は頭を抱えた。
果たして隣に座る少女はこの状況に耐えられるだろうか。無理だろうな、と貴之は目を閉じる。彼女との関係を、庄治やシエルに知られてしまった時の狼狽ぶりを思い出し、うん、やっぱり無理だ、と閉じた目にギュっと力を入れる。貴之のきつく握り締められた手は緊張でうっすらと汗ばんでいた。
相変わらず庄治や円とわいわいやりながら笑いこけているシエルだが、その目に笑みはない。貴之に向けられたその真剣な眼差しは、彼の覚悟を見極めようとする意志に満ち満ちていた。
それを感じ取った貴之は思った。覚悟を決めよう。彼はシエルにアイコンタクトを送り、神妙にコクリと頷いた。
シエルは貴之のサインを満足げに受け取ると、コホンと咳ばらいをした。
「さぁて、そろそろ今日の主役さんに一言コメントしてもらいしょう!」
シエルの視線がポニーテールの少女へと向けられる。
「タカユキの未来の花嫁候補、天ヶ瀬あかね先輩! 今の心境はどうでしょうか!?」
前置きもへったくれもない、シエルのストレートな問いに、その少女――天ヶ瀬あかねは口をポカンと開いた。
「イエーイ! 待ってました! あ・か・ね! あ・か・ね!」
「い、いぇ~い……」
庄治と円はパチパチと拍手をしながらシエルの後に続く。
「直球かよ!!? あと丘村、今呼び捨てにしただろう、殴るぞ!」
貴之は庄治を大声で威嚇する一方、やけに低姿勢にシエルに向き直る。
「た、頼むよシエル、もう少し前置きとか考えてくれよ!?」
やなこったと、シエルは貴之の提案を却下すると、あかねへとウインクをした。
だらしなく口を開いて硬直したままのあかねだったが、シエルのウィンクでスイッチが入ったかのように突然立ち上がった。
「え、え、えええええええっっっ!!? な、え!? ちょっと貴之、え、なにこれ、え!?」
そういって貴之へと逃げ道を探すあかねだったが、自慢の彼氏は「すいません」と汗びっしょりで目を閉じている。
「ささ、何か言いたい事はありますかな、天ヶ瀬先輩!」
「あるだろうさ、そりゃあるだろうさ!」
ノリノリのシエルと庄治。若干引き気味の円。そんな様子を細目で眺めながら、これから繰り出される数々の恥ずかしい質問を想像し、貴之は身を硬くした。
「え? ようするに今日の料理会って……、あれ? みんな私達の事を知った上で……ってこと?」
置かれている状況を整理するかのように、あかねは震え声で呟く。シエルと庄治はニコニコと笑いかけ、円は困ったように愛想笑いをし、貴之はごらんの有様である。
プシュー!と沸騰したヤカンが発する効果音をバックにしたかのように、みるみるうちにあかねの顔が真っ赤に変わっていく。
「い、い、い、い、い……」
「おおっ! なんでしょうか、天ヶ瀬先輩?」
シエルがマスコミよろしく、エアマイクをあかねへと向ける。
「言ったらダメでしょ普通ーーーーー!!!!!!」
あかねの絶叫が、午後の閑静な住宅街にこだました。
お料理会の意図を説明し終わるまでそう時間もかからなかったのだが、その間あかねは恥ずかしさの余り声を出す事も出来ず、ずっとうつむいたまま、合わせた膝の上に乗せられた拳をプルプルと震わせていた。そんな仕草は庄治にとって新鮮そのものだった。
「お、おい、相馬! あかねのヤツめちゃ可愛いじゃないか! なにコレ!?」
あかねのそんな様子に、すっかり骨抜きになったかのような庄治は貴之に詰め寄った。
「ドサクサに紛れて、また名前を呼び捨てにしたな……」
なにやら興奮してクネクネする生物を脇に追いやりつつ、貴之は片手でこめかみを押さえながら呟く。
「……どうしてこうなった」
お前のせいだ、とシエルが身も蓋もない返事をする。
「あ、あの、天ヶ瀬さん、大丈夫……?」
円が心配そうにあかねの顔を覗き込もうとするが、今の情けない自分の顔を見られまいとあかねはプイッと顔をそむける。
「あ……」
が、そこには貴之の顔があり、あかねの顔はさらに赤みを増した。しかし諸悪の根源である貴之は、ポンとあかねの肩を叩き力なく言ったのだった。
「僕が言えた義理じゃないけど、頑張れ……」
引きつった笑顔の貴之をあかねは睨みつける。「後で絶対泣かしてやる」と考えてはみたものの、半ベソ状態のあかねこそ、まったくそんなことを言えた状態ではない。
「天ヶ瀬先輩、だ、大丈夫か?」
少々やりすぎたかとシエルが声をかけると、あかねはビシっと背筋を伸ばし、咳払いを一つした。
「……だ、大丈夫です」
顔の赤みはまるで取れていない。額は汗でびっしょりだ。
「おい、マジやべぇよ……二次元キャラみたいな反応だよ……」
庄治が再び盛り上がりはじめたが、貴之は話がややこしくなるのはゴメンだ、と、こんども無視を決め込んだ。
「だから、その、このお料理会は、あたしと貴之の為にある……って事ですね」
「そ、そうだね」
震える声で話すあかねに、円もオドオドと答える。
「だ、大体の事情は飲み込んでもらえたみたいなので、本題に入りますね」
涙目でシエルと円を見るあかねがコクンと頷く。
「お、お二人が満足する味付けを追及して、それを他の人が食たべても美味しいな、ってと思えるような、そんな料理を、えーっと、作りますっ!」
「……はい、よろしくお願いします」
どうにかこの場は収まったようだと貴之は胸を撫で下ろす。勿論あかねの恨めしそうな視線には気付かないふりをした。
シエルが、手をパンパンと叩くと全員の注意を引く。
「はーい、それじゃ班分けを始めるよ。まずは買出し班から。誰でいこっか」
「班分け? 人数わけるの?」
庄治が質問をする。
「う、うん、今は手元に材料がないし、何を作るかを考えながら買い物した方が分かりやすいと思うの。ね、シエルちゃん」
円の説明に、なるほどと頷く庄治。代わりに今度は貴之が質問を投げかける。
「ん? だったら班分けなんて面倒な事しないて、最初から外で落ち合えば良かったんじゃないか?」
「……いやまぁ、さっきの話題を外で出来る程、羞恥心捨てれるならいいんだけどさ」
「すいませんでした」
シエルの呆れた返答に謝る貴之。その脇腹をあかねが軽く肘で小突く。
悪いと手を上げ笑う貴之と、顔を赤らめてチラチラと貴之の様子を伺うあかね。
二人の様子を見ていた円は、自分の心臓の鼓動が早くなり、心の中に何かもやもやとしたものが湧き上がって来るのを感じた。これが嫉妬という感情か、と彼女は思った。
これまで十年以上、貴之の隣は幼馴染で同級生の円が独占していた。しかし今、その場所にはあかねがいる。その場所を違う誰かに奪われる事を、円は覚悟していた。何故なら、彼女にはその場所を勝ち取ろうとする意志がなかったからだ。もしも貴之が、そこに自分がいる事を認めてくれたら……淡い期待を込め、彼女はただ立っていただけ。守る事さえしなかったのだ。
「……何にもしなかったもんね、私」
騒ぎ立てるみんなの様子を見ながら、円はポツリと呟いた。
よし、と小声で気合を入れる。彼女はわざわざセンチな気持ちになる為にここに来たわけではない。シエルの提案をあえて受けたのは、貴之の選んだ女性がどんな人なのか知る為だ。
それにしても不思議だ。こんなにも悩み、嫉妬もしているはずなのに、久しぶりに貴之と同じ時間を過ごす事が出来るというだけで、円はとても楽しい気持ちになっている。
――ああ、私はどれだけこの人の事を好きだったんだろう。
照れ笑いをする貴之の顔を見て、なぜだろう、円は幸せを感じる。本当ならその笑みはずっと自分へと向けていてほしい。でも貴之の幸せそうな顔を見ているだけで、そして貴之をそんな表情にしてしまうあかねの存在に、自分の心も温かくなっていくのを感じるのだ。
私は結構大丈夫なのかもしれない。
そんな事を考えると、自然と笑みが零れた。
さぁ、今日まで堂々巡りしていた時間に終止符を打つ時だ。
円は今、自分の中の貴之との新しい関係をふたたび築きなおすため、はじめの一歩を踏み出す覚悟を決めたのだった。
土曜の夕方近くといえば、スーパーのフードコートは子供でごった返していると相場が決まっている。
戦隊ヒーローの必殺技を叫ぶけたたましい子供の声が頭に響く。その隣で泣き止まぬ赤ん坊をあやす母親を、他人事ながら大変だなと考えながら、庄治は紙コップの中に残っている氷をかじった。できるだけ静かな場所を求めて奥まった席についたものの、あまり効果はなかったようだ。
買い出し班としてやってきた三人、あかね、円、そして庄治は、買い物が一段落したところでこのフードコートへ休憩に来たのだが、買い忘れがあると女子達二人は再び席を立ち、今は庄治が荷物番を任されている。円形テーブルの上、あかねと円の飲みかけのジュースが入った紙コップ二つを、庄治はボーっと眺めていた。
「両手に花……過去最高に輝いている俺、などと考えた事もありました」
あまり女性と話す機会がない庄治にとって、二人の女性に囲まれて買い物に出るなど、初めての経験だった。ワクワクと相馬家を出発した庄治だったが、今は後悔しかない。買い物を終えて帰るまでこの気まずい空気の中に身を置かねばならないのかと思うと、憂鬱で仕方がなかった。
「いやいや、他人から見たら羨ましい状況なんだから、楽しまないとダメだろう!」
なんとか前向きに考える。
天ヶ瀬あかねは凶暴だが相当に可愛い。しかも最近はそんな気の強い部分も鳴りを潜めたせいか、当社比120パーセント増しで可愛く思える。先ほどの恥ずかしがるあかねを思い出し、庄治は鼻の下を伸ばす。これで彼氏がいなければ玉砕覚悟で突撃するのもありかな? などと、あまりリアルの恋愛に興味がない彼でもそう考えてしまうほどの愛らしさだ。
死ね、相馬。
そう考えた。
一方、月島円は地味だがおっとりとした優しい性格で、彼女とまともに話をしたのは今日が始めての庄治も、その信じられない程の癒しキャラぶりにすっかり心を和ませていた。
円は、いつも幼馴染の貴之とその親友である結城和泉と行動を共にしている為、他の生徒とはあまり深い付き合いがない。そのため謎多き少女として意外に隠れファンが多いのだ。円の不可思議な魅力は、僅か数時間の間に庄治もその中の一人になってしまおうか考えた程だった。
むしろ、死ね、相馬。
またもやそんな事を考える。
今、庄治は一乃谷高校の女子の中でも名うての人気者二人を侍らせているのだ。一瞬の輝きではあるが、彼はそんな自分を誇らしく思う。
「ああっ、それなのに、なんで俺こんなに疲れてるんだろう……」
買出し班に抜擢された庄治へのシエルからの極秘指令は、あかねと円を友達にせよということだった。
二人は今まで接点がなかったせいで、お互いに気を遣いすぎ、とても気まずい状況なのだ。互いに気まずいなら、近づかなければいいではないか、と庄治は考えるのだが、どうやらそういう事ではないらしい。全くもって乙女心はよく分からない。庄治は二次元キャラクターやアイドルおっかけの世界へ逃げてしまいたい気分だった。
あかねと円の関係は、ある程度は貴之から聞いている。簡単に言ってしまえば、あかねは今の彼女で、円は昔の彼女候補だったというわけだ。その認識は違うと貴之は否定したが、彼からすればそんな事情は知ったことではない。よくよく考えれば、こんな役割は貴之がやるべきことだ。庄治はあまりといえばあまりの我が身の理不尽さを嘆いた。
『丘村先輩次第ですよ、がんばれ!』
出かけに言われたシエルの言葉に、いつものように親指を立て、任せろと豪快に言い放った己の調子のよさを、庄治は後悔していた。
「ただいま」
あかねがそう言いながら目の前に座り、その後を追うように、待たせてごめんね、と円も腰を下ろす。
「……お目当ての物は買えたか?」
面倒そうに聞く庄治の問いに、あかねがコクリと頷く。その隣で円が無言のままストローでジュースを飲みはじめる。
「ぐっ…………」
これだ。庄治は先ほどまでの重苦しい空気が戻ってきたことに辟易としていた。二人は必要最低限の会話しかしない。それ以外はこうやって黙りこくっているのだ。二人の時には一体どういう会話をしていたのだろうかと想像してみたのだが、庄治の脳ではその答えにはたどり着けそうになかった。
あかねは庄治が話題を振っても、ほとんどが「うん」という言葉で返すのみである。庄治はあかねへと非難の視線を送るのだが、あかねはあかねで、そんな目で見られても困る、とでも言いたげに情けない表情を返すのだった。人は相手の表情だけでも大体の心情を察する事できるものなんだと、庄治は妙なところで感心をした。
仕方がないと、今度はもう片方に視線を移す。円は両手で持った紙コップを見つめてじっとしている。こちらも微妙に挙動がおかしい。あかねの方を見ようと思いつつも見られない、そんな動きだ。庄治がそれに気が付いたのを察すると、円は彼にニコリと弱々しい笑みをむける。
こんな状況にウンザリしていた庄治だったが、このまま何の戦果もなく帰ることは許されない。まだ円の方が取り付く島がありそうだと、問いかけてみることにした。
「……ねぇ、月島さん。相馬とはどのくらいの付き合いなの?」
―― Next #05