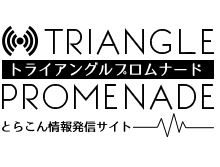『I Will Always Love You.』 #00 *三咲凪編
#00/プロローグ
――#00
「あー、めんどくさいよー」
少しだけクセ毛の髪を乱暴に結んだポニーテールを揺らしながら、少女はげんなりしていた。
耳元ではね返っているこれまたクセ毛の一房を指でピンとつまむと憂鬱そうに見つめる。
授業から開放された周りの生徒達の足取りは軽かったが、ポニーテールの少女の歩みは鉄球がはめられているがごとく重い。
「やっぱやめようよ。私、別に演劇なんか興味ないし」
いつもの彼女なら、すぐさま自宅に戻りお菓子をつまみながらのんびりと再放送の推理ドラマを見ている時間である。だが、彼女の背中を意気揚々と押して歩くショートカットの小柄な少女はそれを許してはくれなかった。
「アンタはホントに中学ん時から全然変らないにゃー。もっと色々触れてみるべきなんだぜ?」
「今、にゃーって……」、
テンションの高い小柄な少女は、昔からこうしてポニーテールの少女の生活サイクルにちょっかいを出していた。
これまで何かに対して本気で取り組んだ事もなく、熱中した趣味に出会ったことがないポニーテールの少女からすれば、この多趣味で行動的な友人の存在はある意味ありがたいものであった。なにしろ放っておかれたら、彼女は引きこもりにでもなってしまいそうな勢いなのだ。とはいうものの、今日のイベントも彼女にはわずらわしいとしか思うことができなかった。
「今日の公演は去年の学祭でめっちゃ話題になった人達が出演するんだよ。木住野もドラマとか好きなら興味あるんじゃないの?」
背中を押す小柄な少女の隣で話を聞いていた眼鏡のスレンダーな男子が口をはさんだ。
「そりゃまぁ、ドラマとか映画とか好きだけど演劇は全然知らないし。なんかホラ、演劇って大げさじゃん? ミュージカルとかも全然興味ないし」
「だーかーらー! そうやって食わず嫌いでいるから柚はダメなんだってばー!」
「うわ、抱きつくなー!! 重い、重いってば咲奈!」
小柄な友人、上林咲奈(かみばやしさな)をおんぶする形になったポニーテールの少女、木住野柚(きしのゆず)は後ろに倒れないよう腰を落として必死の形相で踏ん張る。
それを見ていた眼鏡男子笑いを堪えながら肩を小刻みに震わせている。柚のブルブル震えている膝がツボに入ったらしい。
「すっごい顔してるよ木住野」
「いやいやいや!! 笑ってないでコイツをはがしてよ仲地!!!」
「クククッ! 瑛太に私をひっぺはがす力などあるものか」
「ははは。うん、ないね。だからがんばれよ、木住野」
やる気を微塵も感じさせない眼鏡男子、仲地瑛太(なかじえいた)はいつも通りの二人の様子を眺めながら今日も平和だなあと顔を緩ませた。
新一年生がここ港北大付属一乃谷高校に入学して、そろそろ二週間といったところ。
面倒なオリエンテーションも終わり授業も軌道に乗ったところで、新入生達の関心は部活動へと移行していた。自由な校風で有名なこの一乃谷高校には多種多様なクラブがあるが、その規模は進学校としていかがなものかと思えるほどだ。学園祭に力をいれているせいか、とりわけ文科系の部活動が活発であり、ゲーム同好会なら可愛い方、買い食い倒れクラブや、マジッククラブ、はては栄養ドリンク研究会などいうわけのわからないものも存在する。
そんな中、学祭の華の三大文化部として人気を誇っているのは、軽音部、コスプレ部、そして演劇部だ。
「というわけなんだよ、柚! しかも演劇部には花房先輩って滅茶苦茶かっこいい人がいてさ! やっべーの! マジやっべーんだって!」
「それか。それが目的なのかアンタは」
「上林は去年の学祭遊びにきたっていったもんな」
「ああ、美味しかったなぁ、あのイカ入りタコ焼き……」
「おい、どういうことだ、それ」
中学時代からの仲良し三人組、木住野柚、上林咲奈、仲地瑛太も他の生徒と同じく部活動を見学している真っ最中だ。とはいえ、クラブ廻りに必死になっているのは咲奈ひとりである。咲奈だけが部活動を決めあぐねているのだ。帰宅部一択の柚と、文芸部という地味な部活動を選ぶつもりでいた瑛太は、ここ三日程はこうやって咲奈に連れ回されていた。
そして今日は噂の演劇部の春公演。ほかの部活動の見学とは違い、時間を取られるのは明らかだ。柚は今すぐにでも踵を返して逃げ出したいところであった。
「……てか、さっきから人多くない?」
体育館に向かうに連れ、目に見えて人が増えていく事に柚は眉をひそめた。
「そりゃ、みんな体育館に向かってるからじゃないの?」
なんの捻りもない答えを真顔で返す瑛太に、柚はいつもの事といえその単純さに呆れ返る。
「仲地はもうちょっと会話の裏を読んだほうがいいと思う」
「無理無理、瑛太にそんな高度なテクニック期待するとか、柚ちゃん鬼だなー」
「うん、貶されてる事はわかるよ」
二人の話にすこしばかりシュンとなった瑛太の肩を、咲奈が背伸びをしてよしよしとその頭をなでた。柚は落ち込む瑛太を気にも留めずに、周りを見ながら小声で二人に疑問を口に出した。
「私の言ってるのは、なんで二年生や三年生の先輩達もいるのかってことよ」
「そういや、リボンの色が違うねー」
一乃谷高校では、学年ごとに女子の制服のリボンやネクタイの色がわけられている。新一年のカラーは緑なのだが、まわりの女生徒には赤や青のリボンの人達が結構いる。
「これって一年生の勧誘会みたいなものでしょ? なんで先輩達がこんなに」
「そりゃ、見たいからでしょ?」
瑛太に続き、咲奈もストレートな回答をよこす。
「ぐ、なんかそう言われたらそれしかないだろうけど……。でも、たかが高校生の演劇でしょ?」
「うわぁ、それってヘンケーン。花房先輩は、プロの劇団に入ってる人だよ」
「え? そうなんだ。へぇ、プロかぁ……」
「ん? どったの?」
急にトーンダウンした柚の声に、咲奈は疑問をぶつけた。が、柚はそんな咲奈の声などはまるで耳に入っていないようだった。
身近に存在しなかったプロという言葉の響きに、柚は不思議な感覚を覚えていた。
確かに、学生であると同時にプロであるスポーツ選手やタレント、歌手、俳優等々はあまた存在する。これまで柚はそんな存在を意識したことがなかった。自分には縁のないものだと思っていたと言ってもいい。
だがしかし、同じ学校の中、演劇部にはそんな人物がいるという。こんな身近に自分の知らない世界が広がっている。
世の中に対する期待を持てず、ただ白けた日々を送っていた柚であったが、この時、あきらかにプロという言葉に刺激を受けていた。『何かに惹かれる』という、忘れかけていた感覚が自分の中に湧き上がってくるのを感じて、少しだけ震えた。
「ねえねえ、どうしたの?」
考え込む柚の顔を咲奈が覗き込む。
「ん? んー……。プロってすごいなぁって素直に」
「なになに? いつもの自信満々な柚様はどこへいったのかな?」
「はは、木住野はいつも自分だって出来るっていうものなー」
「失礼な!」
酷い言われようだが、実のところ的を外していなかった。
――私にはなんでもできる。柚には自信があった。
柚は大きな壁にぶつかったことなどない。これまでの人生、柚はなんでも器用にこなしてきた。この辺りでは比較的難関と言われる一乃谷高校への受験でさえそれほど苦労はなかった。そればかりか咲奈の受験勉強を手伝っていたほどである。しかも中学生の時は水泳部のエースときている。
柚にとって怖いものなど存在しなかった。だが、それは酷くつまらないことでもあった。
意外なことに柚は小学生の頃、どんな些細な事にでもチャレンジする好奇心旺盛な少女だった。そして手を出したものは驚くほど上手くこなしていく。こうして何の苦労もなくやり遂げてしまえる経験が増えるごとに、彼女の中にあったはずのヤリガイや達成感を、彼女自身が感じられなくなっていった。
そうして柚の中でいつの間にか世界に対する関心は薄れてしまったのだ。やるべき事だけをやって、あとはテレビドラマの再放送とインターネットという、なんとも味気ない日常を送っていたのだった。
「なるほど。プロか……」
「柚、なんかさっきからおかしくない?」
なんでもないと返事をする柚だったが、その表情が、どんな些細な事に対しても拘っていた十三歳までの彼女のそれになっていることに咲奈は驚いていた。
人混みに流され体育館に入場していく生徒達。
皆この春公演を楽しみにしてきた人達ばかりだ。
一年生の頃からの花房のおっかけファンも居れば、去年の舞台で一乃谷高校演劇部のファンになった人達もいる。そしてそんな噂を聞きつけた新入生達。
様々な期待を持つ人達の中、柚だけは挑戦者として舞台の幕が上がるのを静かに待っていた。
「見極めてやろうじゃん、生で。プロの力がどんなもんなのか」
―― Next #01