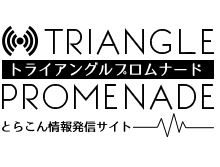『I WILL ALWAYS LOVE YOU.』 #02 *三咲凪編
#02/夕風 :yuukaze
中宮市(なかのみやし)は、嵩鳥市から二駅離れた場所にある少し大きめの地方都市だ。
潮の香りがするその街は、十年程前から地方活性化を旗印に大規模な再開発が進んでいる。その甲斐あってか、中宮の洒落た町並みには若者が溢れ、夜ともなればライトアップされた街路樹や建物が訪れる者の目を楽しませてくれる。ここ数年では観光客も増え、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いである。
しかしいまだ再開発の手が及んでいない駅裏には昔ながらのさびれた街並みが続いている。そんな商店街の中、ひっそりと佇むように、その老舗の手芸用品店はあった。
「案外早く終ったね」
店から出たばかりの赤い詰襟の制服を着た少年は、レシートとつり銭を連れの二人の少女へと手渡した。
「はい、わざわざありがとうございました!」
「本当に助かりました、先輩」
少年と同じく赤いブレザーを身にまとった少女達。
元気いっぱいに頭を下げるのは、大柄なショートボブの少女。
かしこまってお辞儀をするのは、小柄で黒髪ロングヘアの少女。
態度も姿もいつも通り対照的な二人に少年は頬を緩めた。
「これで三咲先輩の衣装もグレードアップですよね! 期待していてくださいよ!」
少年はそうだねと軽く笑うと、ポケットからスマートフォンを取り出し、ディスプレイに表示されたデジタル時計を見た。
「あー、もうこんな時間だったか。それじゃ僕はここまででいいかな?」
「ひょっとして中宮で何かご用でもあったのでしょうか?」
小柄な少女の申し訳なさそうな顔に、少年は両手を激しく横に振って否定した。
「違う違う。用事って程ではないんだけど。……強いていうなら、遊びにきた感じかな?」
「ええ、テスト前にですか!?」
大柄な少女の大きな声に、隣に立つ小柄な少女は、迷惑そうな顔をして両手で耳を押さえている。
「意外! 先輩ってすごい真面目だとばかり思ってました!」
「はは、かいかぶりだったね」
スマートフォンをポケットにしまいながら、少年は少し自虐的に笑った。
そんな彼の言葉を遮ったのは小柄な少女の声だった。
「逆よ、逆。普段から真面目に勉強してるからこそ、先輩はテスト前でも余裕って事」
「おお、なるほど! 頭いいね篠坂!」
どことなくお莫迦な雰囲気をかもし出す大柄な少女が、愛嬌のある笑顔でコクコクと頷く。
「そりゃここにいるメンバーで、柳瀬より頭の悪い子はいないしね」
「ひどっ! 私だってそこそこ勉強できるのに!」
「ぷ、所詮そこそこじゃない」
二人の少女の会話は聞いていて飽きないが、このままでは日が暮れてしまう。さすがにそれは避けたいと少年は仲裁に入った。
「ほらほら、そういうケンカは帰り道でもできるだろう? もうすぐテストが始まるっていうのに後輩を連れまわして遅くまで街を徘徊してるなんて噂、僕は立てられたくないんだから」
「す、すいません! つい柳瀬が面白くって……」
少しだけ困ったような顔付きの少年に、小柄な少女――篠原朱乃(あけの)は深々と頭を下げた。
「え、私には謝らない感じ……?」
朱乃に散々にバカにされていた大柄な少女――柳瀬実夏(みか)は、ポカンと口を開ける。どうやら朱乃の中では、少年と実夏の間には超えられない壁が存在するようである。
「えーと? 篠原さん……えー、と、あー」
うまく言葉を見つけることができないまま口をモゴモゴとさせる実夏。
少年はそんな実夏を少々気の毒だとは思ったが、そこまで面倒を見る気はく、彼女の様子を笑顔で眺めていた。
「ま、そんなわけだからこの続きは帰りの道中でどうぞ。さっさと帰るんだぞ?」
「り、了解であります!」
納得はいかないままだが、なんとか立ち直った実夏がビシっと敬礼を決める。そんな彼女の脇を小突きながら朱乃も再び頭を下げた。
「はい、それでは失礼します。先輩もあまり遅くならないようにしてくださいね」
少年も軽く手を上げそれにこたえる。実夏はよほど元気が有り余っているのか、楽しそうに手をふりながら後ろ歩きで遠ざかっていく。隣を歩く朱乃が危ないからよせと目を吊り上げて注意をしているが、彼女達の仲の良さを知っている少年からすればこれもまた見慣れた光景であった。
「さて……」
駅へと向かう二人の姿が小さくなるまで見届けた少年は、反対側を振り返る。
古臭い小さなビルが立ち並ぶ色褪せた光景。彼はそんな薄暗い通りへと踏み出した。
時刻は十八時を回っていたが、まだ日暮れには早い。そんな六月の出来事だった。
一乃谷高校はテストの一週間前から部活動が禁止される。
普段はお気楽な校風で生徒達も忘れがちだが、進学校としては当然の配慮といえよう。
テスト期間も含めて、一週間以上も練習できないのは柚には歯がゆい事であった。柚のイラつきはピークに達しつつあったが、そのイラつきは自分に向けられたものではない。
かねてから柚は、自分以外の演劇部員は演劇部員として圧倒的に練習時間が足りていないと感じていた。ただでさえ足りていない彼らの練習時間がさらに奪われてしまうのだ。とは言うものの、さすがに校則に逆らうわけにもいかない。柚のイライラは募るばかりであった。
「で、柚の立ち位置としてはどうなのよ」
「どうもこうも。私はもう役を待つだけなんだもん」
放課後の図書館。友人である上林咲奈のテスト勉強に付き合っていた柚は、そんな疑問に頬杖をついたまま興味なさげに返事をした。
「ふーん……相変わらず尖ってんねぇ、柚は」
勉強をしながら雑談をもちかける咲奈。
ノートに書き綴られていく数式が本当に頭にインプットされているのか疑わしく思える。こんなことで咲奈は無事にテストを乗り切れるのかと、柚は少しだけ心配になった。しかし彼女が教えてほしいとでも言い出さない限り、柚は手助けをする気はなかった。
「……もうちょっと誰かに対して世話を焼くってことをさ、してもいいんじゃなかなぁ」
ペンを走らせながら咲奈は言う。今まさに考えていたこと見透かしてきたような友人の言葉に柚は動揺した。
「な、なんでよ」
「なんでって……、そりゃ持つ者が持たざる者へ手を差し延べるのは当然なんじゃないかな?」
その言葉は柚の癇に障った。
まるで本当に怠惰なのはお前自身ではないのかと言われたように感じたのだ。
「だから、それがなんでって聞いてるの」
ストレートに喜怒哀楽が表情に出やすい柚は、わかりやすく不機嫌な顔付きになっていた。それに気がついた咲奈は、やれやれと呟きペンを置く。
「まぁ、怒んなさんな、ホレ」
友人の差し出したスティック菓子の箱からは、チョコレートの香りがした。
木住野柚のご機嫌をとるなら甘いお菓子。彼女の友人達の中では、なかば常識であった。
「……いただきます」
甘い食べ物にはすぐ屈服してしまう自分が少しだけ恨めしい。そんなことを思いながら柚はチョコレートスティックを口に咥えた。
「なんていうのかなぁ、効率? 柚のやってる事って結局いつも効率悪いと思うんよね」
「は? 私ほど効率好きな人間はいないと思うけど」
明らかに的外れと思われる咲奈のアドバイスに、せっかくチョコレートで収まりかけていた怒りが再燃する。
「いやいや、そうじゃなくてさ。あんた自身の効率はいいよ。今だってテスト勉強しなくていいってのは、普段から勉強してるわけだからっしょ」
「そうだよ。咲奈が悪い。なんで私が勉強を手伝わないといけないのよ」
「わ、私の事はいいっての。だーからさー、そうじゃなくてチームプレイの話」
論点がズレてしまいそうだったので、咲奈は話題の軌道修正をしながら再びスティックをかじる。
「柚は自分の事は自分でやれって考えでしょ?」
「当たり前じゃん」
柚の同意を得られたことで咲奈はウンと頷き、両手を頭の後ろに回して背伸びをする。
「でも、チームプレイでそれやってると、自分の脚を引っ張るよ」
「どゆこと?」
「うー、やっぱ勉強は肩こるにゃー」
これ以上言うことはないよ、とでも言わんばかりに咲奈は首筋のマッサージを始めた。
「ちょっと待ってよ、話途中でしょ!」
思わず大きな声を出してしまった事で、二つ離れた席で勉強をしていた眼鏡男子がギロリと彼女を睨んできた。
「……あ、ごめんなさい」
柚は軽く頭を下げ小声で謝る。
そんな彼女をクスクスと笑う咲奈を、柚は少しだけ憎らしいと思った。
人は何かに挑む時は一人だ。
いや一人で挑まなければならない。
もし挑戦に失敗した時、誰かの手を借りていたとしたら、それをその人のせいにしてしまうかもしれない。
だから柚は何事にも一人で挑む。自分のミスは自分自身で全て負うべきなのだ。
その痛みも、その屈辱も、その悲しみも。
他人を巻き込むべきものではないのだ。
だから柚は、他人に手を貸さない。
自分も他人から手を借りない。
そう決めていた。
「ちぇ……」
ファーストフードの大きな窓に面したカウンターテーブル、柚はスマートフォンで今日の運勢を調べていた。
すでに今日は残り六時間。
今更、終わりゆく日の運勢を調べたところでなんの意味があるのかというと、彼女流の少し捻くれた憂さ晴らしであった。
「今日は幸運な日でーす、なんて出てくれればよかったのに……」
自分の人生が運勢サイトごとき決められているわけがないと信じ、占いサイトへアクセスして調べてみた運勢は、散々だった今日の出来事をことごとく言い当てていた。
星座占いで下から数えて三番目。ラッキーアイテムは青い飛行機。
「ブルーインパルスかよ」
丁寧なツッコミを入れつつも。柚はしかめっ面で画面をスクロールさせていく。
すると――『友人からキツい一言を頂く。普段の行いに何か間違いがあったのだろうか』。
「ムカツク!」
あまりの的確さに、柚はスマートフォンを乱暴にテーブルへ置いた。
なんとも冴えない一日であった。いや、冴えていないのはここ一ヵ月ほどか、と溜息をついた。
テーブルに突っ伏し少し顔を起こす。窓の外には夕焼けの空が広がっていた。
放課後、ずっと咲菜のテスト勉強に付き合わされたというのに、まだいつもの帰宅時間にすらなっていない。
いつもなら部室で練習をしている時間。
暇をもてあまして駅前にやってきた柚だったが、もとより大した目的があったわけでもない。あっという間に行き詰ってしまった。一応の収穫と言えば、何気なく立ち寄った本屋で、集めていた小説の新刊が発売されているのを見つけた事ぐらいであった。
柚にとって部活動のない日は鬼門である。家に帰ってもやる事がないのだ。再放送のドラマを見なくなった事もあり、夕食までの時間が酷く長いものに感じられる。だからこうして、あてもなく街へ繰り出してみたわけだが。
仕方なく買ったばかりの新刊のページをめくってみる。これで一時間は潰せるはずだと思っていたが、内容は全く頭に入ってはこなかった。
「つまんないなぁ……」
柚は目の前に置かれたスマートフォンを指でつつきながら不満を漏らす。もちろんそんな事をしてもニ年来の相棒は何も答えてなどくれないが。
この暇な時間を打ち消してくれるようなメールが届きはしないだろうか。テスト期間中だし、ありえないと思いながらも少しだけ期待をしてみるが、やはり相棒は終始無言のままである。
「うー、つまんないよぉ」
カウンターに備え付けられた少し高めの椅子で、足をバタバタと揺らす。すると、それに呼応したかのようにテーブルに置いたスマートフォンがブルブルと大きく震え、飲みかけのジュースが入ったカップを揺らした。
「うわ、びっくりした」
柚は急いでケータイを持つと、着信表示を見ることもなく通話ボタンを押した。
少しささくれ立った心を癒してくれる出来事を望んでいた柚にとって、それこそ相手は誰でもよかった。さて一体誰が受話器の向こう側で待つのだろうか? そんなワクワクを抑えきれないまま柚はケータイを耳へとあてた。
「もしもーし!」
『うわ、びっくりした。柚ちゃん元気だね』
「……ん?」
確かに聞き覚えがある声だった。
が、それこそこのタイミングで連絡がくることなどありえない人物の声だった。柚は慌ててスマートフォンを耳から離し表示画面を確認したが、やはりそれは紛れもなく彼女の憧れの人物であった。
「うわ、マジで!?」
思わず呟くと、再び受話器に向かって柚は歓喜の声をあげた。
「ど、どうしたんですが三咲先輩っ!」
『え、ううん、えと、何か慌ててたみたいだけど、お取り込み中だったかな?』
「いえいえいえいえいえ、そんな事は決して!」
あまりの柚のテンションに若干引いてしまった感のある電話の主は、彼女の憧れの君、三咲凪であった。
演劇部の連絡網として登録してあった凪のナンバーは、部活動の連絡手段以外に使われたことはない。そして部活動は休止中であり、現在その機能は完全にストップしている。にも関わらず、凪から かかってきた電話。つまりこれは完全なるプライベート。
柚にとってはまさに青天の霹靂であった。
「そ、それで三咲先輩、どうしたんですか?」
凪は高鳴る鼓動を抑えると、誰も見ていないファストフード店の傍らで背筋をピンと伸ばす。
『うん、今柚ちゃん暇かなって? なんて思っ』
「暇です!!!」
『ひゃっ!』
凪の言葉が終らないうちに、柚は力いっぱいに答えていた。
――ああ、なんという運命。
二人は互いに暇同士。そしてそれを埋める相手に私を選んでくれただなんて。
柚はそんなことを考えながら受話器の向こうで話す凪の言葉を待つ。
そういえば、いつぞや柚は文芸部の副部長である守山珠希からこう言われていた。気になる人物はいないか、と。
それを直感的に恋の相手だと思った柚は、そんな人物はいないと否定した。珠希はその人物は凪ではないのかと言うのだが、その時の柚にはピンとこない話だった。
『も、もう、柚ちゃんびっくりさせないでよ』
「……そうか、こういう事か」
『ん? 何がこういう事なの?』
「え、あれ、私、今言葉に……。い、いえ、なんでもないです、あははっ」
これでは完全に恋する乙女ではないか。柚は少しばかり自分自身に不安を覚えた。が、
『それじゃ、ちょっと今から会えないかな……?』
「喜んで!!」
不安は、凪の誘いであっという間に吹き飛んでいった。
―― Next #03