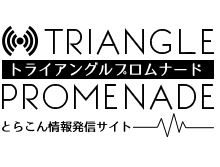『Tea for Two』 #03 *天ヶ瀬あかね編
#03「ホントにそう思ってんなら、私の前でそういう辛気臭い顔するのやめろ」

――#03
残り火のような残照が、あかねが去った住宅街の道をぼんやりと照らしている。
彼女を追いかけることはできなかった。その資格が自分にはなかった。
『……ありがとう、嘘でも美味しいって言ってくれて』
聞かれていた。
本当に迂闊だった。
庄治との食堂での会話は、あかねに聞かれていたのだ。
何かの事情で補習が休止する事はよくある。その可能性をまったく気に留めていなかった自分の軽率さに歯噛みをする。そもそも学校内で、食堂ほど秘密の会話に不向きな場所もない。これは自分の責任だ。
「……嘘じゃないんだ」
――誰に言うでもなく、そんな言葉が貴之の口を衝く。
確かに今のあかねの料理は、客観的に見ても美味しいと言えるものではない。しかし貴之があかねの弁当を美味しいと思う気持ちは、誰になんと言われようがまぎれもない彼の心の真実だ。あかねの料理を美味しいと言う。それは貴之にとって嘘であって嘘ではない。もし敢えて嘘と呼ぶのであれば、『あかねを幸せにするための嘘』なのだ。
しかし気付かれてしまった今、嘘は誰かを幸せにする力を失った。残されたのは嘘をついた、という事実だけだ。
言い訳の一つもすることも出来ずあかねと別れた貴之は、今の彼女に対してどう向き合うのが二人にとって正しい事なのか、すっかりわからなくなっていた。
相反する心の真実と、どうしようもない事実との板ばさみになり、貴之はもう一歩も動けなかった。
その足はあかねの家にも、自分の家にも向かおうとせず、貴之は動かなくなってしまった自分の足元を、ただ見つめている。
「どうしたいんだよ、僕は……」
自らの意志がその歩みを止めている事は、彼にはわかっている。
今すぐあかねの傍へと走っても、彼女に向かいあう勇気は今の貴之にはない。しかし家に戻ったところで、いずれあかねに連絡しなければならない事もわかっている。
答えは、まるで見つかっていない。
だから貴之にとって、ここで独り立ち止まる事だけが唯一の逃げ場となっていたのだ。
「嘘じゃないんだ、本当に……」
再びポツリと呟いたその時、ポン、と軽い衝撃を貴之は背中に感じた。
「こんなところで、何ボーっとつっ立ってんの、タカユキ」
貴之はギクリと振り返る。
「な、なんだ、シエルか。どうした?」
そこには見知った同居人、幼馴染の雨宮シエルが立っていた。
フランス人と日本人とのハーフである彼女は、その青い瞳で貴之を不思議そうに見つめている。長い金髪のツインテールが、田舎の住宅街という風景に全く噛み合っていないのだが、そんな見慣れてしまった非日常的な日常は、彼の心を少しだけ和らげた。
「いや、どうしたって……聞いてるのは私なんだけどな」
シエルは怪訝そうな表情で、黙り続ける貴之を見つめる。
「まぁ、なんでもいいや。はい、これ持って、もう重くてヤダ」
「おっと……」
一つ歳下とは思えない横暴な振る舞いで、両手に持った買い物用のエコバッグを貴之に押し付ける。身軽になったシエルは、背伸びをしながら貴之の横を軽い足取りで通り過ぎていく。
日の落ちた住宅街。暗闇の中、シエルの着るオレンジ色のジャージは貴之の行く手を照らす道標であるかのようだ。
「本当にタイミングのいいヤツだよ、お前は」
幾度となくシエルに助けられた過去を振り返り、貴之はほんの少し感傷に浸った。
さて、それにしてもこのエコバッグは中々の重さだぞ? と袋の中をのぞくと、各種料理の材料がドッサリ、そして特売の鶏肉も入っていた。「今晩は唐揚げか」そんな事を考えながら、シエルの後を貴之は歩き出す。ここでシエルに会わなければ、貴之は街を彷徨っていただろう。外食するだけの手持ちもなかったから、それを考えると無事夕飯にありつける事自体は歓迎すべきだ。一方あかねの事を思いながらも、夕飯くらいで安心している自分を貴之は嘲笑もした。
――家に着いたらあかねにメールしよう、そして謝ろう。
貴之はエコバッグの取っ手をグっと握り締めた。
相馬家の家族構成は、父の守。母の由美。そして息子である貴之の三人だ。
ただし、父の守は五年前から海外で単身赴任中である。よって現在の相馬家には二人しかいない。はずなのだが、相馬家の食卓にはいつもシエルが加わっている。
相馬家の隣に住むシエルは、以前から由美の元に預けられることが多かった。シエルの家は母子家庭だ。
シエルの両親はすでに離婚している。理由こそ違うが夫の不在という共通の境遇のせいか、由美とシエルの母親である雨宮孝子はとても仲がいい。
女手一つでシエルを育ててきた孝子は、仕事で家を空けることが多かった。その間一人ぼっちで留守番をするシエルを心配した由美が預かることを申し出たのだ。
それが習慣となり、今や相馬家にシエルがいるのは当たり前。いつの間にか食事の支度を引き受けるようになった彼女は、相馬家の食卓の主導権をすっかり握っている。
雨宮シエル織姫。フランス人の父が名付けた、なんとも仰々しい彼女のフルネームだ。シエルとはフランス語で空を意味する。彼女の名はまさに空のお姫様というわけだ。しかしその名前を極端に嫌う彼女は、本来のファーストネームである織姫を名乗る事はない。
さらに皮肉な事に母の旧姓は雨宮である。雨降る空の織姫などと、冗談にも程がある。だから彼女は自分の事をシエルとしか呼ばせない。間違ってでも姫などと呼んでいけない。それで血の雨が降らない保証などどこにもない。
周りから見れば羨望の的であるつややかな金髪と青い目、そして美しい名前は、シエルにとって忌むべき存在でしかなかった。そのため両親の離婚後の彼女は、周囲に馴染めずにいた。彼女は異端として見られる事を最も嫌っていた。どこにでもいる一般的な日本の女の子でありたいと願い、そう扱って欲しかったのだ。
そんなシエルの気持ちを理解し、一番初めに認めてくれたのが幼馴染の貴之だった。以来二人の関係は十年の月日を経て、実の兄妹といってもほどの関係になっていた。
「やっぱ、唐揚げは家で揚げるのが一番だわ」
貴之の母、相馬由美は後片付けの済んだテーブルでくつろいでいた。
「ちょっと多めに作っておいたから、明日の朝にでも食べて下さいね」
いつも悪いわね、と由美はカウンターごしに洗い物をするシエルに声をかける。
夕飯は貴之の予想通り唐揚げだった。シエルの作る料理は本当に美味しい。この技術をシエルに叩き込んだもう一人の幼馴染に、貴之はいつも感謝している。
それに引き換え、この母親は相変わらずだ。ボサボサの髪の毛を無造作に肩口で結び、トレーナーにどてら。見るからに引きこもりである。これでは、相馬家がシエルを預かっているのではなく、シエルのおかげで相馬家が成り立っていると言うほうがふさわしい。
ご機嫌な口調で由美がシエルに何やら色々と話しかけているのを傍目に、向かいに座る貴之はスマートフォンでメールを打ち始めていた。
『あかねの料理が美味しいって嘘をついていてゴメン』
なんだこの文章は。自分の文才のなさに腹を立て、貴之は全文を消去する。
あかねの料理は確かに不味い。不味いというか身体に悪い気すらする。今晩食べたシエルの料理とは雲泥の差だ。貴之は、自分が今までどれだけ恵まれていたか自覚していなかったことを、世の男子に謝りたい気分になっていた。
それにしても謝罪のメール一つまともに打てないとはどういう事か。考えようとしても、言葉は何一つとして出てこなかった。
貴之はお茶をすすると頭の中を整理する。
「……うん、美味い」
シエルの淹れてくれたいつもの味が、貴之の思考をリセットしてくれた。
そもそも今はあかねの料理についてはどうでもいいのだ。あかねに対して”嘘をついていた”事が問題であって、それ以外は関係がない。そう考える貴之だったが、相変わらずスマートフォンの画面をタッチする指は止まったままだ。
「タカユキ、さっきから何のゲームやってんの? 喜怒哀楽が激しすぎるぞ」
カウンターからシエルが質問する。
「ああ、別に今はなんもやってないぞ。単純にネット見てただけ」
「なーんだ。なんか面白いゲームあったら教えて。あ、ガラケーでも出来るのでお願い」
了解と答えると、貴之は再びスマートフォンを片手にメールを打つ。
『今日はゴメン。食堂での事はあかねに直接会って話したいです』
文章では真意を伝える自信がない貴之は、結局少しばかり躊躇いながら、用件だけのそんなメールを送り、スマートフォンをそっと机の上に置いた。
「貴之くん、恋の悩みかな~?」
「なっ!」
由美の言葉に、不意をつかれた貴之は思わず声をあげる。
「うわぁ、貴之がこんなに焦るとは。これは重症だ。ねぇ、シエルちゃん」
カウンターの向こうからシエルは、「そうなんですよねー」と軽く答える。
洗い物が済んだ台所の水滴を馴れた手つきで拭き取りながら、シエルがひょいっとカウンターから顔を出す。
「タカユキ、かっこわるー」
気づかれていないつもりででもいたのかと、呆れ顔でそう言うと顔を引っ込めるシエル。
「アハハー! 全くもってその通り! わが息子ながら情けない! こんなエリートハーレム環境で育ってその程度とはね!」
大笑いを始める由美を見ながら口をぱくつかせる貴之。
「えー……」
バレバレだった。どうやら貴之の隠し事は隠し事になっていなかったらしい。
「何? 今付き合ってる子とケンカでもしたの?」
目を輝かせ、由美が貴之にズイっと迫る。
「そういう事、普通聞くかぁ?」
貴之は母のあまりに無神経な態度に腹を立て椅子を蹴って立とうとした。そんな貴之に、洗い物を終えて由美の隣へと座ったシエルが挑発的に言い放つ。
「天ヶ瀬先輩とケンカするほど甲斐性ないですよ、タカユキは」
こんな事を言われて逃げるわけにはいかないではないかと、貴之は浮かした腰を再び椅子へと落とす。
「なぁに、アンタどういう彼女と付き合ってるわけよ」
シエルの意味深な言葉に反応した由美が、いよいよ調子に乗ってきた。
「天ヶ瀬あかね先輩。二年生ではちょっと有名な優等生で、正直タカユキには勿体無いぐらいの美人さん」
シエルがそう答える。
「マジで? またそんなご大層な子が、なんでアンタみたいなうだつの上がらない子を選んだのよ?」
自分の子供のランクをそこまで下げる由美にはプライドがないのかと貴之は呆れた。
「なんででしょうね。私にもそれはわかんないですけど」
シエルの言葉にトゲがあるのは気のせいではないだろう。彼女の怒りはもっともだと貴之は思う。
他人ではあるが家族に等しい存在であり、隠し事など今までなかったからだ。
ジト目でこちらを見つめるシエルに、貴之は申し訳ない気持ちになる。
「シエルちゃんにも相談しないとはますます重症ね」
由美がニヤけた顔で席を立つ。
「お、おい、この状況で放置かよ!!」
チャオ! と一言だけ投げかけると、由美はリビングから自室へと戻っていた。
なんてやつだ……そう呟く貴之に、シエルは「逃げんな」と釘を刺した。
仕方なく貴之はテーブルを挟んでシエルと向かい合う。今日はこのシチュエーションが多すぎだろうと悪態をつきたくなった貴之だが、これ以上何か口走ったら、シエルの雷が落ちるのは目に見えていたので、その言葉をグッと飲み込んだ。
「……で、なんでそんなに自分を責めてんの?」
シエルの第一声は、貴之の心を容赦なく抉った。
「それは……言えない」
煮え切らない返事を聞くや否や、シエルは机をバンと叩いて立ち上がり、貴之を怒鳴りつけた。
「言えないなら、もっとシャッキリせんかー!!!」
「……」
「タカユキは、いっぱいいっぱい大事なもんを捨てて、それでも天ヶ瀬先輩を選んだんでしょ!」
「……そうだな」
「なのに、今のタカユキは捨てられたものの悲しみを忘れてるんじゃないの!? 何? 自分だけが大変な目に遭ってるとか思ってるんじゃないでしょうね!!!」
「そんな事はねぇよ!!!」
シエルの言葉をさえぎるように、貴之も声を荒げる。
「……ホントにそう思ってんなら、私の前でそういう辛気臭い顔するのやめろ」
そういうとシエルはそのまま台所へと姿を消した。
自分の不甲斐なさに胃の中のものが逆流しそうになる。何も言い返せない貴之は、拳を握り締めた。
「ごめん……」
そう言うのが精一杯だった。台所からは、別に謝って欲しいわけじゃない、と、シエルの声が聞こえた。
貴之はテーブルに肘をつき、組んだ両手に額を乗せた。
情けない……。そう嘆く貴之の目に涙が滲む。
自分の傲慢があかねを傷付け、自分の身勝手さがシエル達を苦しめている。
「ほれ」
「冷たっ!!!」
不意に頬に押し付けられた、ガンガンに冷えた缶コーヒー。
「こんだけ冷えてると、もはや痛いな……。由美さん一回冷凍庫に入れてんじゃないか?」
そんな事を言いながら、シエルは缶コーヒーから手を離す。
片手で受け取った貴之は、じっと缶を見つめる。先ほど滲んだ涙は、どうやらこの缶コーヒーの水滴に紛れてしまったようだ。
するとシエルが背中から貴之を抱きしめるかのように覆いかぶさった。
「え……!?」
「いいから、黙って聞け」
シエルはそのまま貴之の頭に頬を乗せた。やわらかな金色の髪が貴之の顔にふれる。すこしだけ、くすぐったい。
「別に悩むのはいい。私は恋愛した事ないからよくわかんないけど、恋で悩むのは悪い事じゃないのはよく知ってる」
それは貴之が聞いた事もないシエルの声。
貴之の悲しみを包みこむ慈愛に満ちあふれた優しい声。
そして、シエル自身の悲しみ、寂しさもにじみだした声。
シエルも、恋とは違うかもしれないがタカユキが好きだ。
時には頼れる兄のような。
時には手間のかかる弟のような。
時には遊び相手で悪友のような。
時には双子の片割れのような。
そんな大切なタカユキが選んだ女性は、シエルが全く知らない人だった。それが悔しくないわけがない。
ならばせめて、自分の大切な人には幸せな顔でいて欲しい。身勝手かもしれない、けれど、そう考えるのは悪い事ではないはずだ。
あかねと付き合い出したタカユキは、時折とても悲しい顔をする。シエルはその顔が大嫌いだ。タカユキは幸せになる義務がある。それが自分へ対する、タカユキなりの礼儀だ。シエルはそんな事を考える。
「タカユキは天ケ瀬先輩を選んだ事で、壊しちゃったんだよ。選ばれなかった人が恋で悩む楽しさを、壊しちゃったんだよ」

その中に自分自身が入っていない事にシエルは少しさみしさを感じた。血は繋がってなくても、やはりシエルにとって貴之は兄なのだ。だから選ばれなかった人たちの中に自分を入れることすら、おこがましい。そう感じてしまう事がさみしかったのだ。
貴之にもそんなシエルのやりきれない気持ちが伝わったのだろう。肩から回された彼女の手を掴むと、済まないと答えた。
「そうやって得た幸せは、そんな顔で毎日を暮らす為だったわけ? じゃ、奪われたその想いはどこに行っちゃうわけ?」
「……返す言葉がないな」
「タカユキが今どんな悩みを持ってるのか私にはわかんないよ。でもさ、悩みを隠して笑う事ができなくなったら、私を……私達を頼ってよ」
貴之は、あかねとの事は自分一人で解決すべきだと思っていた。
だが、それが傲慢であった事に気付いた。いや、気付いていたのだ。選ばなかった相手からの優しさを恐れていたのだ。
本当に必要なのは、あかねの笑顔を守る事で”相馬貴之が幸せであること”を証明することだ。
選ばなかった人達の幸せを願えばこそ、貴之は自分の幸せを勝ち取らねばならない。
「後ろめたい、そういう気持ちがあるのは確かだし、今更都合のいいことかもしれないけど……」
そこで一旦言葉を区切ると、貴之は「助けてくれ」とシエルを頼った。
「遅いんだよ、バカユキ」
シエルは貴之から離れると、こっち見るなと言いながらゴシゴシと目をこすった。
――そうだ。一人で背負い込む事はないんだ。
リビングのソファに場所を移し、シエルにいきさつを語り終えた貴之は、庄治に話した時以上にホっとしていた。
すまん、丘村。お前とシエルじゃやはり信頼度が違いすぎる。そんな失礼な事を考えながら貴之は、シエルの言葉を待つ。
だが彼女は、「僕には想像もできないような案を出してくれるかもしれない」という期待感をぶち壊すように口を開いた。
「はぁぁぁぁぁぁ……タカユキも天ヶ瀬先輩もバカじゃないの……」
「……」
現実は夢のような妄想からはほど遠いものだ。
「そもそも結婚前提って何? タカユキ、そこまでお子ちゃまだったわけ?」
「ぐぬぬっ」
泣きそうな思いをしてまで、告白でもするかのように励ましの言葉をかけたのに、それがいかにも滑稽なものになってしまったことを思い知り、シエルは神を呪った。確かにシエルが聞いても、あかねと凪の過去は厄介なものだった。そこから生まれるトラウマが、いかに苦しいかは想像もつかない。だが今、貴之達が直面しているのは、どうとでも解決できる問題だ。
何故こんなこじれているかはわかりきっていた。
「結局、タカユキは天ヶ瀬先輩と結婚を前提につきあってるのが恥ずかしくて、他人に悩みが言えないって事だよね」
「ぐがっ!!」
「で、天ヶ瀬先輩に、気を遣いすぎの鬱陶しい男だと思われるのがイヤだと」
「ひええええええ!!」
やめてくれと、懇願する貴之。
これでは私は道化だよ、とシエルは落胆するが、すぐさま貴之に提案する。
「アドバイスなんて回りくどい事してるのがいけないの! 直接だ、直接教え込め!!」
「え、どういう……」
呆気に取られる貴之の前で、シエルはケータイを取り出すとすぐさま誰かにコールをする。
「あ、もしもし。円ちゃん今週の土曜日ヒマ? ……うん、そう。ちょっと付き合ってほしいことあってさ」
明日学校で詳しく話す、そう言い終わると、シエルはパタンとケータイを閉じた。
もう間違いはない。シエルはここニヶ月引きずってきたツケをここで払えと言っているのだ。
「ふふふ、これで逃げられないぞ、タカユキ」
ざまぁみろといった表情で笑うシエルを見て、軽い眩暈に襲われながら貴之はソファに倒れこんだ。
勝ち誇った顔で、シエルは台所へお茶を片付けに席を立つ。
ソファーで仰向けに寝転がる貴之の目に、壁掛け時計が目に入る。時刻は二十一時を指していた。
「メール送ってから、もう二時間か……」
貴之はスマートフォンをポケットから出すと、もう一度メールを打った。
今度はさっきのように時間をかける事はなかった。シエルの強引とも言える後押しが効いたのだろう。
幸せになるためには、二人だけの力ではダメなんだ。
そんな、当然とも言える事さえ見失っていた貴之は、いかに自分が罪悪感を背負っていたのかを実感していた。
『もう一度謝る、ごめんなさい。もっとちゃんと謝罪もしたいけど、提案もあるんだ。悪い話じゃない。明日話す』
メールを打ち終わり。送信ボタンをタッチする。送信を確認すると、貴之は椅子に座りなおした。
これでいい、と、貴之はソファの背もたれに首を乗せ天井を見る。
ふいにその顔に影が落ちる。貴之の瞳にシエルの顔が逆さまに映っていた。
「ちょっとマシな顔に戻ったじゃん」
「まぁな」
二人は互いに憑き物が落ちたような顔を見合わせ、久しぶりに、ニシシッと笑いあった。
―― Next #04