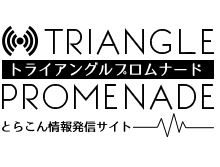『Zero The White Christmas』#03/finale*相馬貴之編
#03/December.24 Part.2
――12/24*19:49
「あの、別に奢ってもらわなくても……」
「介抱してくれた礼だから。なに遠慮してるんだよ、らしくもない」
「で、でもあんなのは当然ですし」
「……つってもファミレスだし。なんなんだよ、いつもだったら大喜びするくせに」
「そ、それに、イブの夜を、その、私と過ごすなんて」
「なに言ってるんだよ? 去年も一昨年も一緒だったじゃないか」
「え!? あ、ああ、そうですね! 私とタカユキさんの関係ですもんね!」
「あ、ああ。 ん? 関係? ……っていうか、なんで今日はさん付けなんだ?」
「そ、そりゃまぁ、年上ですし……」
「今更だなぁオイ。何年前から僕の事呼捨てしてんのかわかってんのか?」
「そ、そんなに前から」
イブに男女二人がファミレスで食事をする姿というのは、本人達だけでなく見ている方も切なくなる。
隣の席に座る男子グループからも、せめてもう少しマシな所に連れて行ってやれよという哀れみの視線を感じる。
とはいうものの。
「……だって相手がコイツだしなぁ」
軽く食事を終え、今はこうして食後のティータイム。
普段とはまるで違う彼女の小食っぷりに少し驚いた。
小動物のような動きでガムシロップをグラスに流し込む目の前の少女。
夢から覚めても、ここも夢。まさしく無限ループにはまってしまったかのような感覚に貴之は囚われていた。
「ま、またそうやって人の顔を凝視してますね……」
アイスティーをストローでちびちびと飲む彼女は、貴之の視線が気になって仕方がないらしい。
「うん、なんかシエルは、いつまでそのへんてこりんな演技をするのかなぁって」
「へ、変ですか? あれ、私、どこか変でしょうか!」
「あー……」
どこが変かと問われれば、全てが変だとしか言いようがない。だがそんな答えでは彼女は納得しないであろう。何せ具体的な要素が皆無なのだから
そんなわけで貴之は、シエルのおかしな行動や言葉使いを脳内でリスト化しようと試みた。
「…………」
途中で考える事がめんどうになってしまった。
何せ彼女から貰った解熱剤によりかなり回復したものの、まだ本調子には程遠いのだから仕方あるまい。
「だから、そうやって考えながら完全に停止状態になるのやめてくださいよ!」
「うん、まぁ全部が変」
「全部!」
結局、貴之の答えは最初に導き出された、もっともシンプルな答えに回帰した。
「おかしいなぁ、そんなに変なのかなぁ……」
彼女は溜息をつき、グラスを机の上にそっと置いた。
「そう、それ。普段ならもっと適当だよな」
「はい?」
彼女は普通に振る舞っているつもりなのに、それを変だと言われることに戸惑っていた。
「それあれだろ。今日はおしとやか路線、とか狙ってるんだろ?」
「ね、狙ってとは」
「んじゃ、そういう感じがシエルの元々の理想なのか?」
いまいち貴之の言葉に納得がいかないのか、苦い顔をする彼女。
どうやら今度は彼女が長考に入ったらしい。貴之は自分の事は棚に上げ、仕方がない、待ってやるかと飲みかけのエスプレッソを口に運んだ。
「すいません、タカユキさん」
「だから、さん付けやめろって、気持ち悪い!」
「今日だけなんだから、それぐらいは我慢してください!」
確かに今まで見たこともないくらいしとやかな今日の彼女だが、このようにすぐに口論になるあたりはいつも通りだと、貴之は思った。
「まぁ、いいよ。なんだよ」
「普段、私はそんなにも女性らしくありませんか?」
真剣な眼差し。
普段見慣れているとはいえ、その蒼い瞳でこうまで見つめられると、さすがの貴之も気恥ずかしくなってしまう。
「……まぁ、自分でそう思ってないのなら仕方ないかもしれないけど」
貴之はメニューを手に取って、なにかを選ぶふりをしながら顔を隠すとそっけなく答えた。
そうですか、と彼女の声が聞こえる。少しだけメニューを下げて彼女の様子を伺うと、グラスの中の氷をストローでつつきながら、がっかりした様子で俯いている。
何度見てもいつものシエルではなく、別人のように感じてしまう。それでもその行動は、やはりいつものシエルなのである。
ゲームセンターに一人で遊びに来てしまうようなところ
他人の体調に対してやたら敏感なところ。
そのくせお金をケチろうとするところ。
形容しがたいチグハグ感。
「シエル、食後のスイーツとか行っとくか?」
貴之は、メニューを俯いている彼女へと差し出した。
「?」
彼女は不思議そうな顔を貴之に向ける。
「スイーツってなんですか?」
「……ああ、デザートなデザート。なんなんだお前のその拘りは」
シエルはスイーツという言い方が嫌いなのであった。なんでも発音が可愛すぎて苦手なのだと聞かされた覚えがある。もう一人の幼馴染、月島円は甘いものが超がつくほど好きなスイーツ党であるため、貴之も単語の使い分けが大変であった。
「ああ、デザートのことでしたか」
メニューとにらめっこをはじめた彼女の姿は、やはりいつものシエルそのものであった。
くだらない事にも本気になってしまう顔。
「よし、これにしましょう。せっかくのクリスマスイブですしね」
彼女が指差したものはティラミスとアイスクリームのセットであった。
少し渋めのチョイスに違和感を抱く。いつもであればチョコレートパフェあたりに飛びつきそうなものなのに。
「モンブランがないのが残念すぎます。しょうがないからこれで我慢です」
こうして違和感はすぐにいつものシエルに塗り替えられる。
「……昨日食べたばかりでまた食べるのか」
「え! す、好きなんだから別にいいでしょう?」
「そりゃまぁ……んじゃ僕もケーキ食べようかな」
狼狽する彼女をよそに、貴之は逆さまのメニューを覗き込んだ。
――12/24*21:12
気付けば時刻はすでに午後九時を回っていた。
いつの間にか昨日から降り続いていた雪は止んでいた。
空を見上げれば雲の切れ間から優しく輝く星が見え隠れし、周りを見渡せばクリスマスのイルミネーションの煌きが人々を包む。
「随分と長居しちゃったな」
「そうですね」
話が噛み合わないのに会話は盛り上がってしまうという、不思議な体験をした二人。
らしくもはなく二人は、前の広場のベンチに腰掛けると、ライトアップされた木々をぼんやりと見上げていた。
「本当はこんなところで油売ってる場合じゃないんだぞ、お前は」
「……はい」
こうして体調が持ち直しているのも、隣に座る彼女のおかげであるにも関わらず、どうしても貴之は憎まれ口を叩いてしまう。
それというのも本当にシエルの事が心配だからだ。
今日だけの息抜きと言えば聞こえはいいが、クリスマスには勉強をすると自らに課した約束を破ってしまっていることに変わりはない。
もしこのままズルズルと気が抜けてしまったら。
そう考えると、彼女の今日の行動を見逃すわけにいかなかった。
「タカユキさんは厳しいのですね」
「当たり前だろう」
「そうですか、当たり前ですか……」
彼女はよいしょと小声を呟き立ち上がると、両手を広げ大きく背伸びをした。
「良かった。私の願いは叶えられていたんですね」
「……?」
彼女は軽やかに貴之へと振り返る。
イルミネーションの光で逆光となり、彼女をかたどる輪郭はひどく曖昧なものになっていた。
そこに居るはずの彼女。
にも関わらず手が届かないような。
貴之は消えてしまいそうなその姿に驚き立ち上がった。
「あ……」
彼女は貴之へと手を差し延べる。
「今度はこの手、握ってくれますか」
忘れられた記憶なのではない。
忘れたい記憶なのだ。
だが、忘れてはいけない記憶。
「なんで、ここに……」
貴之の胸の中を、言葉にならない感情が渦巻く。
その手を、握りかえせば、僕は救われる。
だが、その手を握り返す資格が自分にはない。
「大丈夫ですよ、今度こそ」
貴之は、その言葉に惹かれるように手を伸ばす。
真っ白な妖精のような少女に。
「サンタクロースはいましたか?」
そうだ。
僕は間違った事はしてきていない。
あの時、あの雪の降る日に僕は思ったんだ。
ぼやけていた彼女へのピントがあう。
貴之は今日初めて彼女を、この世界を現実のものとして認識した。
「いなかったよ」
少しだけ自虐をこめた言葉。
だが、立ち止まらない。
あの時の何も出来なかった自分ではないのだ。
自信をもって最後の一歩を踏み出す。
彼女の手をぎゅっと握りしめた。
彼女は、その手にもう片方の手を乗せると不意に震えだす。
「でも、私には、いました……」
涙声だった。
その声に貴之の胸はしめつけられる。
こみあげてくるものを押さえ、貴之はあの時言えなかったその一言を。
万感の想いをこめて、目の前の少女へと告げた。
「だから僕がサンタクロースになる。……君の願いを叶えるために」
「はい……最高のプレゼントでした」
彼女は端整な顔を涙でグチャグチャにして、それでも満面の笑みを浮かべた。
貴之の手を握り締める両手に額をのせ、彼女は嗚咽をもらす。
貴之の目にも涙が浮かぶ。
最悪なクリスマスが、最高のクリスマスに変わった瞬間だった。
「タカユキさん……今まで妹をありがとうございました……」
幼い頃に両親の離婚で海外へと移住した、シエルの片割れの魂。
もう一人の貴之の大切な家族。
「ああ……、こんなことは、おやすいごようさ……」
彼女には伝えなくてはいけない事が山のようにある。
しかし、貴之は涙が目から零れない様に空を見上げるだけで精一杯だった。
――interlude.C
雨宮メル乙姫。
海の名を持つ姫は、元気でしっかりものの双子の姉。
雨宮シエル織姫。
空の名を持つ姫は、人見知りで大人しい双子の妹。
西洋の童話から飛び出したかのような容姿。
にもかかわらず日本の昔話に登場する姫の名を持つ不思議な姉妹。
彼女達に出会ったのは貴之が五歳の時。
すぐさま彼女達と仲良くなった貴之にとって、二人はまるで本当の妹のようであった。
その容姿のせいで、幼稚園に入園早々苛めにあってしまった彼女達を貴之は身を挺して守った。
僕が彼女達を守るんだ。
小さな騎士は、二人の姫のためにそう誓った。
そして間もなく迎えたクリスマス。
姉妹はサンタクロースに願った。
どうかシエルが笑顔に包まれて幸せに暮らせますように。
姉のメルはそう願った。
どうかメルがいつまでも自分の隣にいてくれますように。
妹のシエルはそう願った。
そしてもう一つ、二人は同じ願いごとをした。
どうか貴之とずっといられますように、と。
幸せな日々は一年で終焉を迎えた。
元々病気を患っていた姉のメルは、日に日に痩せ細っていく。
いつしか寝たきりになってしまったメル。その隣から離れようとしないシエル。
色々なことが雨宮家で起こったそうだ。
このままでのはメルの命は長くない。
そんな焦りが、彼女達の両親から冷静な判断力を奪っていたのだった。
子供である貴之には、何故大人たちが争い、いがみ合うのかがわからなかった。
そして、彼女達を守ると言いつつも、その実何もしてあげられることはなかった。
出会ってからほぼ一年、再び雪の降った日。クリスマスイブ。
自分の傍らから離れようとしないシエルに対し、メルは一緒に夜の公園へ遊びに行こうと提案をした。
きっと空を眺めていればサンタクロースがプレゼントを届けにきてくれるはずだと。
こんな病など、あっという間に治してくれる魔法の薬をとどけてくれるはずだと。
そんな二人を守りたい。
騎士として最後の役目を荷うため。貴之は立ち上がった。
そして――
雪の積もった深夜の公園。
その声に貴之は振り返った。
しんしんと振り続く粉雪は街灯の明かりで、キラキラと輝いて見えた。
そんなスポットライトのように円形に光でかたどられた雪の上でメルは倒れた。
純白のコートと新雪を真っ赤に染め姉の傍らで、シエルは叫んだ。
「助けて!! おねーちゃんを助けて!!」
いつも大人しくメルの背中に隠れてばかりいるシエル。
貴之は彼女の口からこんな大きな声が出されるなどと考えた事もなかった、
シエルの悲痛な叫びと訴え。それは貴之をパニックへと陥れた。
シエルは姉を抱き上げ、泣き叫ぶ。そして、震える手を貴之に差し伸べてきた。
「お願い……助けてよぉ……」
貴之は足元の雪を踏みしめて、一歩づつ近付く。
「ま、待ってて、ぼ、ぼくが、助けるから」
「う、うん、お願い、タカユキくん、お願いだよぉ……」
シエルの手を握ろうと、ゆっくり、ゆっくりと。
抱き上げられ、こちらを見つめるメルの瞳は何かを貴之へと伝えようとしていた。
「…………っ!! ……………っ!!」
声にならない声を貴之は発した。
シエルの手を握ることもできない。
メルの言葉も聞いてやれない。
だが余りに遠い。わずか数メートル。
その時、貴之の脇を駆け抜け彼女たちへと駆け寄る影があった。
「どうしたんだ!」
「だ、大丈夫か!? 何をやってるんだこんなところで!」
「とにかく救急車だ、救急車を!!」
クリスマスイブ、静まり返った住宅街に少女の叫びが響けば、近隣の住人も気付きはするだろう。
駆けつけた大人達がメルを抱き起こし、シエルをあやす。
そんな光景を貴之はただ呆然と立ち尽くし見つめる事しかできなかった。
あの時のメルは貴之に何を伝えたかったのだろうか。
一歩も動けなかった?
そんな事はない、あなたは泣きそうな顔を見せてくれていたよ。
一言も言葉が出てこなかった?
ちゃんとシエルを励ましてくれたよ。僕が助けるって。
何一つ出来なかった?
ううん、タカユキさんは、あの時叫んでたんだよ。
僕の家族を助けてくれって。
僕じゃなくてもいいから。誰でもいいからって。
今、メルから伝えられた、あの時の言葉。
「自分をそんなにも責めないで」
それが今につながる本当の記憶。
――12/24*23:43
「うう、さぶ。さすがにそろそろヤバイか」
公園のベンチに座り、イルミネーションを見ながら昔話に花を咲かせた二人だったが、どうやらそろそろタイムリミットのようである。
「ふふ、そうですね。病人には酷ですもんね」
二人は、魔法の解けるまでの時間はあと僅かだと察していた。
思い返すと、この二時間休むことなく喋り続けていたなと貴之は苦笑する。
今回メルが帰国した理由は、病気がほぼ治った事を母親の孝子に伝えるためだった。
本当ならばメルもシエルに会いたかったのだが、孝子と相談した結果、受験を控えるこの時期に動揺させるような事をするべきではないという結論を出したそうだ。
幼少の頃の離婚騒ぎで、姉を引き取り、連れ去って行った父をシエルはあまりよく思っていない。
確かにメルと再会したら、いやがおうにもその父を思い出す事になる。
貴之も、メルが今回の帰国を内密にしておきたかったという話には素直に頷けた。
昨日の午前中、孝子が仕事を休んでいたのはメルに会うためだったということだ。
そこで、メルは孝子からシエルの話をたくさん聞き、写真もたくさん見せてもらったそうだ。そして勿論、その写真には貴之が一緒に写っている事も多かったわけで。
孝子から教えてもらった、今のシエル。
メルはその情報をもとに、シエルを演じていたそうだ。
話を聞き終わった後、もっと早く種を明かしてくれればいいのにと言った貴之に、メルは「あなたが聞かないからでしょう!」と随分腹を立てていた。
とめどなく続く互いの日常を語り合う時間。
そんな夢のような時は刻一刻と終わりへに近づいていた。
そして、きっとまた明日からは、今まで通り互いの今に帰っていくのだと。
「明日の朝に日本を発つって、一体何時起きなんだ?」
「はい、六時起きです。さすがにこんな時間じゃ、今からホテルに戻ってもほとんど寝れません。タカユキさんのせいですからね」
「おいおい、こっちがメルの昔話に付き合ったんだからな。褒められこそすれ、怒られる理由はないだろう」
「そうですね、それは申し訳ありませんでした。よしよし」
立ち上がったメルが貴之の頭を優しく撫でる。
「……なぁ、メル。日本には帰ってこないのか? シエルも喜ぶぞ」
「それは私には決められません」
即答であった。
少しでも彼女の気を自分達に向けられればと思ったが無駄なあがきだったようだ。
「そうか……そりゃそうだよな。メルはまだ中学生なわけだし」
「そうですよ。私達はまだ子供なんです。自分で生き方を決められないんです。でも……」
メルは貴之の頬を撫で、その瞳をまっすぐに見据える。
「生き方を自分で選べるようになるまで、シエルを守ってくれたタカユキさんには、本当に感謝してもしきれません」
「……そっか。そりゃ光栄だ」
感謝される事をしたつもりはない。
ただ、メルの願いを叶えてあげたかった。
メルのサンタクロースになってあげたかった。
どうかシエルが笑顔に包まれて幸せに暮らせますように。
メルが九年前に残した願い。
シエルはたくましく育った。きっと幸せでいてくれるはずだ。
そう信じて自分はこれからもシエルの背中を守ろう。メルのためにも、シエルのためにも。
ずっとメルが隣にいてくれますようにというシエルの願いを犠牲にした未来なのだから。
「それじゃもう少し。シエルが大人になるまで、あの子をよろしくおねがいします」
貴之の前でペコリと頭を下げるメル。
言われるまでもないことだった。もはやサンタクロースなど関係ない。
これからは、いやこれからも大切な家族としてシエルを守り続ける。それが兄の役目だからだ。
「まかせろ」
貴之はメルに向かって拳を握り差し出した。
「?」
貴之のポーズに不思議そうな顔をするメル。もっともな反応である。こんな約束の仕方は男のロマンというものだ。それでも、そんな風に育ったシエルの思いを彼女に伝えたかったのだ。
「シエルと約束するとき、よくやるんだ。互いの拳をコツンとぶつけるんだよ」
ニカっと笑い、貴之はさらに拳を突き出す。
「ふふ、わかりました。約束ですよ?」
「ああ、約束だ」
二人は軽くぶつけた拳を離す事なく笑いあった。
メルのファーストネームは乙姫。海の乙姫。
竜宮城から帰ってきた浦島太郎は、十数年後の変わってしまった世界に驚いたという。
そして貴之の瞳に映る世界も、今日メルと再会したことで鮮やかに輝き出した。
止まっていた時間が動き出したかのように。
クリスマスイブに現れた海の乙姫の鮮烈な記憶は、貴之のこれからの人生を変えていく。
新たな約束を残して。
「いつかまた」
それが新しく刻まれた最初の記憶。
――December.26
「三十八度二分……か」
シエルは貴之の脇から引っこ抜いた体温計を読み上げた。
「ああ、幸い頭痛とかないからな。本当にただ熱があるだけ」
貴之はベッドに寝転がり布団を首元まで被る。熱のせいで赤い顔をしているが、シエルに言ったとおりそれほど苦しいといった事はなかった。
「ん、まぁ。寝てれば治るだろう。下で唸ってた由美さんの方が重症だわ」
体温計をケースに戻すと、それを貴之の枕元に軽く放り投げた。
「それにしてもうつされて災難だったな。あ、ちゃんとマメに測れよ」
「わかってるって。それより近くにいると風邪うつるんじゃないか?」
見舞いにきてくれた事は嬉しいが、受験生に風邪をうつすなど言語道断である。
しかし貴之の心配をよそにシエルは貴之の勉強机の前にドスンと座る。どこからともなく取り出された透明なプラスチックの容器に収められたケーキ。
「あ、それ」
見覚えのあるそれは、由美の為に買って来たケーキである。が、食べる筈の本人があのザマであり、ひっそりと冷蔵庫の中で忘れ去られていた存在だ。
「うん、タカユキんところの冷蔵庫に入ってた。賞味期限二日切れてるけど。まぁ、いけるっしょ」
「二日……うん、二日ぐらいなら……いけるのか?」
賞味期限や消費期限を気にする貴之からすると一日でもラインを割っている次点でアウトなのだが。
「いけるいける、三日はいけるね!」
シエルは箱に取り付けられていたビニール袋からスプーンを取り出すと、ガツガツと食べ始めた。
「まぁ、いけるならいいけど」
いまいち納得しかねるがシエルはすでに食べ始めてしまった。さすがに今更どうこう言うのも野暮であろうと、貴之は嬉しそうにケーキを食べるシエルをぼーっと眺めていた。
飾り気のない黒いパーカーに使い古されたジーンズ。二つにわけられた金色のツインテール。
どこからどう見てもいつものシエルだ。
「……間違えるとか、本当にどうかしてた」
貴之はボソリと呟く。
わずか一日前の出来事がまるで夢のようだったと。
クリスマスイブ、九年ぶりに再会したメルとのひととき。
今日は十二月二十六日。
昨日はやはりというか当然というか、貴之は風邪を引いて寝込んだ。
ゲームで遊んでばかりいて、まともに寝ていない由美も相変わらずだ。とうとう吐き気までもよおしているらしいが、そこまでしてまで遊びたいのかとあきれ返るばかりだ。そんなわけで二日も雨宮家と連絡をしていなかったのだ。シエルが心配になって様子を見に来るのも当然であった。
「モンブランもいいけど、イチゴのショートケーキはやっぱり王道の美味さがあるなぁ」
口元に生クリームを付けてそういうシエルはニシシと笑う。
白い妖精メルと黒い小悪魔シエル。
同じ双子でも環境次第でこうまで違う性格になるのかと貴之は少し感心した。
「飲み物なしでよくケーキなんか食えるな」
「ばっきゃろい、ケーキは飲み物みたいなもんだ! いくらだって入っていくぜ!」
「飲み物だって無限にはっていかんだろう。いやその前に固形だし、それ」
「ああ、ケーキ屋でバイトとかすれば余りものとか貰えるかなぁ……」
貴之の突っ込みを無視して、スプーンを咥えたまま恍惚とした表情を見せるシエル。その間の抜けた姿に、こんな風に君の妹は育ったよ……と、メルに対して申し訳ない気持ちになってしまった。
「てか、コーヒーぐらいいれてこいよ。見てるこっちが胸焼けしそうだ」
「しょうがないじゃん、もうインスタントコーヒー切れてたんだから」
「え、マジで」
シエルのあまりのも豪快な食べっぷりに少し心配になって忠告したものの、貴之はものの見事に空回ってしまった。だがティーパックの買い置きはまだあったはずだ。
「んじゃ、紅茶でいいから、なんか飲め……って、ん?」
「ん? なんだ、どうした?」
貴之が言葉を濁したことにシエルはのってきた。
「あ、そうだ。僕のコートの中」
貴之は自動販売機で買った缶コーヒーが入れっぱなしであった事を思い出す
「なんかあるんか?」
シエルはスプーンを咥えたまま、部屋の入り口近くのハンガーにかけられたコートの中を漁った。
「お、缶コーヒーだ!」
「やっぱりな。それやるから飲んどけ」
「サンキュー! って、なんだこれ。レシート?」
シエルは缶コーヒーを片手に、コートから取り出したレシートを見て不思議な顔をしていた。
「レシートなんか別に捨てちゃってもいいから」
「いや、なんか裏に書いてあるんだが」
「なんだって?」
シエルはよれよれになったレシートを貴之に渡す。
その裏側には美しい文字が書かれていた。
恐らくメルの置き土産である。
その言葉とは――
Joyeux Noell!
「……どういう意味?」
シエルは貴之の手元を覗き込みながら単語の意味を聞く。
「わからない……」
貴之にもその意味はさっぱりわからなかった。
――finale
「しまった……」
メルは日本を経つ前、とある光景を見て愕然としていた。
空港のいたるところに設置された垂幕には、クリスマス関連のものが溢れ帰っていたのだが。
「そうよ、日本人だったらメリークリスマスじゃない! なんでジョワイユ・ノエルなのよ!」
大きく描かれたX’masという文字。
明らかにおかしい造語である。だがしかし、これが日本ではメジャーなクリスマスを英語で書いた場合の綴りなのだ。
すでに三日も滞在している日本で何故それに気が付かなかったのか。そしてフランス語でメッセージを残してしまったのか。崩れるように自らのスーツケースによりかかる。
「だ、大丈夫。タカユキさんならきっと調べてでも読んでくれるハズ……ああああ」
自分の迂闊さが恨めしいとひとしき呻いた後、天井を見上げる。
「だってちゃんとクリスマス祝えなかったんだもん! ううん、でももういい! 今度はちゃんと言いに来るんだから!」
グっと拳を握り締めると、貴之と拳をぶつけて約束をした事を思い出した。
そう今度こそは。その時はシエルも一緒に。
「……必ず帰ってきますからね!」
クリスマスの垂幕へと拳を伸ばし、メルは軽やかに笑った。
―― #fin