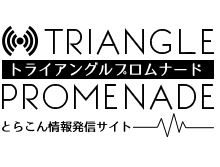『Summer vacation Quartet』#05*天ヶ瀬あかね編
#05/姫と王子と名誉部員
――#05
「ん~~……」
コピー用紙をホチキスでまとめた脚本に目を走らせながら、あかねは唸る。
ベンチに座る彼女のスラリとした美しい足は、先ほどから貧乏ゆすりが止まらない。
一度自分の世界に入ってしまうと周囲の目などまるで気にしない。いや、正確には気にする事が出来ないあかねらしい姿である。
「ああ、もう! わっかんないなぁ! なんでこんなにもスッキリしないんだろう!?」
あかねは頭をかきむしり、小刻みに体を揺らす。そのヒステリックな姿はいつもの明るく快活なあかねからは想像もつかない。うら若き十七歳の乙女が台無しであった。
今日は真夏の突き刺さるような日差しも雨雲に遮られ、八月とは思えないほど涼しく快適だ。
この旅館に宿泊している人にとって、それは少し期待はずれなことだった。ギラギラと輝く太陽の下、うだるような暑さの中でこそ、バカンスとは楽しいもの。海で遊ぶには涼しすぎる上に雨まで降っているという事実のほうが余程に迷惑なのだ。涼しいからなんだと、ここにいる誰もが思っているだろう。
にも関わらず、これは好都合だと思う四人組がいた。
花房了輔率いる一乃谷高校演劇部のメンバーである。
「おかしい、僕らはもう演劇部は退部しているはずなんだけど……」
首を傾げる貴之の隣であかねもウンウンと頷く。だが了輔や凪からすれば彼らは去年の舞台を共に成功へと導いたかけがえのない仲間である。貴之達がどう言おうと、これからも名誉部員であり続けることは本人たちの意思に関係なく、認められた既成事実のようなものである。
草津月館の中庭の片隅にある屋根のついた休憩所は、こんな雨の日に近づく者など誰もいない。ひっそりとしたもので、自主練にはもってこいの環境だ。
部長にして主演男優である了輔と、副部長であるこれまた主演女優の凪。彼らの自主練に、貴之とあかねはつきあっているのだ。何しろ了輔の演じる王子の役を途中まで作り上げたのは、昨年は演劇部に所属していた貴之であり、彼らの演じる『プリンセスローズ』の脚本はあかねが執筆したもの。了輔達にとって彼らほど頼りになるアドバイザーは存在しないのである。
「そうまで言われたらしょうがないなぁ……」
口ではそんな事を言いながらも褒められて悪い気はしない。貴之はともかく、あかねの照れっぷりは、見ている者を呆れさせるほどであった。そんなあかねを、三人は一様に「なんてチョロい……」と思ったものだ。だが今のあかねにそんなチョロい女の子の面影はない。どちらかというとチョロい方が可愛いので、是非今のような態度は表に出さないでほしいものだと、残りの三人はこれまた一様に思っていた。
「ふぅむ、天ヶ瀬君は考え始めるといつもこうなのか……正直怖いな」
「大体こんな感じ。コイツ内向的なくせに攻撃的だから」
「そこはせめて、夢見がちだけど行動的って言ってあげましょうよ?」
あかねの隣のベンチに座りヒソヒソと会話をする三人。
彼氏である貴之はともかく、親友の凪にまで結構な言われ方をされているが、あかねはそんな言葉を耳にしても気にならないくらいに、脚本を食い入るように見詰めていた。
「あかねがこんなんだからアレだけど、凪は本当に上手くなったなぁ」
ペットボトルの水を飲む凪に、貴之はニカッと笑った。
「あ、いえ……本当ですか?」
「ああ、ホントホント。見違えたよ。すごい堂々としてるしな」
凪は自然とゆるんできてしまう口元を、首にかけたタオルで隠した。
「三咲君は演技の上達も中々のものだが、それ以上に自信をもった態度で臨めるようになった事に、僕は嬉しさを隠しきれないよ」
「ああ、女優って感じがしてきたな」
二人の男性に絶賛された凪は恥ずかしさで身を縮めた。舞台での彼女とは違い、こういうプライベートな部分ではこれまで通りはにかんだ表情を見せる凪に、貴之と了輔は顔を見合わせて笑った。
「でも、なんというか……演技は問題ないんだけど」
貴之はそんな談笑をストップさせると、本題へと切り込んだ。
「ん? 何か気になることが?」
「ま、まだ息があってないところがありますか?」
和やかな雰囲気から一転、了輔と凪は真剣な顔付きで貴之の次の言葉を待った。
「あ、いや、演技はいいんだって。すげぇ良い感じに仕上がってきてると思う。……ただ、うーん」
考えがまとまらないのか、貴之は煮え切らない態度を取る。
「なんでもいいから言ってくれないか。互いに話しながらまとめていくのもいいと思うのだが」
了輔の助け舟に貴之もそうだなと返事をした。
「うん、んじゃまず凪」
「はい」
「なんか喋りにくくなかった?」
「はい?」
貴之の言葉の意味がわからないそんな訝しげな顔を凪が見せる。
「花房はどうだった? なんか引っかかったりしなかったか?」
了輔も貴之の言葉に眉をひそめた。
「引っかかる? セリフがかい?」
「そうそう、新しいセリフ。あかねの作ったパートに比べると、なんか流れてないんだよ」
あかねの作り上げた脚本、そのセリフは美しい響きを持っていた。
一方新しく書き加えられたセリフには何かぎこちなさを感じる。何故なのかはわからないが、貴之は明らかな違和感を感じていたのだ。
「それよ、それ!!」
今まで全く話に参加していなかったあかねが、貴之の肩に手をあて乗り出してきた。
「うお、聞いてたの!?」
「聞いてたわよ! てか、こんな近い距離で聞こえないほうがおかしいでしょ!? もちろん私の悪口も含めて全部よ!」
少しキレ気味のあかねに、ヒィと短い叫びをあげる三人。
「お、おう、それはまぁいいとして……。なんだ、なんかわかったのか?」
貴之は猛獣のような目つきをした彼女をなだめるように頭をポンポンと叩いた。
「ちょ、恥ずかしい事しないでよ!」
顔を赤くして貴之の手を振り払ったあかねが立ち上がる。
片腕を腰を当てて、丸められた脚本を了輔と凪へと振り下ろした。
「ズバリ、この加筆した部分を書いた子は舞台映えする言葉を選んでないのよ!」
あかねの言葉に、三人はおおっと言葉をあげた。
「ふぅむ。つまりこの脚本家のスキルに問題があるってことかな?」
了輔は腕を組むと、あかねへと質問を投げかけた。
「スキルっていうか、別のスキルを使ってる……感じ?」
「別のスキル?」
凪がオウム返しをすると、あかねは大きく頷いた。
「これを書いた子って誰?」
あかねの質問に、了輔もいよいよ真剣な表情になる。
「文芸部副部長、二年生の守山珠希という女子だよ」
昨年あかねが演劇部の為に執筆した、オリジナル創作劇『プリンセス・ローズ』は、登場人物が極端に少ない物語であった。元々が舞台の為に作られたストーリーではなく、あかねが暖めてきたファンタジー恋愛小説をベースにしているために、人物が少ないのは当然とは言えば当然であった。昨年は演劇部の部員が例年よりも少なかったのも好都合だった。
昨年の演劇部の秋公演で上演された『プリンセス・ローズ』は大好評を得ることとなった。
それからというもの、公演が行われるたび『プリンセス・ローズ』を目当てにかなりの人数の観客が押し寄せるようになった。
集まるのは観客ばかりではなかった。
今年の春、新たに入部した一年生は歴代最高人数。それどころか昨年の学祭公演で心を打たれた二年生が途中入部までしてきている始末。演劇部はこれまでにない大所帯になっていた。
今や一乃谷高校演劇部の代名詞ともいうべき作品となった『プリンセス・ローズ』を、これまでのまま上演するとなると舞台に立てる部員はごく限られた人数になってしまう。そこで昨年の演劇部部長である森下小百合と、現部長の花房了輔は、その時々の部員数の増減にもある程度対応できるよう、『プリンセス・ローズ』にバリエーションを持たせることにしたのだ。
このような経緯の元に新たに加筆修正されたものが、今あかねが手にしている脚本『新プリンセス・ローズ』であった。
「これは舞台用にカスタマイズされてないのよ。小説なの、小説」
あかねが何度読み直しても、これといって悪い部分は見当たらないわけだった。
読み物としては、相当にしっかりしたものだったが、そのセリフの数々は舞台で演じるためのものという視点が抜け落ちていたのだ。
口から声を出してみて初めて気付くこと。
「あかねちゃん、カスタマイズってどういう意味……?」
場違いな質問にズッコケるあかね達。
「ああ、カスタマイズっていうのは、デジタル用語だから凪は詳しくなさそうだな」
苦笑する貴之に、凪は少し頬を膨らませて馬鹿にしないでほしいと小声で訴えた。
「カスタマイズっていうのはだね、それを使う人に合わせて仕様を変更することだよ。この場合は天ヶ瀬君が言いたいことは、この脚本のセリフは小説やドラマで使うように構成されてるってこと。だよね?」
凪に説明をしながら、了輔は最後の言葉であかねへと向きなおす。
「そそ、花房君の言うとおり。さっき貴之が、言葉が流れないって言ったのは、言葉のチョイスやセリフ回しに舞台で演じるための配慮がないからよ」
「なんだ、僕の思ってた事は正しかったのか」
貴之のモヤモヤとして言葉にできなかった違和感は、あかねの説明により解消した。
「でも、私達はあんまり感じなかったけど……。花房君はどう?」
「僕らはリアルタイムで加筆していった状態を知っているから、それが当たり前だと思い過ぎていたのかもしれないね。それに僕らの要望も大概だったから、随分守山君も悩んでいたようだし」
元々ある脚本のイメージを壊さずに、新しい物語を付け足すのは中々に骨が折れること。原作者のあかねの目から見ても、これを書いた人物はかなりの実力者であることがわかった。それほどに『新プリンセス・ローズ』は原作の雰囲気を壊さず物語のボリュームを上げることに成功してたいた。
ただ、脚本に対するセンスがあかねのそれとは決定的に違いすぎたのだ。
「これなら無理を言ってでも天ヶ瀬君に頼むべきだったのかもしれないな」
了輔の言葉に、あかねの心音は大きく跳ね上がる。
――あたしだったらこう直すのに。
しばしの沈黙のあと、あかねは掠れた声で呟いた。
「……ううん、そういうわけには……いかないから」
「あかねちゃん……」
先ほどまでの威勢はどこへやら、消沈するあかね。
そんな彼女に凪が言葉を投げかける。
「あ、ご、ごめんね凪。う、うん。本当だったらあたしが書くべきなんだろうけど……本当にごめん、その、あたしには、プリンセス・ローズに関わる資格も情熱ももう……」
「ストーップ、ストップ!」
貴之は大きな声をあげて立ち上がると、先ほどと同じようにあかねの頭に手を乗せた。
「な、何するのよ……」
か細い声で非難するあかねだったが、今度はその手を振り払うことはなかった。
「いいって、僕らはアドバイザーなんだから。あかねは思った事を言えばいいんだ」
「……うん」
自分は加害者だ。にも関わらずこのように凪や了輔の前で被害者ぶった態度を見せてしまう自分自身にあかねは幻滅していた。
だが、そんな自分をも認めてくれる貴之の一言で、なんとか踏みとどまる事ができたのだった。
「……大丈夫かい、天ヶ瀬君? どうやら僕は無責任な発言をしてしまったようだね、すまない」
謝る了輔に、申し訳ないと思いつつも、あかねは黙って首を横に振ることしか出来なかった。
「あー、大丈夫大丈夫。あかねは全然気にしてないって。多分謝ってるんだよ、コイツは」
貴之は笑いながらあかねの頭を少し乱暴に横に振る。なされるがままのあかねだったが、今度は首を縦にコクコクと振っていた。
「うん、あかねちゃんが気にする事じゃないから! 全然大丈夫だよ!」
凪がパンと両手を合わせると空気が変わった。
友人の温かい配慮に、あかねもメソメソしていられないと、心を奮い立たせる。
負い目とは永遠に戦うしかない。だからこそ、へこたれていてはいけないのだ。
「……うん、ありがとみんな。貴之ももういいよ」
「おう」
貴之はあかねの頭から手を離すと、彼女に並ぶように立った。
あかねにとっては、その距離が何よりも心強かった。
「よし、それじゃ打開策を考えよ! 二人がもっと演じやすいセリフを考えるの」
あかねは、了輔と凪をしっかり見据える。
「本当は役者がやることじゃないし、大変な事かもしれない。でも、プリンセス・ローズはみんなで作る劇だから。自分の言葉でもいいの。とにかくお客さんに伝わる言葉を思い描くの」
負い目があるからこそ誠意で応えなければならない。
「そのことをこれを書いた子に伝えるの。もっともっといい舞台になるはずだから」
自分の役割を放棄しているあかねが本来言えた言葉ではない。
それでも自分にはこうすることしかできない。きっとこれで二人には自分の気持ちが伝わるはずだ。
そう信じて。
「……うむ、了解した。どうやら僕らは守山君に頼りきりだったようだね」
「みんなで作るのがプリンセスローズ……、うん、あかねちゃんの言う通りだと思います!」
了輔と凪の晴れ晴れした顔を見て、あかねは心の棘がまた一つ抜けたような気がした。
雨が降り、おおよそバカンスとは思えない日ではあった。
だが、またこうしてあかねの心は清々しく晴れ晴れとした太陽で照らされた。
少しずつ、あかねの心は世界と摺り合せられているのかもしれない。
忘れられない思い出が、こうしてまた一つあかねの中で積み重なったのだった。
「ねぇ、シエルちゃん」
「はい?」
「私、今日こんな風に覗き見ばかりしてる気がするんだけど」
「しょうがないじゃん。せっかくタカユキたちを見つけて駆け寄ってみれば、なんかすごい修羅場みたいなことになってたんだもの」
「うん、だからこうやって草陰に隠れたんだよね。雨が冷たいよシエルちゃん。せめて傘はさしておくべきじゃないかな」
「ああ、うん。なんでそんな説明口調なの?」
「うん、風邪引いちゃうと思うの。……温泉入りたいなぁ」
「温泉なら後でいくらでも付き合うから。それより気になるでしょ、あかねさんの事」
シエルと円は了輔と凪の練習を冷やかしにやってきたものの、彼らの真剣な様子にたじろぎ、思わずこうして隠れてしまっていたのだ。
「あかねさん、なんであんなに落ち込んでるんだろう……」
「そうね、それはそれ、これはこれだもんね。雨が冷たい事とあかねちゃんが悲しんでる事は別問題だし、あかねちゃんが悲しそうなのは大事件だし……」
「あ、タカユキが立ち上がったよ、円ちゃん」
「ほんとだ! あ、頭に手を乗せたよ!」
「見ればわかるんだけど……だからなんでものすごい実況口調なの、さっきから」
「ほんとだね、なんでだろう? あ、見て見て、天ヶ瀬さんがすごく可愛い顔した!」
円とシエルの掛け合いは貴之達が和やかな雰囲気になるまで続けられた。
その後二人は何食わぬ顔で貴之達に合流し、会話も適当に切り上げて冷え切った身体を温めるために温泉へと向かったのだった。
「なんでオチに使われなきゃならないんだよ!」
シエルの憤りを含んだ叫びが昼間の浴場に響いたという。
―― Next #06