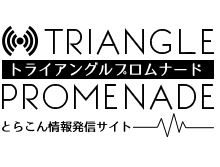『Tea for Two』 #09/Final *天ヶ瀬あかね編
#09/Final「勿論、ハッピーエンドだよ!」

――#09
「あぁぁぁ……」
洗面台の前、ドライヤーで髪の毛を乾かす貴之の口から呻きにも似た声が漏れる。
先ほどの騒ぎのあと、貴之は結局シエルの勢いに押され、とりあえず風呂にでも入って来いと半ば強引に風呂場に押し込まれてしまった。
湯に手を入れるまでは貴之も気付かなかったのだが、その風呂に張られた湯は五十度にも達しようかという温度の、いわゆる熱湯だった。
しかし時すでに遅し、服はすっかり脱ぎ捨てており、足元もびしょ濡れ状態ときたものだ。これでは引き返せまいと、仕方なく水を足し温度調整を試みたのだが、結局のところ想像以上の長風呂になってしまったのだった。
「これ、完全にのぼせてんよなぁ…」
鏡に映る、自身の情けなく火照った顔を見る。
貴之は本来冬場には使わないドライヤーの冷風モードに切り替えると勢いよく顔に当てる。
「あぁぁぁ……気持ちいぃぃぃ」
扇風機に声を当て震わせること事は出来るが、ドライヤーの風ではそれは無理のようだ。そんなどうでもいい事を考えていると、唐突に後方の扉が勢いよく開いた。
「入るわよー……ってやっぱり、そうなったか」
鏡に映った真っ赤な貴之の顔をその背中ごしに見た由美はククッと笑った。
「あのなぁ、ノックぐらいしろよ」
「ドライヤーの音したからもういいかなーって。どうだった? シエルちゃん特製の地獄釜は?」
「……あのまんま入るかよ。死んでしまう」
用がないならさっさと扉を閉めろと貴之が引き戸に手をかける。だが、由美はそれを阻むようにドアに足を引っ掛けた。
「なんなんだ」
「まぁまぁ、たまには母親らしい事言いたくなってね。とりあえず上半身なんか着な」
廊下から入り込んで来る冷たい空気が、貴之の思考を正常なものへと戻していく。
「……まだ、髪の毛乾いてないから。このままでいいなら聞くよ」
すばやく部屋着であるジャージに袖を通すと、再びドライヤーのスイッチを入れる。今度はもちろん暖風モードだ。
「あーあー! 聞こえてる!?」
「聞こえるっつの……。あんまり大きな声出すなよ、恥ずかしいだろう」
「おやまぁ、貴之も歳相応ってこったね。ママとの会話を彼女に聞かれたくないってか」
「誰がママだ。さっさと母親らしい事言えっつの」
つれないなぁ、と由美はぼやきながら腕を組んだ。
「可愛い子じゃないの、アンタのカノジョ」
「……可愛いならいいじゃないか。嬉しいだろ? 今日会えて」
もともと今日、由美はあかねと会う事にはなっていなかった。
貴之は、色々な事を一気に進めるのはやめたほうがいいという。由美は、母親として少しばかり残念ではあったものの、まだその時ではないとの息子の判断を尊重し、一応今日のところは、彼の顔を立ててやろうとしたのだった。が。
「まぁ、シエルちゃんにはまんまとやられたって感じがするわね」
「まったくだよ。あいつはもう、いつも僕の邪魔ばかりしくさって、だいたい今日のことだって……」
ブツブツと文句をいう貴之の言葉はドライヤーの音に掻き消えていく。
「でもまぁ、結構まんざらでもない展開だったと思ってんでしょ、アンタも」
「……」
息子の本意とは違う形になってしまったが、由美としてはあかねに会えた事は喜ばしかった。
そもそも放っておいたら、まともに紹介してくるのはいつになるかわからない。そして何ヶ月もした後に、今度は紹介する事が気恥ずかしくなるに違いない。何かとタイミングが悪い男なのだ貴之は。
そう思うと、今日のシエルの作戦にグッジョブと言わずにはいられない由美だった。
なんでも自分一人で決め、行動してしまう貴之。
一体誰に似たのかと由美は考えたが、頭に浮かんだのは「そんなものお前に決まってるだろう」と突っ込みを入れてくる旦那の呆れ顔だった。
「そんでだ。あかねちゃんと会った母親の感想とか聞きたくない?」
「……そりゃ、聞いてみたいけど。なんでまた今?」
ドライヤーのスイッチを切った貴之が由美へと振り返る。
「いや、シエルちゃんからもう少しアンタを足止めするように言われたもんでね」
「またアイツは……何を企んでんだか」
さぁ? と由美は首をかしげた。そして貴之の顔にずいっと自分の顔を寄せ、睨みつけると、声のトーンを落として言った。
「昔の円ちゃんに似すぎね、あの子」
「えっ……?」
由美の言葉に貴之は声を詰まらせた。
天ヶ瀬あかねと月島円に共通点など、どこにもない。
かたや、勝気な性格で、成績優秀スポーツ万能の人気者。
かたや、大人しく穏やかな性格で、どこにでもいる目立たない女の子。
どこにも通じるものなどない。ないはずである。
そう確信しているにも関わらず、貴之は心を乱され、うろたえている。
由美の予想そのままの、貴之の反応だった。
まるで本質を理解していない息子に、由美はやれやれと頭を掻く。
「こんな事だろうと思ったけどさ。ねぇ、もしもアンタがあの子の事を守る為に彼女と付きあってるとかぬかすなら」
「ちょ、ちょっと待ってくれよ、どういうこと円とあかねが……」
慌てて問いただそうとする貴之だったが、由美の眼差しにたじろぎ、口をつぐんだ。
「アンタ、昔からそうだからね。責任感とか義務感とか、そういうのが感情より先に動きすぎんのよ。で、後から感情が追いついた時にはもう手遅れだっていうね」
貴之は視線を落とす。反論できない自分自身に舌打ちをする。
――僕は何が相手の幸せなのか、いつも考えてしまう。
でも僕が思う幸せと、相手が思っている幸せが同じものとは限らない。
相手が本当は何を求めているかなど、見出すことは出来ないのだから。
そうやって色んな人を傷つけた。
そうやってきっとこれからも色んな人を傷つける。
「円は……僕が……」
貴之は声を絞り出そうとした。が、ただ廊下から流れる冷たい空気が肺に入ってくる感触が胸に残るだけだ。
「分かった? アンタ、誰かの為になんかできるとか思わない事ね」
「……」
「アンタに出来るのは、アンタが幸せになる事だけ。それ以上でもそれ以下でもないから」
ふぅ、と由美は一息つくと貴之の脛を軽く蹴る。
「いてっ」
顔を上げ、由美を見る貴之。そこには先ほどの眼差しとは違い、いつもの由美のニヤけ顔があるだけだった。
「今日はこの辺にしてあげる。あとは宿題ね。それより、あかねちゃんが居間で待ってんだからそろそろ行かないとシエルちゃんが怒るわよ?」
自分で呼び止めておいてそれはないだろうと貴之は笑った。
手早くドライヤーを片付け、靴下を履く。息子の仕草がなんとも旦那に似ている事に、由美もまた苦笑いをした。
行動は感情的な母親に似ているくせに、肝心の感情は、論理的な父親に瓜二つな息子。
由美はそんな貴之を、面倒なヤツだと思うと反面、改めて可愛くて仕方がないのだと再確認したのだった。
「……僕は、あかねの事が好きだ。義務感とかそんなんじゃない」
由美の横を通り過ぎながら、貴之は小さく呟いた。
「遅い! どんだけ長風呂なんだタカユキは!」
「おまえら、いい加減にしろよ!!!」
リビングのソファに腰掛けた貴之は、由美に続きシエルにも言われのない責めを受けていた。
腰に手を当てての仁王立ちは、先ほど貴之の部屋に乱入した時と同じシエルお決まりのポーズだ。心なしか由美も同じような姿をする事が多い気もするのだが、なぜそう思ったのかを考えるのはやめる事にした。
一方、仲が良いのか悪いのか分からないような貴之とシエルの言い争いを、あかねはキッチンから眺めていた。あかねの培ってきた仲の良い友人像からは、いたくかけ離れていたが、何故だか今はそんな彼らの信頼関係が羨ましいと思えた。
それにしても、もともとはシエルが時間稼ぎにと湯加減を熱くしたことが全ての始まりであったはず。にも関わらずその策略に引っかかった貴之の方に否があるかのようなやりとり。しかも貴之の方に旗色が悪いときている。これにはあかねも笑いを堪えずにはいられなかった。
「そこ、何笑ってんだ! あかねも何企んでるんだよ」
「ひえ!? べ、別にそんな大層なもんではないと思うけど!?」
あかねは突然の貴之の声にひっくり返った声を出す。
「こら、タカユキ! あかねさんを怖がらせんな!」
あいつがこんな事で怖がるタマか、と貴之は腕を組んで深くソファにもたれ掛かった。
ははは、と苦笑いするあかねに、シエルもそれもそうかとなんとなくだが納得した。
「ん? 今あかねさんって言ったか?」
「ふふーん、どうよこの距離が縮まった感じ。羨ましいか? 羨ましいのか?」
「え、いや、僕はもとから呼び捨てなんだが……」
「ふはは、羨ましいと言え! 円だけにあかねさんの友達になる特権を譲るつもりはないんだよ!」
高笑いをしながらふんぞりかえるシエルに、貴之の声は全く届いてないようだ。
「あはは、シエルちゃんの頼みを断れる子なんていないって」
有頂天になっているシエルの隣に、手持ちの鍋と二つのカップをお盆に乗せたあかねが立つ。
「はい、というわけですよ」
あかねが、そんなティーセット一式を貴之へと披露し、「どうだ!」とシエルがより一層得意満面の表情で貴之を一瞥する。
「ああ、そういう……。早いよ、お前はなんでもかんでも……」
褒め言葉だな、とシエルは嬉しそうに答えると、あかねの背中をポンと叩いた。
「ほら、あかねさん。この馬鹿ドキドキさせちゃってよ」
小声でよくわからない応援をするシエルに、あかねは困ったようにウンと頷く。
「聞こえてるんだけどなぁ……」
シエルに気にかけられるまでもなく、今日の貴之はあかねの魅力にすっかり骨抜きにされている。それに加えて、このシエルの作戦。そう、貴之が望んだあの紅茶の味をあかねが振舞うというのだ。ああ、これではいらぬ愛の言葉でも呟いてしまいそうだ。そんな贅沢な悩みを押さえ込み、貴之は自慢の彼女の顔を見た。
「もう降参?」
あかねがクスッと笑う。その屈託のない表情から貴之は慌てて目を逸らす。先ほど熱湯でのぼせたときより、はるかに顔が上気しているのが自分でもわかった。
あかねはあかねで、照れる貴之というレア現象に胸をときめかせていた。心から自分への好意を剥き出しにしてくれる貴之が、あかねにはとても愛おしく思えたのだ。
そんな恋人同士特有のラブフィールドを作り出した二人に、自分で仕掛けた事ながらシエルもやれやれと溜息を漏らさざるを得ない。
「はいはい、ご馳走様。んじゃ私は由美さんのところでゲームでもやってくるから」
「お、おう」
心ここにあらずといった貴之のしどろもどろな返事に気を良くし、踵を返して廊下へと歩き出したシエルを呼び止めたのはあかねだった。
「あ、シエルちゃん!」
呼び止められ振り返ったシエルは、まるで庄治のように親指を立てるとニシシと笑った。あかねもつられて笑う。
あかねの言葉を背中で聞くと、彼女はお決まりのセリフと共に扉に手をかける。
「んじゃ、ごゆっくり!」
パシャリと軽い音をたて、リビングの引き戸が閉まった。
シエルが去ると途端にその場は静まり返り、なんとも気恥ずかしい空気に満たされた。壁掛け時計の音だけが、ただ響く。
「……えっと、貴之、どうしたの?」
「はい、なんでしょうか」
「な、なんで敬語なのよ……!」
「は、はい」
あかねはギクシャクと首を動かす貴之に声を荒げた。
いけないいけないと、一旦大きく深呼吸をしたあかねは、手にしたお盆に視線を落とす。
「で、これ……シエルちゃんに教えて貰った、チャイティー……なんだけど」
たどたどしい説明と共に、手にしていたティーセットを静かにテーブルへと置く。
「……ん? チャイティー?」
貴之の不思議そうな表情を見て、あかねが「ああっ」と小声をあげ訂正する。
「違う、ロイヤルミルクティー」
「?」
どうやらシエルと同じく、貴之もロイヤルミルクティーとチャイティーの違いがよく分かってないようだった。でも、チャイティーとロイヤルミルクティーの違いなんてきっと些細なことなのだ。月島さんもきっと同じで、貴之にあまり説明もしていなかったのだろう、とあかねは思う。そんな所も、なんだか月島さんらしい。
彼女にとっては、それがどんなものであるかよりも、それに込められた真心の方が大切なものだったに違いない。そんな友達の心情を感じる事が出来た自分自身にあかねの心は弾んでいた。
「ううん、なんでもないよ! ミルクティー、これはロイヤルミルクティーだから!」
何か言おうとする貴之を制して、まさに勢いで押し切らんばかりにあかねは念を押した。
「あ、そう……なんだ。よくわからないけど、まぁ、そうなのな」
うんうんと頷くと、あかねはティーカップに紅茶を注いだ。
「鍋から直接だと優雅さはないんだけど……」
煮出して作るロイヤルミルクティーは本来カップに注いだ状態で出すものだ。確かに、鍋からカップに注ぐ姿はあまり格好がよいものではない。
「まぁ、その、ね? あ、あたしが注いであげたかったから、しょうがないよ」
貴之が口に出すまでもない。またもやあかねがその疑問を潰していく。自分のカップにも注ぎいれると、鍋敷きへとそっと鍋を下ろす。
「……どうぞ」
紅茶を注ぎ、貴之の反応を伺うように胸元で手をモジモジさせているあかね。カップに口をつけるまでもなく、あかねのそんな姿だけで貴之はお腹一杯のスイーツを食べさせられた気分だった。
その甘ったるい雰囲気はしかし、貴之にとって悪いものではなかった。貴之は何ヶ月も気を張ってあかねとの関係を築いてきたが、実はこんな関係こそ本来求めたものだったのかもしれないと思った。
「んじゃ、頂きます」
紅茶を一口含むと、慣れ親しんだ少し甘めの風味高い味が口いっぱいに広がった。その味は、まさしく円やシエルが作るものと同じだった。
「ど、どうかな?」
あかねが期待の眼差しを向ける。キラキラと輝くその瞳に、貴之は少し照れた笑いを浮かべると「美味しいよ」と返事をした。
さっきと同じ時計の音。でも今は、ぎこちない沈黙を刻む音ではなく、二人を祝福する小鳥のさえずりのように、チクタクと和やかな時を刻んでいた。
「ご馳走様でした」
貴之がカップをテーブルへと戻す。カチャリと陶器のぶつかりあう心地よい音と共に、静かなティータイムは終わりを告げた。
「えへへ」
あかねは、少しだけ紅茶の残ったカップを両手で包み込むように持ち、口元を隠す。向かいのソファーで上機嫌にしているあかねを見ていると、ああ、僕はこんなにも彼女の笑顔に癒されるのかと、貴之はつい頬がゆるんでしまう。それは一面のお花畑に囲まれて安らぐかのような時間であった。
「なんか良い事あったんだ」
貴之の質問に、あかねはさらに照れた顔になると恥ずかしさで舞い上がりながらも頷いた。
「さっき、シエルちゃんから聞いちゃったの! この紅茶の意味!」
貴之は今日一番の眩暈に襲われた。
「え!? あ、ああ! そ、そうなんだ、へぇ~……!?」
動揺を隠せない貴之。まさかシエルのやつ、円の想いを紅茶に託している事をあかねに伝えてしまったのか、いや、伝えたとしても今の貴之には後ろ暗い所など微塵もないのだが、それでも微妙に背徳の匂いがする冷や汗がすうっと背中を伝う。
「ふふ、貴之もそんな風に照れる事なんてあるんだね」
舞い上がっているあかねの目にはそう見えるらしい。
「……そ、そんなことないぞ!? 僕はいたって普通だ!」
どうみても普通ではない人間ほど、自分の事を普通だという。まさに今の貴之である。
「まさか……、その、お嫁さんになる人に、自分の好きな紅茶を淹れて貰うことが夢だったなんて」
あかねは手にしたカップで、その赤くなった顔を隠す。
「え!?」
「……?」
あかねの笑顔を見ながら貴之は察した。シエルが大切な部分をぼかして説明したこと事に。
「あ……。ああ、うん。そうです……」
「ふふ、案外ロマンチストだったんだね。ちょっと親近感沸いちゃった」
どうやらシエルはこのロイヤルミルクティーに込められた想いまでは、あかねに伝えなかったようだ。
『ほら、あかねさん。この馬鹿ドキドキさせちゃってよ』
――さすがに、円から貰った想いを失くさないよう、自戒を込めてあかねにこの紅茶を作ってもらおうなんて考えは……言えるわけないよな。
シエルのいやらしく笑う顔が脳内に浮かび上がる。
「あのやろう、またおちょくりやがって……」
ドキドキさせるというのはこの事だったのかと、貴之は小声で悪態をついた。
「……あの、そっち行っていいかな?」
あかねは、ニコニコとしながら紅茶を飲み干すとそのカップをテーブルへと戻して、少し甘え声で言った。
「あ、ああ。よ、よろしいのではないでしょうか」
「だからなんで敬語なのよ!」
貴之の煮え切らない態度に、痺れを切らしたあかねが立ち上がる。
「もうちょっと甘い言葉とかかけてよ、もう!」
貴之の動揺とはまるで見当違いな怒りをぶつけるあかねは、テーブルを回り込むと貴之の隣にドスンと勢いよく腰掛けた。
「だから、お前はそういうところ、もうちょっとおしとやかにしろって!」
「なーにーよー! あたしは元がこういう大雑把な性格なんだからしょうがないでしょ!」
「いや、あかねは乙女主義ならもっとおしとやかにするべきだと僕は思うぞ」
「なによそれ! あかねはそのままでいればいい、とか言っちゃったくせに」
「それとこれとは話が違うだろう!?」
「違わないもん!」
ふん、と鼻を鳴らすとあかねは貴之の肩へともたれ掛かった。
「~~~っ!!!」
絶句する貴之を上目遣いであかねは見つめた。
「せっかく、こう未来のお嫁さんが紅茶を淹れたわけなんだし、もうちょっと褒めてくれたっていいじゃない……」
貴之の心拍数が跳ね上がる。これ以上何か言われたらどうにかなってしまいそうだ。
「あのなぁ……。すげー嬉しいんだよ。嬉しすぎて動転してんだよ。わかれよ、男心をよ」
「ぷっ。やっぱ、貴之って攻められると弱いタイプなの?」
「……そうみたい」
あかねはニヤ~と笑いかける。
まるで由美やシエルが乗り移ったようかのような、その小悪魔的な顔に貴之は青ざめる。そして、あかねが自分をからかっているのだという事にようやく気がついた。
「なぁんだ。ばれちゃったか」
貴之の表情が変わったのに気付き、あかねもからかっていた事を素直に白状した。
「らしくなかったからね。でも、本当、焦ったよ」
「いやぁ、これで貴之なんか一発KOだよ!なんてシエルちゃんが言うからさ」
「おいおい、お前一日で感化されすぎだろう。シエルみたいになってどうするんだよ」
どんだけ策を巡らしているのだあの小娘は、と貴之は改めてシエルだけは敵に回したくないと感じていた。溜息をつく貴之の隣で、うーっとあかねは大きく背伸びをした。
「ああ、面白かった」
「……僕は心臓に悪かったよ」
「えへへ。まぁ、さっきの雰囲気だと。あたしも貴之がその気になったら止まらないかな~なんて思った」
「おい、僕がお前んところの両親に顔向けできんようにしたいのか」
「いやぁ、隠せるかなとか思うじゃん?」
ケラケラとあかねが笑う。
「まったく……据え膳食わぬは男の恥とは言うけどなあ」
「あたしの食事は口にあいませんかね、貴之殿」
「……それを今言うか?」
「あはは……。あたしとしてはこの紅茶を貴之に振舞えただけで今日の作戦は大成功なんだから、これ以上は望まないですよーっだ」
あかねは満足そうに軽く舌を出した。
「んじゃ、シエルちゃんの企みはこれでおしまい」
すぐ隣、肩が触れ合いそうな距離で可愛らしくちょこんと座るあかねに、貴之の鼓動は高鳴る。
さっきみたいに少しぐらい寄りかかってくれてもいいのに。そんな事を考えながらも、縮まったあかねとの心の距離感に貴之もまた満足していた。
ただただ、この優しく過ぎていく時間を、隣に座る少女と共に分かち合いたかった。
「あたしねぇ、結婚したら子供は二人がいいなぁ……って」
あかねはテーブルに置かれた貴之のカップへ手を伸ばし、その淵を指で優しくなぞる。
「え!!?」
突然のあかねの独白に貴之の声がはねあがった。
「一人は男の子。貴之の為にね。一人は女の子、それはあたしの為に」
「ななななな、なにを言ってるのでしょうか、あかねさん!?」
貴之はソファーの端へ飛びのいてあかねから遠ざかると、口元を引きつらせてあかねに問いかけた。しかし彼女の呟きはお構いなしに続く。
「でね、週末に子供達が寝静まったあと、こうやって二人でお茶を飲むの」
ウットリとカップに話しかけるようにあかねが言葉を紡いだ。
「え、ええ……」
貴之には、色仕掛けよりもこちらの方が堪えているようだ。
「ええーっと、あかね、それどういう……」
具体的なあかねの未来プランを突きつけられ、貴之の背中には先ほどとは別の種類の冷や汗が大量に流れる。
うふふっ、と奇妙な笑い声と共にあかねの瞳が妖しく光った。そして……。
「な~んてね! 今度はあたしの作戦でした!」
「へっ……」
あかねは、テーブルから自分のカップを取る。
両手にそれぞれのカップを握り、軽くチンとそれをぶつけあう。
「今のは、ティー・フォー・トゥーていうミュージカルソングの歌詞の引用なの」
「はい?」
「いやいやいや……。何もそんなに青ざめなくても」
あまりといえばあまりの貴之の動揺っぷりにあかねは眉をひそめた。
「なによぉ……。今のは冗談だったけど、これから先ありえない未来じゃないでしょ?」
「違うわ! お前の演技の方がやばかったんだよ! お前は自分が思ってるよりもずっと乙女趣味なんだから、そういう事したらハマリすぎんだろ!?」
「あ、ありゃ、そう? ごめん……」
貴之の裏返った声の訴えに、あかねは申し訳ないといった表情を見せる。
「でも確かに、これからそういう未来だってあるんだよな……」
三度冷静さを取り戻した貴之が定位置に座りなおすとそう答える。
「うん、まだまだ想像つかないけどね」
あははっ、と笑うあかね。そのソファーに置かれた手に貴之が手を重ねる。
「あ……」
「まぁ、自分からなら。なんとか大丈夫。それに……」
一瞬ビクリと反応したあかねだったが、そのまま貴之の手に指を絡ませた。
「うん、あたしもちょっと触れ合いたかった」
か細い声でうつむくあかね。
「あ、ああ。んで、そのミュージカルってどんなのだよ?」
気恥ずかしさのあまり、貴之は無理やり話題を変えた。それを察したあかねがクスリと笑う。
「まぁ、恋愛モノなんだけどね。ぶっちゃけて言うなら、ノーとしか言えないヒロインが、自分の事を好きでいてくれる男の子からの告白を全部断っちゃうみたいな」
「なんだそれ?」
「まぁ、女の子はその男の子が幸せになれるようにって感じで……。そうね、お互いがお互いの為を思って上手くいかないみたいな……って、あれ……?」
そこまで話したあかねは、目をパチクリさせる。
「あ……。ああ、うん……。その辺でいいから」
貴之が苦笑いと共にあかねの説明を止める。
「お、面白いね、あはは。あ、あたしもここまで考えてたわけじゃないのよ!?」
「ぷっ、ふふ、あははは。はははっ!!!」
弁明するあかねに、貴之は心の底から声を出して笑った。あかねも、そんな貴之につられて笑い出す。
「ははは! それで!? そのミュージカルの二人はどうなるんだ?」
笑いが堪えきれない貴之があかねの手を握り、その繋いだ手の温もりと共に彼女を笑顔で見つめた。
それにあかねも応えるかのように貴之の手をギュっと握り締める。
「勿論、ハッピーエンドだよ!」
――#Final
二学期も残すところあと一週間を切った十二月下旬。
期末テストから開放された一乃谷高校の生徒達は、休み時間を利用して冬休みの計画を練る事が多くなっていた。教室のあちこちで、スキー旅行の打ち合わせだの、大晦日に某遊園地の年越しライブに行こうだの、楽しそうな話題で盛り上がっている。
そんな何気ない風景が、今の貴之にはとても心地よく感じられた。
「ふぁ~……」
大きなあくびをしながら椅子にもたれかかり背伸びをした。貴之の目の前では、あかねと庄治がくだらない話題で笑いあっている。
あの料理会の日を境に、彼の周りの空気は変わり始めた。二週間ほど前まで、常にあかねの事を考え続け、緊張の糸が張り詰めた生活をしていたのが嘘のようだ。もはや気を張り続ける必要はなくなった。
だからこそ貴之は、会話に参加する事なくまどろみの時間を楽しんでいたのだ。
「なに、ニヤケてんのよ」
だがしかし、あかねに頬をつねられて、貴之は現実へと引き戻された。
「だよなぁ、相馬は最近ゆるみすぎじゃねーの」
「そ、そうかなぁ」
だらしない男の代名詞とも言うべき庄治にまで、生活態度の事をツッコまれる。これにはさすがの貴之も心配になってしまい、あかねにつねられた頬を撫でた。
「な~に? 相馬くんは、あかねとなんかいい事あったの?」
隣の女子から声をかけられる。周りに集まった友人達も興味津々といった風だ。
あかねがえっへんと胸を張りながら、貴之の代わりに乗り出す。
「ふふん! いい事はいっぱいあったわよー!」
通りかかる男子も二人に声をかける。
「なんだなんだ? 相馬もとうとう、天ヶ瀬とねんごろになったのか?」
「ねんごろ……って。なんかすげー言い回し古いし、僕はまだそこまでは……」
「そうそう、こいつらの親密さを知ったら、お前ら腰抜かすぜぇ」
貴之がぶっきらぼうに答えようとするのを遮って、庄治が煽り立てる。女子達がより一層黄色い声をあげ、男子生徒は少しだけ驚いた顔をすると、ヒュ~と口笛を鳴らした。
「丘村、なんか知ってるなら話しなさいよ~」
「丘村のくせに我がクラスを代表するカップルの合間に居るなんて生意気ー」
「大体、相馬は寡黙すぎるぜ。このクラスだけの問題じゃないぞ、天ヶ瀬は学年の人気者なんだからよ」
生徒達が貴之達の周りに集まりだす。中心にはあかねを据えて。
あかねは確かにリーダーとしての求心力は失った。しかし、彼女持ち前の明るさや人柄まで失われたわけではない。あの日以来、本来の自分を取り戻し始めたあかねは、前とは違った魅力に溢れており、再び生徒達の中心になりつつあったのだ。
ふと、貴之はクラスメイト達と楽しそうに会話をするあかねから視線を移動させる。
そして顔をほころばせた。
窓際の席で二人の女子と会話をしていた、小柄な女生徒が一人。
まるで天使のような優しい笑顔で、成り行きを見守っている。
「ほんと、風向きは良し……って感じだな」
朝凪のように静止していた二人の時間も、柔らかな風と共に再び動き始める予感がした。
――あたし、”あの子”にお弁当を作ってあげたい!
そう言ったあかねに、貴之は諸手をあげて喜んだ。
あかねが”あの子”を避け続けたのは、世界と向き合う勇気がなかったからだ。
世界はあかねが思っているよりもずっと優しく出来ている。円やシエルとの絆を得て、あかねもようやくそれを感じられるようになったのだろう。そしてこの世界に飛び込んで行く為に必要な事を学んだ。
ほんちょっとの勇気を持つという事を。
今度こそ”あの子”と向き合おう。結末を恐れてなんていられない。
「あたしは頑張ってるよ」という気持ちとともに、”あの子”にお弁当を届けたいんだ。
あかねはそう願ったのだ。
――また三人で一緒に笑えるかな……?
しかし、あかねはいまだもって不安を抱えているのだろう。
あたしは、”あの子”の横に並んで歩く事を許してもらえるのかな?
あの夏と同じく、また三人で笑いあう事を神様は赦してくれるのかな?
そう訴えかける眼差しに、少し前の貴之ならば答えに詰まっていたはずだ。
だが、今はもう怯む事はない。
彼もまた周りの人達から、誰かを信じる事の大切さを知った。
信じていたい、ではない。信じる、のだ。
あかねもその事には気が付いているのだろう。それでも不安なのだ。
きっと、いや、そうに違いない。
だから彼女は今、貴之からただ勇気を貰いたいだけなのだ。
ならば贈ろう。きっとそれは魔法の言葉のようにあかねに届くと信じて。
――きっと大丈夫さ、と。
昼休み、学食は相変わらずゴッタ返していた。
弁当を持参する生徒はそう多くはないため、学食では毎日激しい座席争奪戦が繰り広げられている。貴之もシエルが居なければこの戦場に毎日身を投じること事になっていたはずで、彼女には感謝してもしきれない。
四限目のチャイムと共に今日も学食にダッシュする、戦場の狼こと丘村庄治の活躍で、この日は特等席ともいうべき窓際のテーブルにありつくことができた。今日に限っては貴之は学食なのだ。庄治もたまには役に立つ。
ところが、場所の確保に躍起になった当の本人である庄治は、いつものヤキソバパンを買いそびれ、メロンパン一つという惨憺たる戦果で食事時を迎えることとなった。
「はい、がんばった庄治先輩にはこれをあげます」
庄治の向かいの席に座るシエルが、自分の弁当の蓋を裏返して、そこに卵焼きを乗せる。
「わお! まじかよ、女子に弁当分けてもらうとか、俺様初体験」
「……じゃ、私からも丘村くんに一つ」
卵焼きの隣に、コロッケを置く円。
「お、おおッ……月島さんまでもが……」
「泣くなよ……」
感涙にむせぶ庄治を冷たくあしらうと、貴之は改めてテーブルに身を乗り出す。
「で、今日のあかねの弁当はどうよ」
そう尋ねる貴之に、シエルと円は満面の笑みでVサインを出した。
安堵の溜息をもらす貴之に、弁当をつつきながらシエルと円が状況を説明する。
「朝から天ヶ瀬さんの家にお邪魔して試食したけど、今日のはばっちりだと思うよ」
「うん、私らなんも手伝いしなかったけど、ここ数日であかねさん腕上げすぎ」
「あの味なら、どこに出してもおいしいって言ってもらえるんじゃないかな」
「今日のあかねさんならやれる! 絶対だ! 間違いない!」
キャッキャと騒ぐ二人の様子を見ながら、貴之はうどんをすすった。
そう、今日のあかねの弁当が供される相手は貴之ではない。そしてその弁当には特別な意味がある。
円とシエルが太鼓判を押すほどの出来映えだ。あかねの真心が詰まった弁当は、そこに込められたあかねの気持ちも、その気持ちを伝えようとする覚悟も相手に届けることが出来るに違いない。
貴之としてもその場に居合わせることが出来ないのは少し残念だったが、きっとあかねの願いはかなうと信じて、自分だけ学食でうどんというのも悪くない。そう思った。
「それにしても学食のうどんとは冴えないですな、相馬くん。どう? これ、学年でも有名な女子二人から貰った弁当のオカズですが?」
庄治はニヤけ顔で卵焼きをつまんで見せびらかした。
「あっそ。その卵焼きは僕が毎朝食ってるもんだけどな」
「知ってるよ、こんちくしょう!!!」
庄治がモテないのは、このお調子者すぎる性格に原因がある事は周囲の誰もがわかっている。にもかかわらず、それを理解していないのは本人のみというのが不憫でならない。貴之達は哀れみの目で庄治を見るのだった。
「でも、なんかタカくんが、学食でご飯食べてるのって新鮮」
「あかねに弁当箱三つも持って来てもらうのはさすがにな」
ざまぁみろ、と庄治の負け犬の遠吠えが聞こえたような気がするが、貴之はガン無視で会話を続ける。
「たまには学食で温かいものを食べるのも悪くないしな」
「久しぶりに私が作るか? って言ったのに拒否しやがったんだぜ、こいつ」
ストローでコーヒー牛乳をすするシエルが、ムスっとして事情を説明する。円は眉をハの字にしながら、それは仕方ないよと笑いかけた。
会話に適当に相槌を打ちながら、向こうは華やかなお弁当会になっているんだろうなどと、ぼんやり考えている、その時だった。
「貴之!!」
名を呼ばれた貴之はハッとなり振り返る。
そこに立つ、ポニーテールの声の主。隣にはショートカットの小柄な少女。
「あかね……それに」
「えへへ、あたしの作ったお弁当、どうせならみんなと一緒に食べたいって言うからさ!」
あかねと手を繋いで現れたその子がペコリと頭を下げる。
二人の手には、赤と青、二つのお弁当箱。
「貴之さん……お久しぶりです」
「あ、ああ。凪、久しぶり」
たまたま顔を合わせたら、会釈をするくらいの事はあった。だが、こんな風に面と向かって話すのは何ヶ月ぶりだろうか。
少しだけ大人びた顔付きになったその少女、三咲凪が、グっと力強い眼差しを貴之に向ける。
「信じてました、貴之さん」
貴之は、凪はきっと待っていてくれるはずだと信じた。
凪も、貴之はあかねと共に迎えにきてくれるはずだと信じた。
私を信じてくれてありがとう。
私にあなたたちを信じさせてくれてありがとう。
万感の思いを込めて、たった一言。
――ありがとう。
「ハハッ、何がだよ……まったく」
思わず眼が潤んでしまった貴之は、それをごまかそうと、わざといい加減な返事をしながら明後日の方を向くのだった。
礼を言うべきは貴之の方だ。凪はたった一人、誰に相談するでもなく、あかねと貴之を信じて待ち続けてくれたのだから。
「そうだよ、こんな甲斐性なしを、信じるだけ無駄だって!」
あかねが、凪の手をより一層ギュっと握る。
言葉とは裏腹に、その手の温もりは貴之への信頼に満ちている。文字通り、手に取るように凪にはそれを感じることが出来た。
「ふふ、確かに、タカユキはちょっと甲斐性なしな部分があるよなー」
「うん、タカくんはもう少しだけみんなの事を信じてみてもいいんじゃないかなー……って」
シエルと円に冗談とも本気ともつかぬ追い討ちをかけられ、うぐっと怯む貴之。
凪はそんな彼らに目を細めた。
「あかねちゃん」
「ん?」
「私も、みんなの仲間に入っていいかな?」
凪の言葉にあかねは束の間、押し黙る。
じっと、凪を見つめる。
やがてその頬をひと筋の涙が伝い、そして凪をぎゅっと抱きしめ、少しだけ上ずった声で叫んだ。
「あ、あたりまえじゃん! 何言っちゃってるの、凪は!」
周りで食事をしていた生徒達も、何事かとその手を止める。
「ごめん……ごめん凪……ごめんね! あ、あの、あたし……あたし!」
凪に抱きつき嗚咽をもらすあかね。庄治が参ったね~と肩をすくめて両手をあげる。
「うわ、超目立っちゃってるし」
「でもこれは……しょうがないかな?」
「うん、これはしょうがないと思う」
貴之が、円が、シエルが。それぞれが少し困ったような、それでいて優しく暖かい表情であかねと凪を見守る。
「はわわわ、何を悠長に! 目立っちゃってますよ、貴之さん!」
「うわぁぁぁん! 凪ぃぃぃぃぃ!」
「ああああ、あかねちゃん、わかった、わかったからちょっと! ひゃっ!? どこ触ってるの!?」
学食中の生徒たちがざわざわと集まってくる。
「なんだなんだ? 仲直りの儀式か!」
「そういや、二年生の鉄壁コンビが最近は一緒に居なかったのはこのせいとか?」
「うわ! 天ヶ瀬先輩の王子様と、三咲先輩のお姫様復活って感じなの!!? キャー!!!」
「え、すげぇ、百合百合しいぃんですが! も、萌えーーー!!!」
周囲の男子女子がお構いなしに盛り上がり、そこらで拍手などをする生徒達まで現れる。
改めてこの二人の知名度の高さがどれほどのものかを知る事になった貴之も呆気にとられていた。
「よ、さすが三咲凪! 舞台役者だけに目立つ事に慣れてるな!」
庄治がそんな生徒達をまるで先導するかのよう歓声を飛ばす。
「え!? いや、こういうのにはちょっと、不慣れですが……って、あー、よしよし」
胸元で泣きじゃくるあかねをあやすかのように、凪はその頭を撫でる。
「うぐっ、凪、大好き……だよぉぉ」
見た事もない表情をしたあかねと凪がいる。それだけでも、ここまで進んで来た道に間違いはなかったんだと貴之には思えた。少しばかり遠回りをしてしまったのはご愛嬌。そう思えるほど、今この瞬間に立ち会えた事が貴之には嬉しくてたまらなかった。
「ははっ、やれやれ、とんでもない仲直りだな……」
本当に大切だからこそ、言いたい事が言えなくなる。相手の事を思えば思う程に。
親友とはそういうものだ。
「タカユキ、そろそろ和泉にもあかねさん紹介してやれよ」
シエルが貴之のわき腹を肘で小突く。
「……だよな」
貴之は今度は自分の番だと腹を括った。
貴之達にはまだまだ考えなければいけない事が山積みだ。
恋愛だけではない。進路、そしてこれからのどのように生きていくか。それでも、あかねと凪の笑顔があるならば、これから先の未来に何も怖いものはないと信じる事ができた。
その日、あかねが凪の為に作ったお弁当は、予定よりもちょっとだけしょっぱかったらしい。
――とらこん Alternative「Tea for Two」 Fin