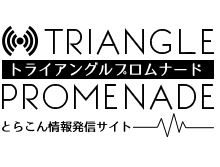『Tea for Two』 #08 *天ヶ瀬あかね編
#08「このバカみたいにかっこ悪いあたしと」

――#08
「うん、そう……」
台所の片隅から、あかねの呟くような声が聞こえてくる。
相馬家のリビングは、そんな声さえも鮮明に聞き取れるほど静寂に包まれており、貴之達が聞き耳を立ててしまうのも致し方ない。
「え? ううん、それは大丈夫。こっちで用意してくれたから。……というかそんな適当で本当にいいの?」
意を決して自宅に連絡を入れたあかねだったが、母の反応はそっけないものだった。見事に肩透かしを食らったと言っていい。グッとケータイを握り締めていた手も、いつの間にやらガクリと落とした肩と同様に力が抜けている。
「本当に替わらなくてもいいの? 貴之くんのお母さんもすぐ近くにいらっしゃるんだけど」
あかねが貴之の母親である相馬由美に顔を向ける。
隣で腰に手をあて佇む由美は、任せなさいと言わんばかりにニコニコと笑っている。しかし、髪はボサボサ、表情はどことなくぼんやりとして、心なしか身体もユラユラとゆれている。何より、今にもまぶたが落ちそうな由美の眼が、あかねには気になって仕方がなかった。
「はぁ、よかった……」
「いやぁ、びっくりした。信用されてるのなぁ、タカユキってば……」
ソファーに逆向きに座り、その背から仲良く顔を出して様子をうかがっていた男女二人。無論、貴之とシエルである。
困惑気味ではあるものの、笑顔のあかねを見て、貴之は胸をなで下ろした。
年頃の娘さんを一晩預かるのだ。下手をするとここ数ヶ月であかねの母親から得られた信頼を一挙に失いかねない。これからも長くあかねとつきあっていきたい貴之からしてみれば、それは大きな痛手になる。とりあえず今はその心配がなくなったことに、貴之は安心したのだった。
半ば強引に話を進めたシエルも、あかねの外泊が許されるまでには一波乱あると思っていた。
あかねの両親を納得させるためにはこちらも保護者を引っ張り出すしかないと、徹夜の仕事明けで熟睡していた由美を叩き起こしたのだが、完全に無駄骨だったようだ。こんなにも平穏に事が運んだことに、シエルは驚きを隠せなかった。
「……しかし、由美のやつまだ寝てんだろう、あれ」
呆れた口調の貴之。
「うん、由美さんをアテにした私が間違ってたわ。まぁ、結局いてもいなくても良かったようだけど」
大きく溜息をつくシエルに苦笑しながら、貴之は再びあかねの様子をうかがう。
「わかったってば。ちゃんとお礼は言っておくから大丈夫。それじゃ切るね。うん……おやすみなさい」
あかねはケータイを切ると、一呼吸して由美へと向き直った。
「というわけで、両親から許可を貰いました! あ、改めまして、今晩お泊りさせて頂きます、天ヶ瀬あかねです!」
よろしくお願いします、と元気よく頭を下げるあかねを、何を思ったのか由美はやおら抱きしめた。
「うわぁ、可愛いわ! 天使みたいだわぁ。ウチに天使が来とるよ、ほれ馬鹿息子、天使がなぁ」
「え、ちょ、あれ???」
「いやーん、ちょうカワイイ!やわらかいの好きやわらかいのくねくね、はふー」
明らかに寝ぼけている。あかねは助けを求めて貴之達に視線を送るが、ソファーから首だけ出してこちらを覗いていた二人は、ご愁傷様と言わんばかりにそろって首を引っ込めた。
こうして『あかねの相馬家お泊り大作戦』は、シエルの計画とはまるで関係なく、日ごろ培ってきた貴之への信頼が決め手となって、何の波風も立たず成功を収めることとなった。
「え、これが貴之の部屋?」
あかねの驚く顔に、しまったと貴之は自分の額に手を当てた。
階下では、シエルが台所の片付けや風呂の準備、はてはあかねのパジャマまでを用意するなどと張り切っている。あかねも手伝おうとしたものの、お客様はゆっくりしていて下さいとはねのけられ、結果、こうして貴之の部屋へ押し込められている。
「想像してたのと違うなぁ。あたしんちではいつも綺麗に整頓しろーって小言ばっかり言ってるのにねぇ?」
あかねの咎め立てるような眼差しが貴之に突き刺さる。彼の部屋は先ほどのゲーム大会が行われたときのまま、お菓子や雑誌、飲みかけのペットボトルが散乱していたのだ。
「……言い訳させてください」
「えー、どうしよっかなー。貴之って言い訳するような男じゃないはずなのになー」
最近貴之に主導権を握られっぱなしだったあかねが、活き活きと目を輝かせる。
まるで昔に戻ったかのようなあかねの笑顔に、貴之は懐かしさを感じた。
あかねはこういう表情をしているべきなのだ。いつだって、あかねが笑っていられるように、そのために貴之は彼女を守っているのだから。
あかねがこの笑顔を取り戻す事ができた今日という日が、彼女にとっていかに大切な日であったかを今更ながらに貴之は噛み締めた。
「まぁ、座れない事はないから……どうぞ」
「ふふーん、んじゃベッドにドーン!!!」
本来の主人である貴之を差し置き、我が物顔のシエルに不正占拠されていたベッドは、あかねの有無を言わせぬ豪快なダイブで再びその利権を奪われた。
「うわ、何するんだよ! 埃が舞うじゃないか!」
「なーに姑みたいな事いってんのよー」
ケラケラと笑うあかねに、貴之の心も晴れ晴れとしたものへと変わっていく。
「そっかー、ここが貴之の部屋かー……」
大の字になり寝転がるあかねを傍目に、自分の椅子に腰掛ける貴之。
「ごめんな、汚くて」
「ふふっ、いいよ。許してあげる。どうせ散らかしたのは丘村なんでしょ?」
「そう思ってくれるなら助かるなぁ」
あかねは寝転がったまま貴之へ顔を向け、ニタァと笑いながら意地の悪い質問を投げかけた。
「……ねぇ、なんでそんな離れたところに座るの?」
彼女が自分のベッドで寝転がっている。たとえ階下に由美やシエルがいるとしても、少しぐらいなら恋人らしい事ができなくもない。だが、彼の自制心は、そんな安易な誘惑に負けることはなかった。
「ご両親に顔向けできないような事、今の僕がすると思うか?」
ニヒルな笑みで大人の対応を決め込む貴之に、再びあかねが意地の悪い顔をして笑った。
「そんなに自分に自信があるなら、別にこっちきてもいいんじゃないの~」
あかねはゴロリとうつぶせになると、肘をつき両手で顔を支えるような体勢になる。
「ぐっ……やめろよ、結構危ないんだから、こっちは」
首を傾げて誘うように微笑むあかねから、貴之は慌てて目を逸らした。
そんな貴之の反応を見て少々苛めすぎたと思ったのか、あかねはごめんねと舌を出して、今度は屈託なく笑った。
「大丈夫、貴之が何もしないの知ってるから。だからあたしもこんなに無防備でいられるんだよ?」
彼らは今までも、あかねの自室で何度となく二人きりで過ごしてきたのだ。チャンスはいくらでもあった。それでも貴之の中では、あかねを大事に思いやる気持ちが邪な気持ちに負けることはなかった。その結果が今の状況である。
あかねの心が立ち直るまで、あかねが自分自身から心を開いてくれるまで、貴之はその障害になるものすべてに抵抗すると決めていた。勿論それは自分自身の欲求に対してもだ。
「でもね……今日、あたしはだいぶ立ち直ったかもしれないの。ちょっと油断しちゃったのかな?」
あかねにも貴之と同じように悩みがある。もし貴之とナァナァな恋人生活に浸ってしまえば、本当にダメになってしまうと思っているのだ。あかねにとってそれは絶対に避けなければならないことだ。
もし幸せの意味合いを勘違いしてしまったら、あかねは凪に合わせる顔がなくなってしまう。
自分をどんな時にでも信じてくれた、かけがえのない親友、三咲凪を裏切る事になってしまう。
だから、あかねは今の自分がどのように生きていくべきか、それに答えを出すまでは貴之に甘えないと心に誓っていたのだ。
自分の心がどこへ向かうべきかをまだ見つけられないあかねだったが、今日、月島円と話せたことはたまらなく幸せな事だった。今の自分に出来る事は何か、円は断片的とは言えあかねに教えてくれたのだから。
貴之の枕に顔を押し付けてあかねは再び語りだす。
「月島さんと話してね、あたしわかったことがある」
「……ん?」
今までより少し真剣みを帯びたあかねの声が貴之へと届く。
「あたしね……、もう活発でも姐御肌でも優等生でもなんでもないあたしだけどね、やっぱりみんなと一緒にいたい。それでね、凪と……凪と貴之、三人でまた一緒にいたいの!」
あかねは枕を抱きしめ身体を起こす。
目を輝かせるあかねを貴之は黙って見つめた。その吸い込まれそうな瞳に、かつて見たあかねの光の部分を感じたのだ。
「クラスでも演劇部でも、いま凪の周りにはたくさんの人がいる。でも、今のあたしには貴之だけ。あたしが本当に心を許してるのは貴之だけなの」
「そんな事は……お前はクラスのみんなに人気があったじゃないか」
あかねは貴之の言葉にブンブンと首を振り否定する。
「ごめん、イヤな子だと思ってくれて構わない。あたし、みんなの事全然気にしてなかった。あたしの目に映るものは、貴之と……凪だけだったの」
「……」
貴之もそのことには気がついていたが、それをあかねの口からはっきりと聞かされる日が来るとは思っていなかった。
活発で姐御肌で優等生の天ヶ瀬あかねという少女。それはあかねが凪の目により良く映るために作り上げた虚像だ。周りの誰からもあかねは愛されていると、凪とそしてあかね自身が錯覚するよう演じていたに過ぎない。
いつだってあかねは、凪を通して世界と向き合って来た。いやそうしなければ向き合うことができなかったのだ。
あかねは、偽りの姿とはいえ完璧な人間を演じていたからこそ自分には居場所があった、と考えている。世間はあかねが思うほど彼女に冷たいわけではないのだが、そんな虚像を捨て去った今、自分には居場所はなく、貴之以外には誰にも受け入れてもらえないと思い込んでいる。
「あたし、凪ではなくて貴之を選んじゃった時に気が付いたの。ああ、あたしっていままでどうやって生きてきたんだっけ? これからどうやって生きて行ったらいいんだろうって」
枕に顔を押し付けたあかねは恥ずかしそうに身を縮める。
「だって、かっこつけてる完璧なあたしよりも、貴之は、かっこ悪いあたしの方を肯定しちゃったんだもの。貴之はあたしが元々かっこ悪いこと知ってるんだ。いつだってかっこ悪いあたしを好きでいてくれるんだ。それってすごいと思うの」
愛おしそうな眼差しで貴之を上目遣いに見つめるあかね。
「お、お前なぁ。そんな事言われると……色々と困るだろう」
貴之は顔を真っ赤にして飲みかけのペットボトルに手を伸ばす。一気に飲み干した炭酸水で咽がヒリヒリとしたが、その感触はなんとなく心地よかった。
「でもね、やっぱり凪やみんなにはかっこ悪いあたしを見せたくなかったの。そんなあたしは誰も受け入れてくれないんじゃないかって怖かった。それで無理して前みたいに振舞おうとしたけど……やっぱりダメだったよ」
辛い想いを告白しているはずなのに、あかねの口調は何故か軽快だ。
「ダメだったかー」
あかねの明るい雰囲気につられて、貴之も笑顔でそれに応えた。
「うん、ダメだったの。だから、こんなかっこ悪いあたしは貴之と二人だけで居られさえすればいいやって思っちゃった。そうすれば他の人にかっこ悪いところ見せなくてもすむしなーって」
「ははっ、おまえと親しいヤツは、おまえがかっこ悪いって事、わかってるんだけどな」
「うん、そうなんだけど……それは今までの優等生として生きてきた者の意地なんですよ」
あかねは枕をそっと下ろすとベッドの上で正座をした。
「でも、でもね。今日月島さんが友達になってほしいって言ってくれたの」
ふぅと息を整えると、あかねは満面の笑みでベッドの上に立ち上がった。
「このバカみたいにかっこ悪いあたしとね! 友達になってくれるんだって!」
「……そっか」
「もう物語も書かない、成績だってよくない、ご飯だってまともに作れないあたしがね……! 友達を作ったんだ!」
「いや、おまえ、自分の事過小評価しすぎだろう」
彼女のこの自己評価の低さは、誰から見ても不思議だろう。しかし、それは完璧な人間を演じてきた事への反動である。あかねの悩みは、他人からは中々理解されがたいものだった。
だが円と出会ったことで、あかねは自分の価値を、自分の幸せが何なのかを見つけ出そうとしている、
あかねはさらにまくしたてる。
「あたしね、月島さんの言う通り、凪やみんなが幸せになれれば、自分はどうなってもいいって思ってた。嘘の自分でみんなに接してたあたしが、今更みんなの輪の中に入るなんて出来ないし。貴之と一緒にいられさえすればあたしは幸せだ。そう思ってた、思おうとしてた。でも違った。あたしは寂しかったんだ」
あかねは、ベッドから降りると貴之の前に立つ。
「あかね……」
「今日はね、あたし、月島さんのおかげでね、こんなにかっこ悪いあたしでもみんなと一緒にいたいなあって、思えたんだ」
嬉しそうなあかねの瞳から一滴の涙がこぼれる。
「おまえなぁ、最近、泣きすぎだろう」
「うん、でもこれは嬉しい涙なの。だから…、うん、ノーカウントね!」
そうだな、と優しく貴之は右手をあかねに差し出した。
「改めて言うよ。かっこ悪いあかねを、僕の自慢の彼女だってみんなに紹介してもいいかな? 妄想癖があって、乙女趣味こじらせてて、ご飯作るのも下手で、すぐ泣くし暴力的だし、あんまりいいところないけど……」
「うん! そんな風に紹介して欲しい! こんなあたしだけどみんなと一緒にいさせて欲しい。そして貴之の隣に立ってたい!」
差し出された貴之の手を握り締め、はにかむあかねに、貴之も笑顔で頷く。
しばらくの間見つめ合ったあと互いに照れ笑いを浮かべると、二人は握り締めていた手を名残惜しそうにそっと離した。
「だぁぁぁあああ!!健全すぎんだろう!!?」
「なっ!?」
「えっ!?」
バタンと大きな音がして扉が開くと、そこにはシエルが般若のような顔付きで仁王立ちしていた。
「あんたらいい加減にしろよな!?お茶会の準備が出来たと知らせに来たついでにこっそりのぞいてみりゃ、この体たらく!高校生ならキスぐらいまでとっとすませんか!せっかくわざわざ二人っきりになれる時間を作ってやったというのに!」
シエルの豪快な鼻息が静まり返った部屋にフンスッと響いた。
あまりの出来事に硬直していた二人だったが、いち早く状況を理解した貴之が慌てて立ち上がり、シエルの元へと歩み寄る。
「お、おお、おま、おまえ、聞いてたのかよ!?」
「うっさい馬鹿!ヘタレ!死ね!」
聞く耳を持たないシエルは、抗議をする貴之の顔をむりやり横におしやると、キッとあかねをにらみつけた。
「天ヶ瀬先輩っ!」
「はいっ!?」
「なんて勿体無いことしてんすか!せっかくの大チャンスだったのに!!手を離しちゃうとかないっしょ!!!」
「あ、は、はい! ……は、はい?」
シエルの言葉の意味はまるで理解できていなかったものの、勢いに押されてあかねは素直に返事をした。
そんな様子をみたシエルは、プッと一度吹き出す。
「ああもう。天ヶ瀬先輩は、その素直で押しに弱いっていう自分をもうちょっと客観的に見たほうがいいですよ?」
「え、それってどういう……」
シエルは、ハテナ顔のあかねの手を取る。
「任せちゃおけないから、私がとっておきの作戦を伝授してあげます」
「はぁ!?」
いいからいいから、とあかねを引っ張り部屋から連れ出そうとするシエル。
「お、おい、待てよ、僕を無視するなよ!」
貴之が再びあかねの手を取り、自分の元へと引き戻そうとする。
「む!タカユキのくせに生意気な!」
「こんなわけのわかんないことで、僕らの時間を邪魔すんなよ!」
「馬鹿!あんたらだけじゃ話にならないからだよ!ストイックなのはいいけど、限度があるだろう!」
大体の事情を察したあかねも、顔を真っ赤にして叫んだ。
「痛い痛い!!な、なんなのよこれ!!!!」
まるで大岡裁きのように二人に手を引っ張られるあかねの姿を、ドアの影に潜んでいた人物がニヤニヤと見ていた。
「面白いから写真でもとっておくかね」
いつの間にかシャッキリとした表情になっている由美は、ケータイのカメラを構えると軽快なシャッター音と共に騒ぐ三人の姿を記録した。
「ロイヤルミルクティー?」
「はい、ミルクティーじゃないですよ。ロイヤルミルクティーです」
再び今日何度目かの相馬家台所。あかねの戦いは第二ラウンドへと突入していた。
シエルから手渡された茶葉の瓶を、両手で包み込むように持ちまじまじと見つめるあかね。
「ロイヤルってことは王室って意味だから、結構お高い紅茶ってことだよね」
「そうそう、お高い……って、え? そうなんですか?」
自信満々にミルクティーとロイヤルミルクティーの違いを説明するつもりのシエルだったが、完全に出鼻を挫かれ、逆にあかねに問い返す形になってしまった。
あかねから茶葉の入った瓶を受け取ると、シエルはラベルの説明などを見て回る。が、そこには王室云々などという説明はない。唸り声と共にシエルはさらに続ける。
「そういや、ファンタジー漫画とかに出てくるなんとかロイヤル騎士団とか、あれも王室って意味ですよね。そっか、王室の紅茶って意味だったんだ」
「はぁ……」
「じゃ、王室ではなんでミルクティーを好んだんだろ? 別にストレートティーでも良かったのに」
「そうだね、なんでだろ?」
「ひょっとして、ミルクなしでは飲めない茶葉とかつかってたのか?」
「うーん……どうなんだろうね」
やけに真面目に考え込んでしまったシエルとのやりとりを交わしながら、あかねは若干後悔していた。どうやらシエルは、一度でも疑問を感じると解決するまで前には進めないタイプのようだ。このままでは話が進まない。と、そんな折り、
「いや、まぁ、そこは考えなくてもいいんじゃないかなー。ねぇ、あかねちゃん?」
カウンターごしにテーブルの席で二人を見守っていた由美が、あかねへと助け舟を出した。
「そ、そう! おばさんの言うとおりです! 雨宮さん、ここはそういう知識の話じゃないから!」
「お、おう、そうですよね!」
あかねとシエルは「アハハッ」と乾いた笑い声をあげる。
「もう、あかねちゃんったら。おばさんなんて堅苦しいなぁ、別に名前でいいのよ?」
「い、いえ、さすがにいきなりそういうわけには……」
困り顔になりモジモジとしながら声が小さくなっていくあかねに、由美はご満悦の表情を浮かべた。
あかねとシエルのやり取りは、シエルと円の子供時代を見るようだ。今でこそ姉妹のように仲のいい彼女達にもぎこちない時期はあったのだ。そう、今まさに目の前で繰り広げられているように。あかねとシエルを見て懐かしさを感じた理由はそこにあるのかもしれない。
由美はお茶請けにと用意したクッキーにパクリとかじりつく。そのクッキーは円の手作りだ。
円のクッキーを食べながら、貴之が初めて作った彼女の紅茶を飲む事になるとは、さすがの由美にも考えもつかないことだった。
――ああ、ひょっとしたら、貴之がこの子を選んだのは結局そういう事なわけ?
色恋沙汰が大好物な由美は、我が子の恋愛事情をシミュレートしながらほくそえんだ。
罪作りというか、これが運命だというのか。
呆れてしまうが、不思議とすんなり受け入れている自分もいた。
貴之達が納得しているのだ。親の自分が口出しするべきではないことも承知していたし、そもそも子供達の恋愛事情に首を突っ込むほど、由美は野暮な性格をしているわけでもなかった。
なんにしても、今こうして目の前で起きてる事実は、貴之なりに起こした奇跡なのかもしれない。
由美は一刻も早く、出張中の旦那にこの出来事を面白おかしく報告したい気持ちになっていた。
「でまぁ、あんたらさっさとしないと貴之が風呂から上がっちゃうわよ」
「おっと、そうだった……」
由美の忠告を受け、シエルは再びあかねへと真剣な眼差しを送る。
「タカユキが出てきたらこれを飲ませましょう、天ヶ瀬先輩。私の計画の為にもファイトです!」
「お、おー……?」
ガッツポーズで意気込むシエルに、あかねも力なく拳を振り上げた。
時刻は二十三時を軽く回ったあたり。さすがにこんな時間から甘いものを食べるなど、あかねとしては遠慮したいところだったが、どうやら相馬家では日常的な事であるらしい。委細構わずクッキーを食べ続ける由美を見ながら、まぁ、二、三枚なら太りもしないか、などと考えるのであった。
それに、どうしてシエルは自分をここに泊める気になったのか。何故、ロイヤルミルクティーを作ろうなどと言い出したのか。その疑問を解決する為には、彼女なりのダイエット事情があるにせよ、クッキーの十枚くらいは覚悟しなければ、とあかねは思った。
「というわけで、天ヶ瀬先輩。まずはこれ、どうぞ」
シエルから小さな手持ち鍋を受け取ったあかねは、これでお湯を沸かすのかと首を傾げる。台所のカウンターには、電気ケトルが置かれているからだ。
あかねの不思議そうな顔を見て、今度こそとドヤ顔になったシエルが再び説明を始める。
「ロイヤルミルクティーはミルクで茶葉を煮出して作るんです。ようするに一煮立ちさせるってことですね」
「ちなみに、そうやって作る紅茶をチャイって言うのよ~」
水を差すかのように由美が茶々を入れる。
「え!? ロイヤルミルクティーじゃないの!?」
「そうよー、シエルちゃんの思ってたミルクティーは、実はチャイティーなのだった!」
「お、おばさん!? 雨宮さん、違う、違う! そういう話じゃないから! 作り方の話だから!!」
貴之達からしてみればまるで全てをお見通しかのようなシエルも、由美にかかればまだまだ弄り甲斐のある耳年増のちょっとませた子供にすぎない。ふくれっ面で「なんで今まで教えてくれなかったんだ」と文句をいうシエルは、あかねから見ても新鮮な姿であり、つい吹き出してしまう。
「雨宮さんって、そういうところもあるんだね」
「あー、そりゃまぁ、私もまだ高校一年生のクソガキなんで……」
不貞腐れるシエルを見ながら、彼女とのコミュニケーションはひょっとすると女の子同士のものではなく、貴之と話す時のような言葉使いのほうがしっくり来るのではないかと、あかねは直感した。
「うん、で、そんなクソガキの雨宮さん。早くあたしにチャイじゃなくって、ロイヤルミルクティーの作り方を教えてくれないかな?」
少しづつではあるが、シエルの事を分かり始めたあかねは少々言葉を崩してみた。するとシエルはニヤリと笑うと、あかねの空いた手に計量カップを押し付けた。
「ふふん、言いますね天ヶ瀬先輩! 私は円と違ってスパルタですよ!」
「おお、望むところだ!」
「私が天ヶ瀬先輩とタカユキのために、最高のお茶と時間をプレゼントしますから! しっかりついてきて下さいよ!」
シエルの熱気に便乗するかのように、あかねも「オー!」と勢いよく返事をする。
右手に鍋、左手にカップを持ち、フル装備状態になっているあかねの様子に、由美も思わず声をあげて笑ってしまっていた。
長い前哨戦を終え、今度こそあかねの戦いの火蓋はきって落とされたのだった。