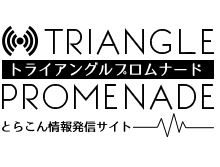『Tea for Two』 #00/01 *天ヶ瀬あかね編
#00/01「わかってる……わかってるんだけどなぁ……」

――#00
「わかってる……わかってるんだけどなぁ……」
彼女はそう呟きながらベッドの上にゴロンと寝転がった。握り締めたケータイはもう何時間もメール着信ランプが点滅し続けたままだ。真っ暗な部屋の中、少々古臭くなった学習机の上でつけっぱなしのノートパソコンのモニターだけが煌々と輝いている。
「ん、もうこんな時間か……」
時刻は深夜二時。
長い黒髪を無造作にまとめていたゴムをほどきながら、寝返りをうち顔を起こすと、暗がりの中、立てかけられた姿見に映った自分の顔が目に入る。少し幼さは残っているけれど、それなりに整った顔立ち。……自分でいうのもなんだけど、ちょっとかわいいよね。ぼんやりとそんなことを考える。
しかし口をついて出た言葉は、そんな思いとはまるで正反対のものだった。
「酷い顔……」
鏡に映った表情は、悔しいような、或いは怒っているような。泣きたいのに泣けないような。自分自身どうしていいのか分からない表情。もっと簡潔に言うならば感情のぶつけどころを失って戸惑っている顔だ。

「ダメだダメだ! こうやってすぐにヘコんじゃうからアイツに余計な心配かけてるんじゃない……!」
枕を手繰り寄せるとそれを抱きしめ、自分自身を叱咤する。洗濯したての枕カバーは太陽の香りがして、それに顔を埋めているとほんの少しだが冷静になれた。
大きく深呼吸をして、ケータイを開く。メールの一覧を表示すると、そこには新着メールが三件。送信者は相馬貴之。二時間ごとに送られてきていた。
わざわざ時間を開けてメールを送ってくるあたり、いかにも彼らしいなと彼女は微笑んだ。
悪いのはあたしの方なのに。そう思いつつ、彼の気遣いに一向に応えようとしない自分への失望が、再び彼女の心を闇に染め上げ、笑顔は次第に重い表情に引き戻されてしまう。
――メールを開きたくない。
メールを開いてしまったら、必ず彼の優しさに触れる事になる。そうなれば間違いなく、私はまた自分を責めることになるのだろう。
昔も今も彼に甘えてばかりだ。些細なことにも嫉妬して罵倒し、軽い冗談のようなセクハラに手をあげ、いつも傍にいてくれる彼を突き放し続ける。それもこれも彼の前ではいつも元気な姿でありたいと思う身勝手さのためだ。明日の自分が笑顔で彼と接したいという我侭のためだ。
あたしは貴之の事が大好き。彼がいない人生なんか絶対にイヤだ。それなのにまたこんな事して……。つきあい始める前と何ひとつ変わっていない自分の脆弱なメンタルに反吐が出る。
気がつくと彼女の目からはぽろぽろと涙が零れ落ちていた。
「ああ、やっと……」
自分の不甲斐なさで泣けた事で彼女は少しだけ表情を緩めると、ゆっくりとケータイを折りたたみ、パソコンの電源をオフにすることもなく毛布にくるまる。
明日、彼の顔を見て直接謝ろう。どうせメールを見ても見なくても自分を責めることに変わりはないのだ。そう理解していながらも、五時間近くも悩んでいた自分が本当に滑稽だった。きっと夢の中では理想とする自分が演じられるはずだ。そんなことを思いながら、彼女は深い眠りについた。
深い藍色の瞳を持つ大きな目。筋肉質ではあるが細くしなやかな身体に、黒髪のポニーテールがトレードマークの快活な女の子。豪快さと気立てのよさを兼ね備えた性格は、姐御として女子はもちろん多くの男子からもから絶大な支持を受けている。さらに成績は勉強スポーツ共にトップクラス。教師からも一目置かれる生徒。そんな優等生を絵に描いたような存在、それが港北大付属一乃谷高校二年、天ヶ瀬あかねだ。
そう、二ヶ月前までは。
彼女のアイデンティティは、十七歳の秋にガラガラと音を立て崩れ落ちた。いや、彼女自身が捨て去ったというのが正しいだろう。
今や、クラスメイトに心配をかけ庇護される存在。学校はサボりがちで担任教師を悩ます問題児。あかねは”今までの自分”と”これからの自分”のギャップに悩み、些細な事でも心が揺れ動くか弱い少女となっていた。
そんなあかねが初めて迎える冬。ちょっとした事件が起こったのだった。
――#01
私立港北大付属一乃谷高校は、嵩鳥(たかとり)町全般に広がるなだらかな斜面の中腹に位置している。
比較的緩い校則や、田舎特有ののんびりとした雰囲気を持ち、進学校でありながらも数多くの季節行事が目白押しという、少々風変わりな私立校だ。そのイベントの多さや、可愛らしい制服を目当てに入学をする生徒も珍しくなく、生徒の半数は青春を謳歌するために一乃谷を選んでいるといっても過言ではないだろう。それを大目に見てしまう校風もまた、人気の秘訣と言ってもいい。
秋にしては肌寒く、真冬というにはまだ暖かな十一月下旬。
ここ嵩鳥では、年末に向けて慌しく動く人々が徐々に増え始めていた。そんな街とは反対に、中心部から少々離れた場所に佇む一乃谷高校では、年内最後のビックイベントである文化祭も終了し、比較的静かな時が流れている。
二週間後には期末試験も控えており、校内にはだんだんとぴりぴりした空気が漂い始めていた。だがそこはそれ、自由な校風を持った学校である。それなりに賑やかなのは自然なことだ。殊に昼休みの食事時は、こんな時期でも生徒たちが唯一気を抜ける時間帯とあって、その騒々しさは教師達が少々頭を痛める程である。
「いいじゃねーか、相馬。たまには俺にもその弁当食わせてくれよ~!」
「これは僕だけが食べる事を許された弁当だから。どこの誰にもあげるわけにはいかないな。もちろん丘村にもだ。何度も言うけどお断りする」
昼休みの教室では、今日もコントのような予定調和的な会話が飛び交っている。この男子生徒二人の会話も例外ではない。
「普通彼女のお弁当は独り占めするわよね。ねー、相馬君?」
「そうだぞー、ラブラブな二人の仲を引き裂こうとする丘村は地獄へ落ちろー」
三つほど席が離れたところに座り弁当を食べていた女子一団から、からかいの混じりの罵声が飛ぶ。「ですよねー」と貴之は女子たちに笑いかける。
「だいたい、彼女のお弁当を人にあげるとか絶対にないとは思わんか?」
貴之は庄治にドヤ顔で答える。これがリア充の顔だと言わんばかりのドヤ顔である。貴之は勝ち誇った顔で再び肉そぼろを口に運ぶ。庄治には、弁当が平らげられていく様を眺めている他に術はない。
「ちくしょー! なんで俺ばっかりこうも悪者に! ちょっとぐらい食わせてくれてもいいのに……!」
庄治は腹立ちまぎれに食べ終わった焼きそばパンの袋を握りつぶした。
相馬貴之と丘村庄治は、親友とまでいかないにしろ一年生の頃からつるんでいる腐れ縁とも言うべき悪友である。
幼馴染に女の子が二人もいて女性関係に恵まれすぎたせいか、逆に恋愛ゴトに首をつっこまない貴之。一方リアルな恋愛よりもアイドルの追っかけが好きで、気の置けない男友達とつるむ方が楽しかった庄治。二人は相性がよかった。
二年生になり、演劇部とかかわるようになった貴之は、三咲凪とその親友である天ヶ瀬あかねと一緒にいることが多くなった。自然、腐れ縁の悪友もその輪に加わるようになる。貴之と庄治が馬鹿話で盛り上がり、あかねにどやされる。それを傍らでおろおろしながら見守る凪。そんなありふれた日常の光景は、庄治にとっても心地のよいものだった。
しかし、あかねの登校拒否事件を境に様相は一変する。
優等生のあかねが学校に来なくなったのは、九月前半からだった。そして十月に行われた文化祭に姿を現したあかねは、全く別人であるかのように大人しくなっていた。そればかりか、あかねと貴之はつきあい始めたのだという。
登校拒否になる前のあかねは、バカな事ばかり口走る庄治達男子をよくたしなめていた。しかし今のあかねは男子に対して怒声をあげることも少なくなり、女子の中心に居るようなカリスマ性もなくなっていた。あかねのあまりの豹変ぶりに、貴之とあかね、そして凪の間に何があったのか、誰もが興味津々ではあった。が、それを直接聞こうとするような度胸ある生徒は現れなかった。
庄治は文化祭最終日に貴之に連れられて教室に現れたあかねを思い出す。その日あかねが学校に戻ったのは一ヶ月ぶりの事だった。あかねは一回り小さくなったかのように見え、その変わり様に庄治は驚きを隠せなかった。あかねに抱きつき泣き出す女子もいれば、おかえりと優しく接する男子もいた。
「心配をかけてごめんなさい」肩を震わせながら精一杯の声で、皆に詫びた彼女。あかねは傍らの貴之の手を握り締め、貴之もその手をしっかりと握り返す……そんな二人を凪は少し離れて見守っていた。
貴之は昔と変わらないようでやはり雰囲気が違っていた。どこか大人びてもいる。あかねや凪もそうだ。自分が知らないところで起こった何かで、彼らの関係が大きく変わってしまった。
その光景を目の当たりにした庄治は複雑な思いだった。いったい何があったのか、気にはなるものの、それについて詮索するつもりもなかった。ただ、昔のような関係にはもう戻れないかもしれないと感じていた。
椅子に深く腰掛け、天井を眺めながら残り少ない珈琲牛乳をストローですする。
「ダッセーな、俺……」
「ん? なんか言ったか?」
貴之が聞き返してきた。声が大きすぎたかと内心舌打ちをしながらも、いつものおどけた表情を作ると、なんでもないと庄治は答えた。
「あ、あかねー、おかえりー」
一人の女子の声にクラスの面々が振り向く。職員室からあかねが帰ってきたのだ。
「昼休みに職員室に呼び出しを食らうとか、なんか親近感湧いちゃうね~」
「小林先生はちょっと話しつこいよね」
「おう、天ヶ瀬。彼氏がお待ちだぜ」
あかねはクラスメイト達からあれこれ声をかけられ、困ったように笑いながら、貴之と庄治の座る席へとやってきた。
「あれ? もう食べちゃったの?」
「冷めると不味いからな」
「おいおい。最初から弁当は冷めてるじゃねーか……」
昔と何ら変わらない会話だ。ただあかねの隣には、いつもそこにいたはずの凪がいない。
凪はいま、庄治や貴之たちではなく別の女生徒たちと弁当を広げている。
「あ、あかねちゃんおかえり! だ、大丈夫だった?」
少し離れた窓際の席から手を振る凪に、「自業自得だから、仕方ないよ」と苦笑しながら応えるあかね。庄治はこの構図にまだ慣れる事ができずにいた。
――仲が悪いわけじゃない。確かにあかねと凪の関係は昔とは違うが、悪いほうに転がった感じはしない。それはそれでいいじゃないか。
あの心地よい毎日は失われたが、それは仕方のないことかもしれない。庄治は一人だけ取り残された様な気がして不機嫌になっている自分は一体なんなんだと、少し可笑しくなった。
「よっこいしょっと……」
「オバサン、腰大丈夫か」
ツッコミを入れる貴之。フンと口を尖らせて自分の弁当を開けるあかね。
すっかり弱々しくなってしまったあかねだが、それでも貴之に対してだけは以前の通り元気一杯に振舞っている。
「全く毎日毎日、夫婦漫才すなー」
「あんたらだってベテラン芸人コンビみたいなもんでしょ」
ニヤけ顔であかねをからかう庄治を眺めながら、貴之は小さく安堵のため息を漏らした。
貴之は、あかねの周りの人間がこれまでと変わらない態度で彼女と接することを望んでいる。貴之本人も、あかねを気遣ったり、守ったりしているそぶりを見せないように気をつけているのは言うまでもない。
あかねには、自分が周囲の人々に気を遣わせているという自覚がある。その気遣いを過度に意識してしまうようなら、それは彼女にとって大きな負担になってしまうだろう。
そんな負担を感じさせないよう、彼は今、あかねを最上級と表現しても良いほどに甘やかしている。
十年以上も歪な生き方をしてきた彼女は、計り知れないほどのフラストレーションを溜め込むこととなった。
自分ではどうすることもできない感情を持て余しているあかねが本当の自分をみんなの前でさらけ出すには、まだまだ時間が必要だろう。当然だが今まで通りにはいかない。
それまでは、気持ちに波風を立てるようなことはできるだけ避けてやりたい。今の貴之の想いはそこにある。
一方、凪はあの一件以来強くなった。あの気弱で臆病だった小柄な少女には、もはやあかねの助けは必要ないのだろう。いや立場は逆転している。今や、あかねにこそ凪の力が必要なのだ。
しかし今のあかねは自分の事で精一杯で、凪の助力すら負担に思ってしまうだろう。凪もそれを理解しているからこそ、こうやって距離を置き、静かに見守っているに違いない。
凪もそう思っているのだろうか。彼女に真意を確認したいという気持ちはあるものの、あかねを選んだ自分にはそこに踏み込む資格がないと感じていた。
「なー、天ヶ瀬。相馬が全然お弁当わけてくれないんだよ、酷くね?」
「しょうがないなぁ、んじゃちょっと食べてみる?」
あかねはピーマンの肉詰めを弁当の蓋に乗せて庄治へと手渡した。
「最近貴之も褒めてくれるんだよ」
「そうなんだよなぁ。天ヶ瀬、昔弁当作るのすげぇ下手だったのに。いただきまーす」
「ふふん、味わって食すがよいよ」
それを口にいれた庄治はさっきまでの勢いはどこへやら、完全にその動きを止めている。
凪の方を見ていたせいで、あかねと庄治のやりとりに注意していなかった貴之は、その光景を見て青ざめた。
脂汗をかきながらフリーズ状態の庄治は、目だけをキョロキョロさせて貴之に何か訴える。不思議そうにするするあかねに気付かれないよう、貴之は表情と小さなジェスチャーで庄治へと返事をした。
「う、うまい。マジで、予想以上……」
絞り出すようにやっとそれだけを言った庄治に、あかねは「でしょー」と、満足そうに答えた。
――NEXT#02