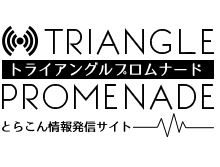『Tea for Two』 #02 *天ヶ瀬あかね編
#02「うん、優しすぎてさ……ちょっと辛い」

――#02
天ヶ瀬あかねは味の感覚が大層ズレている。
元々彼女の家庭の味付けは濃い。幼い時分から慣れ親しんだその味こそが普遍的な味だと、あかねは信じていた。
小学生の頃、給食や外食などの味付けをいつも物足りないと感じていたあかねは、どうしてみんなはこんな薄味を好むのだろうと不思議で仕方がなかった。
中学一年生の春、家庭科の授業で作った味噌汁が彼女の疑問を解決した。
その日あかねが作った味噌汁は、彼女にとって会心の出来というべきものだった。しかしそれを口にしたクラスメイトの苦笑いを彼女は忘れてはいない。その味付けは、あかね以外の者には耐え難い塩辛さだったのだ。
それまで何でもそつなくこなしてきた彼女にとって、人よりも劣っている事が、まさか自分にとって自信があった料理だとは思わなかった。以来、あかねが他人に食事を振舞う事はなくなった。
それから五年。
あかねの料理の味付けが破綻していることを知りながら、彼女自身の手作り弁当を望むものが現れた。あかねの初めての彼氏である相馬貴之だ。
あかねは嬉しかった。
冷凍食品や、出来合いの惣菜に頼る事なく、自分自身で料理を作れる事が嬉しかった。
貴之のアドバイスを聞きながら味を調整し、この一ヶ月間、毎日のように弁当を作った。あかねにとっては薄味だと思うおかずだが、一般的にはこの味が正解のようであり、ここ数日は貴之から注文をつけられる回数も減っている。
美味しくなってきた、そう笑顔で応える貴之の顔をあかねは何よりも愛おしく感じた。自分の料理を美味しく食べてくれる人がいる。それはなんと幸せな事なのだろう。
「しばらくは、僕が独り占めするからな!」
貴之はそう言っていたが、早くいろんな人に自分の料理を食べて貰いたい。そして自慢の彼女だと言われたい。あかねはそんな事を夢見るのだった。
一ヶ月以上も授業をサボっていたあかねは、居残りで補習を受けることが多い。
日が落ちるのが早い季節、下校時刻を過ぎてなお、ダラダラと時間を潰すような酔狂な生徒は少ない。今この食堂に居座っている者もほんの数人だ。
ここ数週間、補習帰りのあかねと下校する為に窓際のテーブルを占拠する貴之は、閑散とした食堂の主と言っても良かった。
定位置に座り、一人で静かにあかねを待つ時間は貴之にとって中々に居心地の良い時間だ。
しかし、今日は目の前に教室でイヤという程顔合わせている庄治が座っている。なぜなら貴之には、昼休みの件でどうしても彼に頼んでおかなければならない事があったからだ。いつものような気楽な気分でいるわけにはいかなかった。
「……というわけだ」
貴之は説明を終え、テーブルの上で組んでいた両手を離すと、身体を背もたれに預け肩の力を抜いた。
「ああ、うん。つまりあれだな? 天ヶ瀬の作るメシは、本当はまだ全然美味くないって事だな?」
庄治が呆れた表情で、話を簡潔にまとめた。
「美味しくないっていうなよ。せめて味付けが濃いと言ってくれ」
自分の彼女を馬鹿にされたのが癇に障ったのか、貴之は不機嫌に返事をする。
「いや、あれはどう言いつくろっても不味い。で、何も知らない俺がそれを食う羽目になったのもお前が悪い。そもそもお前らバカップルの内輪ネタで被害にあった俺の気持ちわかる? てか、リア充爆発しろよ」
「バ、バカップルって、そんな事ないと思うんだが……そんな風に見えるか?」
「くそっ! 見えるから怒ってんじゃねーか!」
庄治が微妙に話を脱線させ始めたが、そもそも自分に非があることを承知している貴之に彼を止める資格はない。庄治は被害者なのだ。ここは甘んじて彼の暴言を受けるしかない。
「……悪い、でも今の話はそういう事じゃなくてだな」
「だから、天ヶ瀬の弁当がそういうものだってことは他言無用って言いたいんだろう? くそ、面倒クセェ事に巻き込みやがって」
巻き込まれたというよりも、勝手に首を突っ込んできて自爆した、が正しい。貴之はそう考えながらも、コクリと頷いた。
「しかし、不味いなら不味いって言えばいいじゃねーかよ。なんでこんな回りくどい事してんだ?」
「それは……」
貴之は、沈みかけの夕日を見ながら彼女の顔を思い浮かべる。
あかねが初めて貴之の為に作った弁当は、普段の彼女の料理から少しだけ薄味に仕立てられた肉ジャガだった。
それはとても合格点を出せるような味ではなかったが、貴之の為にと多少でも自分のポリシーを曲げた彼女の心遣いが嬉しかった。だから酷く甘辛い肉ジャガの感想は「美味い」であり、それ以外の言葉は彼の口から発せられる事はなかった。
貴之に褒められた事で、あかねは自信を取り戻し始めている。いつかみんなに褒められる料理を作る。それが今の彼女の望みだ。だが、そうやってみんなの舌に合わせ続けていく限り、あかねが美味しいと思える味からは遠ざかっていく。自らを犠牲にしたあかねの笑顔は貴之にとって本意ではない。たとえ、あかねがそれで満足だとしても、それは貴之自身が許せない。
だから、ここでの貴之の答えも、やはり決まっていた。
「それは……あかね自身にも美味しいと思える料理であって欲しいからだ」
貴之は独り言の様にそう答えた。
その目は夕暮れの景色ではなく、まるで遠い未来を見ているかのようだった。
「まぁ、お前がそれでいいなら、それでいいけどよぉ。天ヶ瀬としてはどうなんだ? 結局なんだかんだ言っても、相馬が嘘を言ってる事には違いないんだぜ」
「それはわかってる。だから少しずつあかねの料理を改善していこうと思っていた。僕らが濃いと思う味、あいつが薄いと思う味、中間にすれば問題ないだろう?」
「…………ないけどさぁ」
――貴之の話は確かに理想的だが、そんな気の長い話に庄治は納得ができない。
そもそも、何故そこまでしてあかねの味付けを尊重するのか。お互いが好き勝手に食べればいいではないか。何が貴之をこうまで必死にさせているのか、そこがどうしても庄治には引っかかった。
「あのさぁ、お前がそこまであいつの料理に拘るわけってなんなん?」
「……答えたくない」
一瞬の間を置き、貴之はそう答える。腕を組み目を瞑る貴之は、これ以上は聞かないでくれと言わんばかりのオーラを全身から発していた。
わかり易いその拒絶の姿勢は全く逆効果で、庄治の好奇心に完全に火をつけてしまった。庄治はイヤらしく笑い、テーブルに肘をつき身を乗り出す。
「わかった。じゃ、さっきの話、天ヶ瀬にするわ」
「えっ!? ちょっと待てよ!」
貴之は慌てふためき、思わず椅子から立ち上がった。
「だってよぉ、お前人にモノを頼む態度じゃねーんだもの。あいつに黙ってて貰いたいなら、ちゃんと説明は欲しいと思うわけよ、俺は。一応被害者なわけだし」
「うっ、そう……だけど」
貴之は心底困った顔をしていた。調子に乗った庄治は、狼狽した悪友をさらに問い詰めにかかる。
「まぁ、俺には聞く権利があると思うけど? 何せこれからも黙っていないといけないわけだろ? 気を遣わないといけないわけだろう? なぁ、相馬くぅん?」
「ぐぅ……ちょっと待ってくれ……。その質問に答えるのは、正直かなり勇気がいるんだ……」
そう言いながら席に座り直す貴之は、心なしか顔が赤くなっていた。
「なんだ、エロい事に関係してるのか?」
「違う!!」
再び立ち上がろうとする気持ちを押さえつけた貴之は片手で顔を覆うとブツブツと何かを言い出した。そのあまりに面白い姿をニヤニヤと見守る庄治には、リア充共に振り回されてなるものかといういらぬ気迫が感じられる
「なぁ、相馬くぅ~ん?」
庄治の最後の一押しで、観念したかのように貴之は声を絞り出す。
「……あかねと僕が、これからずっと同じ食事を取るなら……その、なんだ、二人共満足する味がいいだろう?」
――おとずれる沈黙。
言葉の意味を理解できない庄治はハテナ顔で考える。それを見ていられなくなった貴之は、机の上に顔面を叩きつけ突っ伏した。
「……えーっとさ、それ天ヶ瀬と同棲とか考えてるって話? そうなのか?」
庄治は考えられる限りのリアルな路線で質問を返す。だが「違う」と突っ伏したまま頭を振る貴之を見て、大体の察しがついた。こみあげてくる笑いを抑え、震える声で庄治は追い討ちをかける。
「ぷっ、いやいや。いやいやいやいや……お前もう返事したようなもんじゃん。言っちゃえよ! 何があったん!? んんっ!?」
「…………い、一生、一緒にいる……って言った」
机に額を押し当てて、耳まで真っ赤にしながら貴之は答える。
想像通りの返答にとうとう庄治は笑いが堪えきれなくなり「ガハハハ」と大笑いを始めた。
食堂に残っていた数人の生徒は、そんな庄治を何事かと眺めるが所詮は他人事、すぐさまそれぞれ他愛のない会話に戻っていった。
「……そこまで笑わなくてもいいだろう」
「いやいやいやいや、これは笑いどころだろう! そっかー、あの天ヶ瀬とお前がねぇ。ぷぷっ……いやぁ、青春だなぁ! ここまでくると、リア充でも清々しいな!」
貴之はのそりと顔を上げたがその顔はまだ赤いままだ。ふんぞり返って再び腕を組むが、その視線は恥ずかしさの余り宙を漂っていた。
「こんな相馬が見られるとは思わなかったわ……くくくっ」
「うるせーよ! ほとんど脅迫だったじゃねーか!」
珍しく声を荒げる貴之を見て、庄治は昼休みに感じていた劣等感を吹き飛ばしていた。自分だけ取り残されたわけではない。今、目の前の貴之は子供じみた夢を語っている。勿論、この想いは本物なのだろう。そうでなければここまで普段クールな貴之が取り乱す事はない。
しかし庄治にとって嬉しかったことは、貴之が子供っぽい悩みをまだ持ち続けている事に対してだった。彼らが遠い人間になってしまったような錯覚。それが自分の勝手な妄想だと知り、安堵感を覚えていたのだ。
「おう、わかった! この庄治様が力の限り応援してやるぜ!」
親指をグっと立て、満面の笑みを浮かべる庄治。
「じゃ、お言葉に甘える。おまえ、これからあかねの料理を美味しいって言いながら食え」
「えええ!!!?」
あまりといえばあまりの提案に、またもや大声をあげる庄治だったが、周りの生徒はもはや我関せずといった様子である。
ようやく一矢報いた貴之は畳み込むように続けた。
「最近のあかねの料理を僕以外で食べた事があるのはお前だけだ。僕ら三人は最近一緒に食べることが多いからな。おまえがこれからもあかねの料理は美味しいと言えば丸く収まる」
庄治は、もう一緒に食べるのは止めたいと呟いたが、貴之に睨まれると身に危険を感じて冗談ですと答えた。
すっかり日の暮れた嵩鳥駅周辺は、そろそろクリスマス商戦に入ろうというのに、ネオンの輝きは中途半端だ。
そんな田舎駅とはいえ、帰宅ラッシュ時はそれなりの混雑を見せる。普段電車に乗りなれた者ならいざ知らず、のほほんと徒歩で学校に通う貴之やあかねには、毎日こんな人混みの中で生活するなど、とても信じられない。
「ああ、電車通学にしなくて良かった……」
「あたしもそれは常々思ってる」
貴之とあかねは、哀れむように庄治を見る。
「おまえら、俺にケンカ売ってるのか」
電車で二十分程の中宮市(なかのみやし)から通学している庄治は、普段は帰宅ラッシュ前に下校する事が多い。寄り道をして遊ぶにしても、大都市である中宮へ移動してからの方が効率もいいのだ。
だが、今日の庄治は最も混雑する時間帯を狙いすましたかのように嵩鳥駅へと辿り着いた。あの肉詰めピーマンさえ食べなければこんな事にもならかっただろうと内心やりきれない気持ちでいるところに、このバカップルの憐憫の目である。
「まぁ、いいや。たまに相馬とダラダラとダベるのも悪くなかったしな。天ヶ瀬と下校ってのも中々新鮮だったし」
「そうだな、たまにはいいな」
「だろう? たまにはな」
ハハハッと青筋を立てながら互いを牽制しあう男子の様子は、女子からすれば理解しがたいものかもしれない。あかねはやれやれといった様子で電光掲示板を見る。
「丘村、もうすぐ電車くるみたいだけど?」
「おおっ、さんきゅ。気をつけて帰れよな」
「大丈夫よ、貴之が送ってくれるもん」
だからこそ危ないんじゃないかとからかおうと思ったが、あかねの横に立つ悪友からの殺気を感じ、その言葉を飲み込んだ。
「じゃあな」
「おう、また明日」
「ん、明日ね」
軽い挨拶を終え、庄治は二人を残し改札へと消えていった。
「よし!」 あかねは、くるりと振り返って貴之に微笑みかける。
「せっかくだし、軽くなんか食べていく?」
「ん、今日はもう遅いし止めておこう。それに買い食いすると太るぞ?」
「うわ、失礼な事言うわね。どっちかっていうと、太るのはあんたの方でしょ」
違いないと貴之は笑った。しかし返ってくるはずの彼女の笑い声はない。あかねを見ると視線を落とし、何か考え事をしているかのようだ。
「……どうした?」
「んーん、なんでもないよ」
「んじゃいいけどさ……ほれ」
そう言いながら貴之は、あかねに手を差し出す。
「あ……」
「ほら、さっさと帰るぞ」
あかねはウンと照れくさそうに頷いて、その手を握り返した。
商店街を抜け、住宅街に入った二人は見慣れた道を歩く。
そこはかつて凪と三人で歩いた道だ。あれからまだ半年も経っていないと言うのに、あの夏が遥か昔に感じられるほど懐かしく思われる。
凪は貴之を信じてあかねを託した。彼はその気持ちに応えるために、どんな些細な事からでもあかねを守っていこうと覚悟を決めている。あの日、この我侭で暴れん坊で、でも本当は気の弱い夢見がちなお姫様を一生守ると誓ったのだ。
だが一介の高校生である自分が、あかねの理想とする王子様を演じ続けることはできるのだろうか。一生あかねを守りきるだけの力があるのだろうか。……本当にあかねを幸せにできるのだろうか。そんな不安が頭の中を渦巻く。
「……ねぇ、貴之聞いてる?」
「え?」
「うわ、聞いてなかったか」
「悪い、ちょっと考え事してた」
「ふーん」
――あかねは貴之の顔をチラりと横目で見る。
あかねの手をギュっと握り締める彼は、難しい顔をしながらも彼女の歩調に合わせて歩いている。こんなところにまで気遣いを見せる貴之に、あかねは嬉しくなると同時にやるせなさも感じていた。
どうしようもなく遠い。
貴之はこんなにも近くにいてくれるのに、あたしの心はどうしてこんなに離れているのだろう。
「違う、逃げてるだけ……」
すぐ隣の貴之にも届かないほどの、か細き呟き。
『あかねが幸せなら、自分の事はどうでもいい』
貴之は絶対に自分を見捨てないと確信してしまっているからこそ、彼の口から直接その言葉を聞いてしまったら、あかねの心は折れてしまうだろう。
だから、距離をおこうとしているのはあかね自身。
そうやって自分の人生を背負い込む事で、貴之が不幸になってしまうのではないかという恐れが、あかねを苦しめる。
にも関わらず、あかねの心は彼の隣にいつづける事を望むのだ。
彼にとって自分が負担になっているとわかっていても。
彼を解放する為にこの場から逃げ出したいと思っていても。
本当に好きだから、彼を信じて寄りかかっても生きてもいいはずだ。
でも、本当に好きだからこそ、彼を苦しめるような事はしてはいけないのではないだろうか。
「貴之ってさ……」
あかねはポツリとつぶやくと、つないだ手を離し、少しだけ距離をとって前を歩きだした。
あまりに話を聞いていなかったために機嫌を損ねてしまったかと、貴之はあかねの背中に慌てて声をかける。
「ありゃ、悪かったよ。大事な話だった?」
「別にそういうわけじゃないけど……なんていうかさ、貴之って優しいなぁと」
背中を向けたままあかねはそう答えた。
「なんだよ、唐突に」
「うーん、なんかさ、ちょっと自分が惨めっていうかさ。ちっちゃいなーと思っちゃったの」
よくわからないな、と困惑気味に答える貴之に、わかりませんか、と明るく答えるあかね。
先を歩くあかねは、角を曲がると小走りになってさらに貴之との距離を開けた。貴之は思わずあかねを呼び止める。
「あれ? おい本当にどうしたんだよ?」
彼女は一瞬の沈黙の後立ち止まり、振り返った。
街灯の光で映し出された彼女の顔。その頬にはひとすじの涙。
「うん、優しすぎてさ……ちょっと辛い」
言葉を失い、呆然とあかねを見つめる貴之に、彼女は悲しげに微笑む。
「……あたしの料理、まだまだ人に食べさせるのは早かったみたいだね」
――そして、今にも消え入りそうな少女は、その唇から少年が最も聞きたくなかった言葉を紡ぎ出した。
……ありがとう、嘘でも美味しいって言ってくれて。
―― Next #03